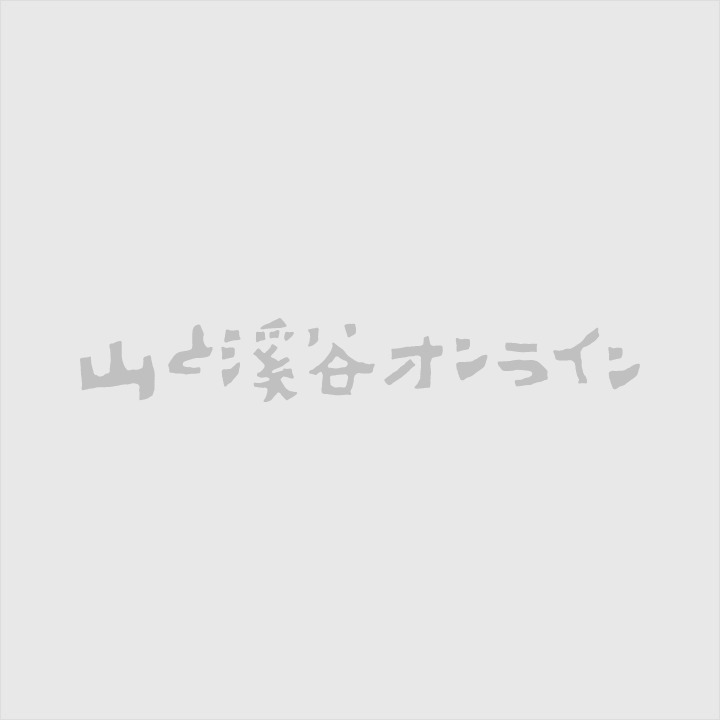行程・コース
行程・コース
天候
初日:晴れ、2日目:晴れ、3日目:快晴~大きな雲が浮かぶ ※2日目雨予想が大きく変わり360°見れるほどの快天に
利用した登山口
登山口へのアクセス
タクシー
その他:
沢渡バスターミナル前駐車場2:30着満車。その脇にさらに大きな駐車場ありまだ数台のみ、そこに駐車。さすが車の数が半端ないほど多い。バスは5:00発で3:30に1番に並ぶ。その後3・4番目の人とタクシー相乗りにして、4:24沢渡発。上高地ゲート前に待機。4:55ゲート通過。猛スピードでタクシーは走り、5:05に上高地着
この登山記録の行程
【1日目】
上高地バスターミナル(05:10)・・・河童橋(05:14)・・・明神(06:07)[休憩 5分]・・・徳沢(07:13)[休憩 10分]・・・横尾(08:07)[休憩 10分]・・・本谷橋(09:15)[休憩 15分]・・・涸沢(11:57)
【2日目】
涸沢(04:30)・・・ザイテングラート取付(05:48)[休憩 20分]・・・穂高岳山荘(07:26)[休憩 20分]・・・奥穂高岳(08:40)[休憩 70分]・・・穂高岳山荘(11:00)[休憩 70分]・・・涸沢岳(12:36)[休憩 60分]・・・穂高岳山荘(14:00)
【3日目】
穂高岳山荘(05:18)・・・ザイテングラート取付(06:38)[休憩 10分]・・・涸沢(07:50)[休憩 40分]・・・本谷橋(09:50)[休憩 10分]・・・横尾(11:05)[休憩 25分]・・・徳沢(12:36)[休憩 30分]・・・明神(14:01)[休憩 10分]・・・河童橋(15:00)・・・上高地バスターミナル(15:05)
高低図
標準タイム比較グラフ
 登山記録
登山記録
行動記録・感想・メモ
小学生のころ上高地に出かけた。河童橋の脇に望遠鏡をセットして穂高岳の頂上が見えるよと手招きしてくれた人がいた。何が見えるんだろうとその望遠鏡を覗き込んだ。そこには頂上に立つ1人の登山者がいて大きく手を振っていた。えっ、あんな高いところに人がいる⁈と子供心にも大きな驚きだった。その人のことかスーパーマンに思えた。
そしてこのスーパーマンに自分もなることが出来た。夢ってかなうもんなんですね。登山を始めた頃は、高所恐怖症で、奥穂高岳なんて夢のまた夢の存在。自分が登るにはいくつものハードルを超えないと無理とわかった。やっぱりあの人はスーパーマンなんだと奥穂に登ろうなんて考えもしていなかった。3年くらい登山をしてみると、大きな変化が訪れた。ほんの少しだけど高いところが楽しめるようになっていた。その時自分もスーパーマンになることは出来ないだろうかと、奥穂高岳への憧れは本気に強くなった。この3年は八ヶ岳で岩場や高度感になれるよう赤岳、横岳、阿弥陀岳、権現岳と奥穂高岳に登りたい一心で練習を積んだ。そしてこの9/19から21にかけて、奥穂高岳へチャレンジしてみようと決めた。コロナ渦で一度は断念もしたけど、山小屋を予約し、夢は現実に近いた。ところが行く1週間前から天気予報は雨。天気を恨みもした。でも今回は台風が近づいているなら諦めもつくけど、そう言うわけではないので、とにかく涸沢までは行くことに決めた。山の天気は大きく変わるとよく悪い意味で使われます。でも実際に雨だと言われていた天気が良くなったなんて言うことは幾度となく体験してきた。自分は天気運は良いんだと信じて、現地の天気で判断をすることにしようと思った。山小屋の予約状況が満室から予約が取れるように変わった。それは悪天候でキャンセルした人がいたということ。ところが行く数日前から天気は好天してきた。でも、自分が登頂する予定の9/20はやはり天気予報は雨のまま。9/18金曜日朝決行と判断。その夜大きな夢を目指して諦めず車を走らせた。
(初日)
夜中の2:30、沢渡の駐車場に着いた。なんとバスターミナル前の駐車場は満車。その横に1段下がった駐車場があるので、そこはまだ数台だったため駐車場に停めることが出来た。
次はバス。5:00発が1番のバス。3:00にバスのチケット売り場に行ってみるとまだ誰も並んでいない。少し眠ろうかとも思ったが、せっかく早く来てとにかく1番のバスに乗りたいので、おにぎりを食べて、3:30に並んだ。1番だった。程なく次次と並び始めた。タクシーの受付が4:00に電気がついた。先頭に並んでいた4人で、タクシーの相乗りをすることになった。その方が料金が安くすむし、なんと4:24に出発となった!上高地のゲートに4:40着。しばらく時間があったので相乗りした人たちと山話で盛り上がる。小梨平でキャンプをはり、1人は前穂高へ、そしてもう1人は西穂高へ登るそうです。それにしても1日で行って帰ってくるっていううんだからすごいなあと感心。そしてゲートは4:55に開いた。タクシーは飛ばす!5:05にバスターミナルに到着。なんとまだ暗い。ヘッドライトを用意して5:10まずは涸沢へ向けて出発。
河童橋からみる奥穂高岳は無気味に暗い。頂上は雲で見えない。天気に負けてたまるか!ってそのとき思った。明神に着くころにはすっかり明るくなり、明神岳が頂上部が雲をまといなんとも格好いい。1時間後、徳沢、そしてさらに1時間後横尾に到着。まっすぐ行けば槍ヶ岳、横尾橋を渡れば涸沢。大きな分岐点だ。もちろん涸沢に向け出発。横尾橋には長野県警の方が一人ひとり登山者と話をしていた。もちろん私とも会話になった。「どちらまで?」「涸沢で1泊」「次の日は?」「天気次第ですが、奥穂高岳です」「明日は雨の予想なので無理はしないように判断ください」と言われた。もちろんその通り!楽しんでこその登山。無理をしに来たのではない。でも、天気は変えてやる~!ってそのとき心で叫んでいた。
横尾橋から先はやっと登山道らしくなってくる。途中、天気は青空になっていて、なんと北穂高岳がどっしり青い空に鎮座しているではないか。すごい!なんか最高の天気!この勢いで明日も晴れてくれ・・・。
本谷橋に到着。吊り橋を渡り、しばし休憩。ここはこれから先の急登を登る前の一休みとして快適。それにしてもここまで意外とペースをあげてしまっていた。けっこう疲れてた。そのつけは涸沢への登りでいきなり来た!コースタイムよりもはるかに遅く、やっぱりペース配分はちゃんと保たないとなっと反省。でも気持ちははしゃいでしまってね。
本谷橋から先はいきなり急登、しかも登山道はよく整備されていて、ほぼ階段状になっている。つまりずっと階段をのぼっているのと同じってわけです。前半を飛ばし、ここでいきなり崩れ始める。といってもだんだんと涸沢カールが見えてきて、テンションがあがる。とにかくこういうときは1歩1歩進むだけです。そして本日お世話になる涸沢ヒュッテに12:00前に到着した。
ヒュッテのテラスにでるともうそこはアルプスの少女ハイジの世界。前穂~吊尾根~奥穂~涸沢岳~北穂と3000m級の峰々に囲まれる。9月も下旬に近づいているのにまだここは夏っていう印象。意外と暑かったです。太陽が眩しい!空の青、白い雲、白い岩、緑の木々が織りなす光景は言葉ではいううことができないほど、優雅で奇麗な光景。写真たくさんとりすぎて大騒ぎです。
午後はのんびりとハイジの世界を堪能し、でも夜遠し走って来たので、睡魔が襲う。しばし仮眠が気持ちよかった!夕飯もばっちり、美味しかった。
次の日は、夜中4:00出発予定。なので3:00に起きて、そのとき、もし穂高の稜線がくっきり見えて、風がないようなら、行こうと決めました。あとは運を天に任せて・・・
(2日目)
夜中3:00。外にでる。なんか靄がかかっている⁈テラスにでてみる。空を見上げる。そこには漆黒の闇のなかに燦然と輝く穂高の稜線がほんとうにくっきりと浮かび上がっていた。もちろん雨は降っていない。そして驚いたことに無風。なんか扉がそのとき開いた気がしました。「旅人よ、おまえの夢をかなえてこい」といってくれているかのように道を開けてくれたと思った。急ぎ支度をし4:00真っ暗の中ヘッドライトの灯を頼りに登山道を進む。選んだのは涸沢小屋からのルート。残念ながら真っ暗な道なので、写真を撮ることもできなかったが、登山道は結構岩場の道で急登。キツイ!そしてほぼ中間地帯からゴーロ帯に突入。これがどう進んでよいのかほんとにわからない。○と↑をみつけようとするが、全然見当たらない。スマホの地形図から判断して間違ってはいないので、方向だけミスらないように登ってみる。とマーキングが・・の連続で意外と苦戦。明るければそんなに大変ではないはずなのにつらいし、不安で怖くなる。こういうときにヘッドライトの電気が切れたらどうなるんだろうとか考えてしまうのはなぜだろう?
ゴーロ帯をなんとか進み、パノラマコースとの分岐点にほどなく到着。ここまでくるとやっと景色がわかるくらい明るくなってきた。斜めまっすぐの登山道をザイテングラードへ向け登る。そしてここでなんと!涸沢岳がピンク色に~!モルゲンロートをなんと1番最前列でみてしまった感じ。時間はわずか30秒。一瞬の出来事(もちろんシャッターはきりました)。感激です。日の出からわずか30秒で太陽が少し上部の雲の中に入ってしまったので、ほんとの一瞬でしたが、長さは関係ない。燃えるピンク色が今も目に焼き付いてます。
そしてザイテングラード取りつきに到着。ここで朝ご飯です。お弁当を食べた。出発してからもういろいろありましたが、食事で活力が沸いて、いざザイテングラードへ。
ザイテングラードは岩の迷路というくらい、面白いほど入り組んだ登山道を進む。浮き石も多いので注意しながら進むが、言われていたほどの恐怖な感じはしなかった。高度感は確かにあるが、これまでの練習のおかげか、その高度感を楽しむ自分がいた。「楽しい!」と心がなんか叫んでる。核心部といわれる鎖場と梯子の連続する場所に来た。鎖場は確かに注意が必要。急斜面をトラバースして岩を巻いているので、足場の岩をしっかり確認して、三点支持で注意して登る。梯子は楽ちんです。その後岩が鋭くなり、そこを縫うように登山道はどんどん高度を上げます。振り返るともう涸沢が下に小さく見える。すると「ホダカ小や20分」という文字が岩に書かれた場所に来る。え、もうあと20分なのと思うくらい、思っていたよりも苦戦ではなかった。ほどなく登山道も階段状になってきて、もう目の前に赤い穂高岳山荘の建物がそこにあった。
穂高岳山荘着。この小屋にくるのも憧れでした。正直ここまででも充分と思っていたほどです。そしてその小屋の左には、垂直な岩壁が立ちはだかっています。ここを登る。なんども映像や写真を見たけど本物はやはり怖いなあ・・・まずは穂高岳山荘で奥穂への準備。ザックから不要なものを出し、身軽にして奥穂へチャレンジです。荷物は自己責任で、食事のできるスペースの壁沿いか外に並べておいておける。
さあ、いざ、奥穂へ。あとこの壁さえ攻略できれば、夢に思っていた奥穂の頂に立てる。ここだけだ。人工的につくられた石段を登る。岩が近づく。平坦なところに一度でるが、目の前には頑張れよと言っているような笠ヶ岳が頂上に雲一つなくなんとくっきりと見える。風が飛騨側から少しでてきたが、思っていたよりも弱い。これなら登れる。そこに垂直な岩の壁が立ちはだかり、鎖場を4本の手と足で、登る。登りきると平坦なテラスのよう場所にでるが、そこに梯子がかかっている。梯子はほぼ垂直に2段。正直怖いです!でもいろんなことをここまでやってきて、いまここにきている。目線は上を見ているわけではない。もう十分渡り歩けるはずだと信じて梯子にとりかかる。梯子にピッタリくっついてはいけない。足が動けるだけの空間をつくってあげて、足の踏み場を目で確認できることが大切。梯子から胸を離す。怖くない。できる。そう信じて、梯子を2段登りきる。高度はさらにあがり、風も強くなった。そしてここからが岩場のトラバース。すれ違うのもけっこう狭くて大変。鎖場の連続です。最後に極めつけは、○とマーキングされた大きな岩をつかみ、一歩大きく空間に足を踏み出さねばならない場所がある。もちろん空間というのは、下は切れ落ちた崖。穂高岳山荘の赤い屋根が下に鮮明に見える。一歩大きく踏み出すというのが本当に怖い!でもそうしないと進めない。勇気を奮うポイントです。
超えた!超えた!超えた!やったー攻略した!まるで頂上についたようなはしゃぎよう。ここさえ超えればあとは、頂上に向けてただ進むだけ。危険個所はもうない。つまり奥穂の頂上に立てるということ。頂上に向け進む。振り返れば、なんと槍ヶ岳がどんと穂先を天に突きさしている。右には全部をさらけだしている笠ヶ岳、その奥には、自分が一番登ってみたい黒部五郎岳までも見える。天気が悪いって誰が言った!こんな登山日和はない!あきらめず登ってよかった。といううよりやっぱり天の思し召しかな・・。うれしいです。この登り意外と距離がある。稜線を歩き、飛騨側から突風にあおられる、左側は涸沢カールだがなんと切れ落ちている。見ためは怖くないけど、けっこうすごいところを歩いてると気づくと怖くも感じる。そしてそして、先には頂上が確認できた。あそこだ!とペースが速まる。もう怖かった鎖場や梯子のことはすっかり忘れている(笑)大きな岩をトラバースして登りきると、なんとジャンダルムがどんと姿を現す。ジャンダルムの頂上には人が2人たっていた。すごいなあ・・・ジャンダルム=傭兵の名にふさわしい風格。そして奥穂の頂上は目の前です。
奥穂高岳3190m、日本第3位の高峰。祠の立つ高い場所に立った。この山より高い山はこのエリアには存在しない。なにもさえぎることのない360°の大パノラマがそこに広がっていた。それも雲でさえぎられた山はない。すべてがしっかり見えるほどの大パノラマ。とうとうここに立った。夢がかなった瞬間です。子供頃は夢は結構かなうもんだったけど、年齢を重ねるともうそうは夢もないし、かなえるってことすら忘れていた。でも自分はまだ夢を持っていた。そして2020.09.20、その夢が今かないました。
もうひとつやってみたいことがある。それは頂上から上高地を見下ろすこと。どんな世界なんだろうと夢見てきた。霞沢岳と焼岳の間にあって、遠くには乗鞍岳、さらいその先には御嶽山。このシチュエーションの中央に梓川が流れ、河童橋が見えた。小さい・・・。
そしてやってみた。大きく手を左から右へ、右から左へ、降ってみた。もしかしたら、河童橋からこの姿をみて、大きくなったらあそこに行ってみたいって思う子がいるかもしれない。自分がそうだったように、今度は自分が夢を与えたくなった。奥穂高岳にたてて、感無量。言葉ではうれしいとしか言えないけど、こみ上げるものが大きくて、本当に感動しました!
乗鞍岳・笠ヶ岳・黒部五郎岳・双六岳・鷲羽岳・槍ヶ岳・常念岳といくつもの百名山に360°かこまれ、夢見ていた奥穂の頂上は岩だらけのゴツイ頂きでした。こんな稜線を歩くと北アルプスはやっぱりすごいところなんだなあと感心させられるし、これからも北アルプスをもっと歩いてみたいと思った一瞬でもありました。
奥穂高岳最高!!
フォトギャラリー:97枚

2日目真っ暗な中、涸沢小屋脇からゴーロ帯を進んで、ザイテングラードとりつきまでのガレ場を進む。やっと朝を迎え辺りが明るくなってきた・・!

次の瞬間、ほんの30秒ほどでしたが、モルゲンロートが辺りを赤く染める。目の前に赤ーく染まった穂高岳・涸沢岳が本当に見事なほど奇麗だった。

ふと振り返ると常念山脈が黒光りし、太陽は上部の雲の中に消えていた。モルゲンロートは最前列での観覧ができたようです。

さあ、これからいよいよザイテングラードです。足を速めて先を急ぎます。

ザイテングラード取り付き。ここから本格的な岩稜歩きになります。ヘルメットを装着して気合を入れます。ここで、朝食のお弁当を食べてエネルギーも補充です!

ザイテン↑と書かれた大きな岩の左を両手両足で登っていきます。

岩は大きくなり、最初のロープが張られた登山道を登っていきます。手がかり足掛かりがしっかりしているのでロープは不要です。

手前の岩壁がザイテングラードの核心部です。この手前が落石の危険もない広い場所があるので、ここで気合いを入れなおします。=休憩です(笑)

鎖場です。この鎖はある程度頼って、離さず登っていきます。高度感はあるといえばありますが、落ち着いて一歩一歩確実に進めば問題ないです。

鎖場を巻いていくと、次に現れるのが5段の梯子。大きな岩を登るために設置されています。高度感はないです。

核心部を超えると幾重にも折り重なった鋭い岩場になります。矢印を見ながら指示通り進みます。

↑○を確認しながら、どんどん高度を上げていきます。ジャングルジムでも登っているように、慣れてくると面白くなってきます。でも三点指示を忘れず、確認を怠らず、落ち着いて登ります。

ここで重要なメッセージが書かれた岩が目に飛び込んできます。「ホタカ小や20分」。えっ!もうそんなところまで来ているんだと驚きました。苦戦を覚悟で登っていましたが、ここまで順調。よし!もう一息=ここで休憩!とれます。

ここからは岩も少し小さくなり、登山道がなんとなくはっきりと刻まれているのがわかります。でも意外と高度感あるところ登っています。

振り返ると素晴らしい景色です。蝶ヶ岳~常念岳の稜線、眼下には涸沢のテント場がかなり小さく見えます。

と、気づくとはるか彼方に小さく見えていた赤い建物がもうそこまでに迫ってきました。白出のコルにある穂高岳山荘です。

もう目の前です。

穂高岳山荘到着です。ここに立てるなんてもう本当に嬉しかったです。ここにこれただけでも夢でした。
穂高岳山荘でザックを軽くし、いよいよ奥穂高岳へチャレンジです。

奥穂高山荘の目の前に巨大な垂直な壁が立ちはだかっています。これを攻略しなければ頂上にはいけない。高所恐怖症と戦い、これまでいろんな山で、この日を迎えるために練習をしてきました。いよいよ本番です。正直、怖いです。登る前先を行く登山者の動きを見ながら、確認をしました。
よし!行くぞ!

階段状に作られた岩の階段をあがり、穂高岳山荘の屋根の見える平坦な場所にでます。その先には、笠ヶ岳がどっしりと構えています。ここから飛騨側からの風が強まります。恐怖心は加速します。

平坦なところを先に進みます。つまづかないように慎重に・・・

一番奥まで行くと今度は空をほぼ垂直に見上げます。手足4本をつかい、よじ登ります。後半は鎖場になります。不思議に落ちたらそうしようとかは思わなかった・・・少しは度胸がついたのかな(笑)

垂直な壁を鎖をつかい登りきると、目の前にいよいよです。赤い梯子が目に飛び込んできます。ほぼ垂直に切り立った岩壁を登る2本の梯子場です。

さあ、登ります!これこそ基本に立ち戻って、梯子と身体は間隔を開けて、自分の足が見えるように、足はしっかりと地につけて、登っていけばよい。下を見ようなんて思うことはない。ひとつひとつの段差=梯子を登ればよいのです。

さすがに見下ろすと穂高岳山荘の赤い屋根が真下に見えて、かなりの高度感があります。ここはこの高度を楽しまないと・・・!高度感を楽しむなんて自分にはできない!?と思っていましたが、最近になって、もしかしてこんな感じのように少しだけ楽しんでいる自分もいたりします。今日はその気持ちで頑張らないと。

2段の階段を登りきると、岩場のトラバースで鎖場になっています。下山者と登山者のすれ違いがやっとで危険個所です。残念ながら写真がとれなかったのですが、一番最後のこの○印のついた大きな岩。ここはこの岩を両手でしっかりつかみ、足を一歩空間に大きく出し、ちょうどこの岩を右から回り込むように通ります。もちろん下は切れ落ちた岩場です。

超えた瞬間、なんか頂上についたくらいはしゃいでしまい、歓喜の雄たけびでした。少し離れてみると、これどこを通るのというくらい、道なんてないですよね。

歓喜の雄たけびのあと落ち着いてよくみると、穂高岳山荘の先にはもうひとつの3000m峰、涸沢岳がどっしり構えています。

登山道を少し進み振り返ると、なんと涸沢岳と北穂高岳の間に、槍ヶ岳の姿が飛び込んできます。

先は岩場の連続。でも危険個所はないです。落ち着いて落石を落とさぬよう高度を上げていけばよい。でも、頂上までは少し距離があるので、気合いを入れなおして、ここまで来たら頂上へは必ず行けると思うと、少し足早になりました。

真後ろには先ほどよりも槍ヶ岳の姿が全貌を観れるようになります。左右には涸沢岳と北穂高岳がたち、従えているかのようにも見えます。

右に目をやると、笠ヶ岳、黒部五郎岳、双六岳など、黒部源流域の山々も見えてきます。黒部五郎岳、憧れます。

目を真正面にすると、登山道もだいぶ歩きやすい道になってきました。ただ、風が飛騨側から吹き付けてくるので、この稜線歩きは風との勝負です。

左側に前穂高岳が見えてきます。この左側は切れ落ちた断崖になっているので、結構すぎる高度感があります。

そしてそして待ちに待った頂上が目に飛び込んできました!3つとんがった頂がありますが、その中央が奥穂高岳の山頂になります。もう一歩です。

振り返れば、槍ヶ岳がどんと中央にたち、ここまで歩いてきた稜線の登山道がはっきり見えます。

手前の三角の頂を右から迂回し、頂上へ近づきます。

そしてここを登りきると・・・

ジャンダルム!奥穂の傭兵に相応しいこの風格!よく見ると2人頂上に立っている。すごいなあ~

奥穂高岳の頂上はもう目と鼻の先です。

奥穂高岳3190mの山頂です。
私もこの上に登りました。この山より高い山はもちろんないので、360°の大パノラマです。すごい見晴らしろと高度感です。

頂上を前穂よりからみるとこんな感じです。

大天井岳から常念岳。常念岳はピラミッドみたいでやっぱり格好いい山です。大好きな山です。

穂高岳の吊尾根です。前穂高岳に向けて登山道が伸びています。

その先は、明神岳。

そして、眼下に広がる上高地。づっと上高地からこの奥穂の頂上を見上げていました。今日奥穂の頂上から上高地を見下ろすという大きな夢がかないました!こんな景色なんだね。頂上から見ると。大感激!霞沢岳・焼岳が左右に並び、中央には乗鞍岳、さらに奥には御嶽山と百名山が立ち並びます。頂上からの景色は大絶景です。

そして、ジャンダルム。

北の方に転じると、笠ヶ岳、黒部五郎岳。

そして最後は、涸沢岳、槍ヶ岳、北穂高岳。と360°の絶景が広がります。
憧れの奥穂高岳、日本第3位の高峰。まさか自分がここに立てる日が来るなんて、思ってもいなかったことです。夢ってかなうんですよ!

奥穂の登頂を終え、穂高岳山荘へ戻り、次はもうひとつの3000m峰、涸沢岳に向かいます。3000m峰は21座しかありません。なのでここまで来たら、登らない訳にはいきませんよ!

笠ヶ岳も応援してくれます。

そして、涸沢岳は3000m峰に登るという目的と、奥穂高岳の雄姿を見るということも大きな目標です。奥穂に登れば奥穂の姿は見えません。お隣の山に登れば、奥穂の全貌をみることができるのです。
穂高岳山荘から頂上まで登山道がつながっているのがよく見れます。

そしてあの格闘した梯子と鎖場です。よくもまああんな垂直な壁を登って下りたものです。

さあ、前を見て涸沢岳に進みます。

高度を上げると、前穂と奥穂の吊尾根がしっかり見えます。

岩場の登山道を一歩一歩高度をあげ、涸沢岳頂上はもう少しです。

涸沢岳3110m、日本第8位の高峰です。
乗鞍岳・仙丈ケ岳・奥穂高岳についで4つ目の3000m峰になりました。4/21ですね・・・

まずは、ジャンダルムと西穂高岳。西穂のピラミッド型も格好いいです。

そして、ジャンダルムと奥穂。これぞ岩稜帯ですね。

さらに、奥穂から前穂の吊尾根。穂高岳は大きいです!

西から北に順に目をやると・・・
笠ヶ岳。かっこいいですよね。

手前は三角点のある涸沢岳。
奥は黒部五郎岳、双六岳、薬師岳、鷲羽岳など黒部源流域の山々。

そして、もちろん、槍ヶ岳。憧れます。

常念岳。

ズームアップ!槍ヶ岳。

ズームアップ!北穂高岳。

ズームアップ!常念岳。

ズームアップ!笠ヶ岳。

ズームアップ!ジャンダルム。

ズームアップ!奥穂高岳。

涸沢岳からみた奥穂高岳!

穂高岳山荘の正面には、常念岳から蝶ヶ岳の稜線が広がります。初めのころこんなに長い稜線を何もわからず歩いたんだなと懐かしく思います。

穂高岳山荘から見る夕陽。

奥穂高岳への垂直な岩壁も夕陽にオレンジに染まります。

太陽が笠ヶ岳の右横に沈んだところ。

太陽が沈み、空が焼けたように前上がった。すごいこれは何?

笠ヶ岳の手前に雲海も広がり、夕陽のショーもこれで終わりです。しかしめちゃ奇麗だった。

ここからは涸沢です。
いろんな角度から涸沢を撮ってみました。まずはちょっと前まで高山植物で咲き乱れていたであろうお花畑帯と奥穂、涸沢岳。

パノラマコースから涸沢小屋

パノラマコースから奥穂、涸沢岳。

前穂と奥穂の裏吊尾根。

涸沢小屋と北穂高岳。

涸沢テント場から見た吊尾根

涸沢テント場から見た奥穂、涸沢岳。

涸沢テント場から見た涸沢岳と北穂高岳。

涸沢テント場から見た北穂高岳。

涸沢ヒュッテから見た吊尾根。

涸沢ヒュッテから見た奥穂高岳

涸沢ヒュッテから見た奥穂と涸沢岳。小さく穂高岳山荘が見えます。

涸沢ヒュッテから見た北穂高岳。

ズームアップ!奥穂と涸沢岳。

ズームアップ!奥穂高岳。

ズームアップ!奥穂の岩壁と穂高岳山荘。

ズームアップ!穂高岳山荘。

涸沢ヒュッテの夕食。

穂高岳山荘の夕食。

帰り際、上高地河童橋からみた奥穂高岳。頂上は雲の中でした。
装備・携行品
| アンダーウェア | ダウン・化繊綿ウェア | ロングパンツ | 靴下 | レインウェア | 登山靴 |
| バックパック | スタッフバック | 水筒・テルモス | ヘッドランプ | タオル | 帽子 |
| グローブ | サングラス | 着替え | 地図 | コンパス | ノート・筆記用具 |
| 腕時計 | カメラ | 登山計画書(控え) | ナイフ | 健康保険証 | ホイッスル |
| 医療品 | 虫除け | ロールペーパー | 非常食 | 行動食 | テーピングテープ |
| トレッキングポール | |||||
| 【その他】 シーツカバー | |||||