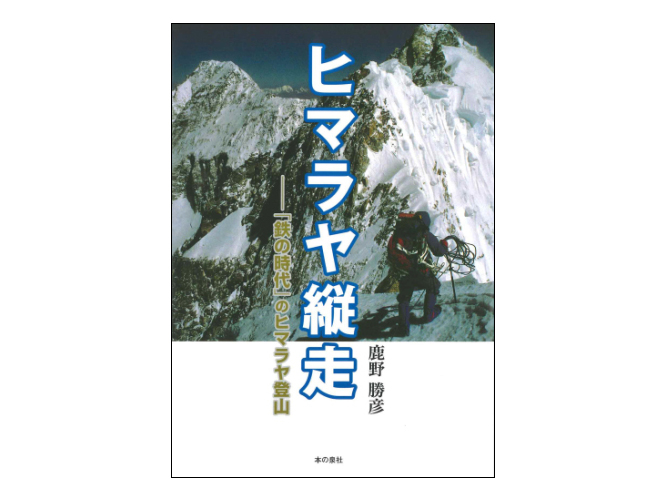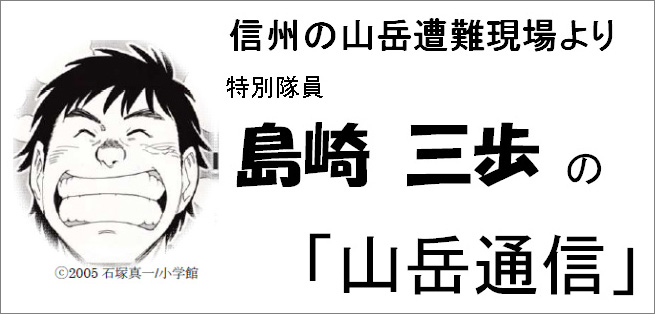1960年以降のヒマラヤ登山をたどる 『ヒマラヤ縦走 「鉄の時代」のヒマラヤ登山』
評者=中村輝子(ジャーナリスト、翻訳家)
今年は日本山岳会隊によるエベレスト(チョモランマ)登頂、50周年になる。ネパールが一シーズン、一ルート、一隊だけに許可する時代の第六登である。大学山岳部にも隊員推薦の呼びかけがあり、著者は東大スキー山岳部から参加、サウスコルまで登った。
その五年前には山岳部が挑戦したカラコルムの難峰キンヤンキッシュでも最年少で働き、雪崩遭難による撤退を経験した。では、その後の人生は、ヒマラヤ登山家の中に名をつらねる道を選ぶかといえば、そうはならない。組織の行動とリーダーシップの関係、プロ意識の高いシェルパたちへの親しみなどを経験し、元々が文化人類学に足を踏み入れた道筋として、南アジアが強く意識されてきたからである。
しかし、チョモランマ帰りの彼を待っていたのは、未踏峰チューレンヒマールを狙う若手OB・現役たち。その登山申請中に、双耳峰の南、西両峰も韓国隊と静岡大に登られたばかりとわかる。まさにジャイアンツ挑戦の黄金時代が過ぎて、大衆化が急速に進んだ鉄の時代の現実にまともにぶつかった。
その偶然のなりゆきから、著者は初の試みであるヒマラヤ縦走という形式――二ないし三の頂上をもつ山塊に、複数の極地法を同時に使い主稜線を縦走でつなぐ形をつくり出していく。サミッターだけを全員が押し上げる極地法とは違う“チームの文化”の創造――。
しかし、チューレンは実力不足もあり敗退した。その隊で歩荷役のシェルパのソナム・ギャルツェンが自分の判断でルート工作に取り組む異例の場面に強い印象を受ける。指示待ちでないシェルパの行動に気付く「目」が、さらなる企画や研究につながる。本書を貫く「縁」の始まりといえるだろう。
1973年に、RCCⅡがチョモランマ南西壁に挑戦する時、マネージャーを依頼される。ほとんどアルパインスタイルしか経験していない気鋭の登山家たちが、8000m級の気象と岩壁に苦しめられる。リーダーは撤収を指示し、東南稜からの登頂に切り換えた。登攀者はどう合意したか――計画の挫折や変更の共有という問題に著者はこだわり続けた。しかも未知の方法を探して――。
やがて著者の周囲から、ザイルの縁を再び、という動きが始まる。チーム全体の参加が表現できる登山、しかもインド隊と合同という条件――それが1976年のナンダ・デヴィ縦走だった。
東峰から主峰を結ぶ縦走は、二つの極地法で登頂しつつ、縦走隊がその間の未知の部分をつなぐ組み合わせ。全員が緻密な計画を理解してルート工作をし、縦走隊をタイミングよく迎え、送るやり取りはスリリングですらある。著者はこの計画達成が最も快心の山登りだったという。
また、1984年にはネパール登山協会合同で、カンチェンジュンガ西峰を除く三つの峰の縦走を実現させた。(ネパール政府にとって未踏峰扱いの)中央峰と南峰にネパール隊も登頂するという許可条件も適切な配置でクリアした。
登山の方法で、その行為を評価することはとうに難しい時代になった。商業登山ばかりが話題の中心である。ここでも試みられた“チームの文化”のありようは、社会的な上下関係から離れ、自分の気持ちで山の同意を得るように足を踏み出している、その伝え合い。この一書には物語のような膨大な日記がベースにあると思われる。
思い出すのは、シェルパのソナムである。著者と彼との付き合いは、次世代にも及び「一貫して誠実で頼りになる導き手」だという。ここに記された登山もシェルパも、今と地続きの歴史の一局面。次代に伝えることを促す好著である。
評者=中村輝子
1938年、北海道生まれ。ジャーナリスト、翻訳家。東京大学社会学科卒業後、共同通信社入社。編著に『生の時・死の時』(共同通信社)、訳書にジョー・シンプソン『死のクレバス アンデス氷壁の遭難』(岩波現代文庫)ほか。
(山と溪谷2020年8月号より転載)
登る前にも後にも読みたい「山の本」
山に関する新刊の書評を中心に、山好きに聞いたとっておきもご紹介。