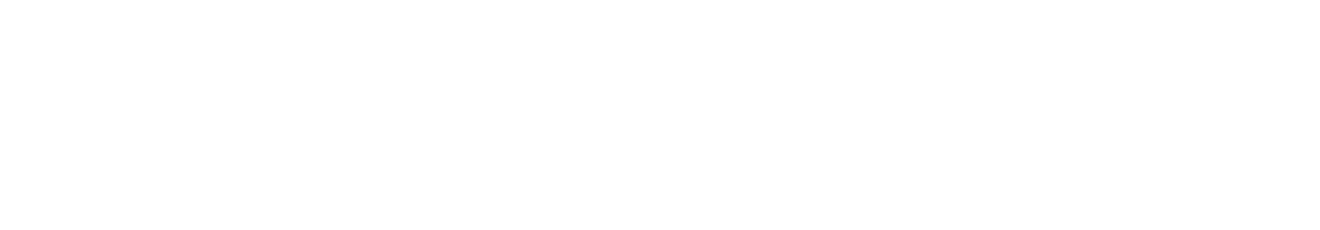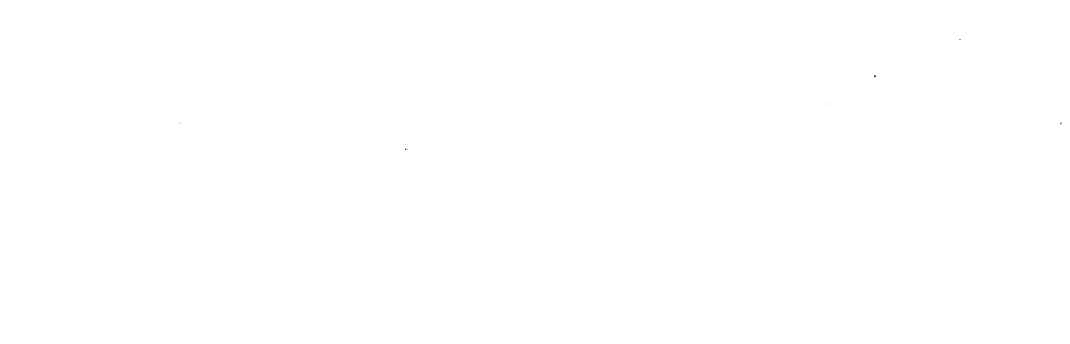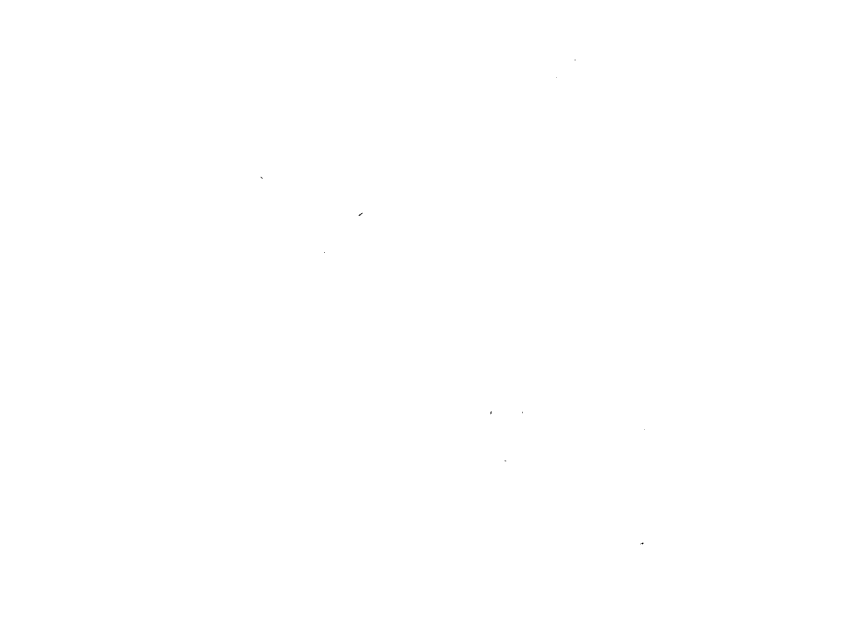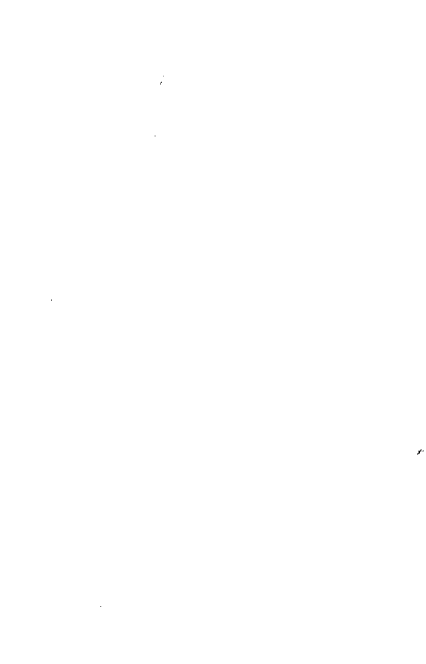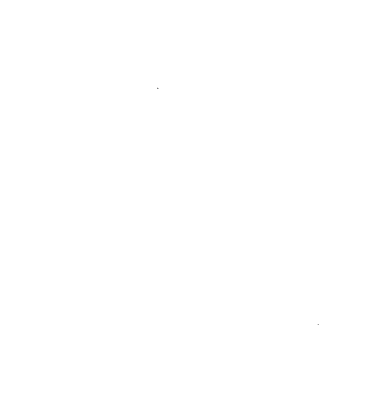冬山入門!
スノーシューで登る、
蛇峠山スノーハイキング
Jan.
27-28
本格的な冬を迎えた南信州・阿智村。1月27日(土)~28日(日)、雪に覆われた銀世界を楽しむスノーシューハイキングが開催されました。1日目は冬山の天気を学ぶミニ講座を実施、2日目に阿智セブンサミットの蛇峠(じゃとうげ)山(1664m)に登りました。当初は富士見台高原の予定でしたが、ゴンドラの不調により急遽場所が変更。当日は天気にも恵まれ、馬の背までの穏やかなスノーハイキングを楽しみました。
 眺望が開ける蛇峠山・馬の背。北アルプス・中央アルプス・八ヶ岳などの絶景が広がる
眺望が開ける蛇峠山・馬の背。北アルプス・中央アルプス・八ヶ岳などの絶景が広がる
冬山初心者も安心。
ゆったり旅を楽しむ1泊2日
今回のツアーは1泊2日。1日目は午後集合のため、公共交通機関を使っても、余裕をもって参加することができます。
集合場所は、阿智村のコワーキングスペース「レンタルスペース・昼神空間」。まず最初は自己紹介タイムです。参加者は5人とあって、アットホームな雰囲気で始まりました。30代から70代まで年齢も幅広く、そして登山経験もさまざまな方々です。阿智☆昼神観光局の登山ツアーは7回目ですが、リピーターも多く、なかには全回参加している方もいらっしゃいました。同行するのは、地元登山ガイドの伊藤賢治さん、阿智☆昼神観光局の酒井優佳さん、山と溪谷社の湯浅陽介、そしてこのレポートの筆者、横尾絢子です。
冬の天気や雪山について学ぶ
ミニ講座
自己紹介の次は、「冬山を楽しむための、やさしいお天気ミニ講座」が開催されました。講師は私、横尾です。気象予報士の資格を持っていて、これまでもライターとして気象の記事を書くことは多かったのですが、今回は講座の機会をいただきました。
前半は、冬山と夏山の違い、冬の天気サイクルなどについて説明し、大雪となる危険な天気パターンなどを紹介しました。後半は「お天気クイズ」を出題し、「ひょうとあられの違いは?」「世界で最も降雪量が多い都市は?」など全5問に挑戦していただきました。正解発表では意外な答えもあったようで、皆さんから歓声が上がると私もうれしかったです。最後はお天気談議となり、山で悪天候に遭遇した体験など、みなさんの天気に関するお話を聞くことができました。
昼神温泉の湯と、
南信州の味覚を満喫!
阿智☆昼神観光局の主催であるこのツアーでは、南信州の魅力をたっぷり味わえるコンテンツが凝縮されているのが魅力です。この日は「ユルイの宿 恵山」に宿泊し、南信州の味覚と温泉を満喫します。
温泉街を一望する落ち着いた和室で、ほっと一息。夕食までにはまだ時間があり、温泉に浸かってのんびりすることにしました。「美人の湯」として名高い昼神温泉は、アルカリ性が高く、つるつる、とろとろとした肌触りが特徴。穏やかな時間が、忙しい日常を忘れさせてくれました。
夕食には旬の食材を使った彩り美しい会席料理が並び、南信州の味覚に舌鼓を打ちながら、楽しい山談議に花が咲きます。食事の後には「山ビンゴ」大会が開催され、山のカレンダーや山グッズなどが、賞品として参加者に配られました。
蛇峠山でスノーシューハイキング
前日まで吹いていた風もやんで、登山当日は穏やかな冬晴れとなりました。
蛇峠山は「阿智セブンサミット」のひとつで、戦国時代の名将・武田信玄が狼煙台を設けたといわれる展望のよい山です。
「浪合パーク」で伊藤ガイド、観光局の酒井さんと待ち合わせ。荷造りをして、しっかり準備体操もしてから出発です!
しばらくは林道を歩き、別荘地の中を進みます。道の傾斜が緩く、雪も少ないため、ここではスノーシューを着けず、登山靴だけで歩きました。
別荘地を抜けるころには道もしっかりと雪に覆われてきたため、いよいよスノーシューを装着します。スノーシューは初めてという方もいて、伊藤さんが履き方をサポートしてくださいます。「かかとに着いているこれは何ですか?」という質問が参加者から上がると、「これはヒールリフターです。急斜面でこのように上げると登りやすくなります」と伊藤さんが教えてくれました。
伊藤さんによれば、スノーシューにも様々なタイプがあるとか。素材や形状、爪の数や付き方などの特徴によって、浮力を重視したもの、平らな場所に向いているものなど、得意なシチュエーションが異なるそうです。
スノーシューを付けると、裏側の爪がしっかりと雪に食い込んで、滑りにくくなりました。
「引っかからないように、少し左右の足の幅を広げて歩きましょう。スノーシューは持ち上げずに、自然に足を前に出すといいですよ」と伊藤さん。足のスタンスを広げて歩くのは、最初は少し違和感があったものの、30分もすると慣れてきました。雪の登山道でも楽に登れるのは、なかなか楽しいです。
スノーシューは深い雪でも足が沈まないようにする道具ですが、暖冬の影響なのか、この日は足元の雪も浅く、ほとんど沈みません。
「例年はもう少し雪が多いんです。植生が雪に隠れるくらい積もると、登山道以外の場所もあちこち歩き回ることができるので、もっと楽しいですよ。今年ももうちょっと降ってほしかったですね」と伊藤さんは少し残念そう。今回は夏道沿いに登りますが、雪の多いときにも経験してみたいものです。
八ヶ岳やアルプスなどの
大パノラマ!
絶景のなかで、
ぽかぽかランチタイム
次第に雲がとれて、青空が広がってきました。気温も上がってきたのか、登っていると暑いくらいです。汗をかかないようにゆっくりと登っていくと、突然視界が開けて、馬の背に到着しました。
 馬の背に到着!
馬の背に到着!
「すごい、全部見えますよ!」と伊藤さんが指差します。目の前には、南アルプス、八ヶ岳、乗鞍岳、御嶽山、北アルプスなどの大パノラマが広がっていました。参加者からも歓声が上がります。馬の背は、秋にはススキが美しいとのことですが、冬は植生が枯れるので、いっそう展望がよくなるのでしょう。
展望を満喫した後は、各自で持参したお昼を楽しみます。アツアツのうどんやお雑煮を作る方もいて、陽だまりのなかで、のんびりとランチタイムを楽しみました。
冬ならではの山の魅力
雪が浅く、登山道の幅が狭いということもあって、下山はスノーシューでなくチェーンスパイクで下山することにしました。軽アイゼンやチェーンスパイクは今日のようなコンディションの里山歩きに適していたようで、スノーシューよりも足運びが楽で、歩きやすく感じました。
下山はあっという間です。浪合パークに戻った参加者たちは、笑顔で「楽しかった」「景色がきれいだったね」などと感想を口にしていました。
銀世界に包まれた森、澄んだ空気に広がる絶景……。阿智の雪山を歩くことで、冬だからこそ楽しめる山の魅力があるということを、今回のツアーでは改めて感じることができました。
奥が深く、魅力が尽きない南信州・阿智村。これからも定期的にツアーが開催されるそうなので、ぜひご注目ください!
 登山ガイドの伊藤賢治さん(アルプスネイチャーガイド所属、登山ガイドステージII)。ありがとうございました!
登山ガイドの伊藤賢治さん(アルプスネイチャーガイド所属、登山ガイドステージII)。ありがとうございました!
(文=横尾絢子、写真=花岡 凌)