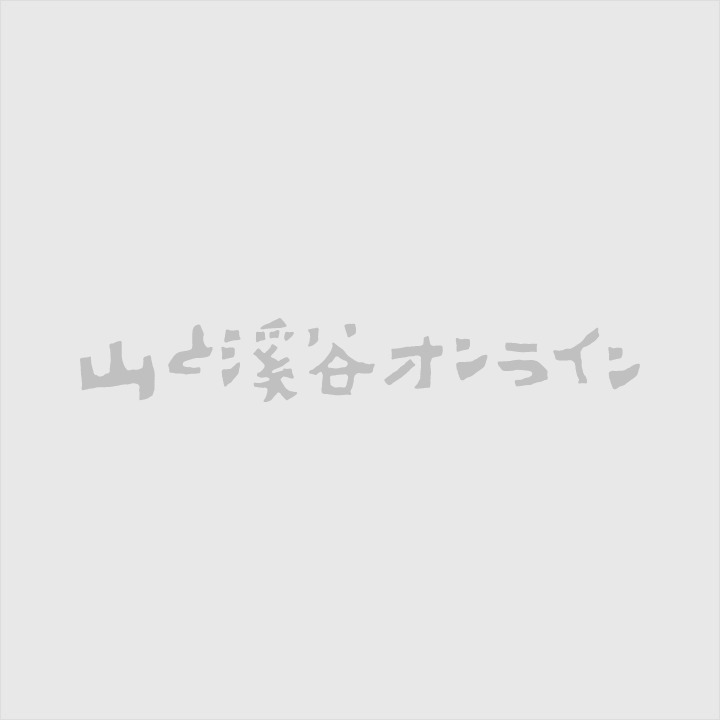行程・コース
行程・コース
天候
曇り時々腫れ
登山口へのアクセス
電車
その他:
往路:目黒→山手線→新宿→立川→青梅線→青梅→青梅線→軍畑
復路:青梅→青梅線→河辺→梅の湯→幸楽苑→河辺→青梅線→立川→南武線→武蔵小杉→東急目黒線→武蔵小山
この登山記録の行程
軍畑駅6:24→鎧塚6:27→柚木愛宕神社6:50→久石山不動尊6:52→即清寺7:02→吉川英治記念館7:07→宿薬師堂7:22→海禅寺・三田綱秀首塚7:30~42→枡形山城登山口7:47→枡形山城跡8:04~10→物見山8:20→名郷峠8:25→辛垣城跡8:35→雷電山8:58~9:10→マスガタ山9:31→ノスザワ峠9:36→三方山9:43→鷹ノ巣山9:50→矢倉台10:19→宮ノ平駅10:52→和田乃神社10:56→明白院(舘の城の山門移築)11:01→館(楯)の城跡11:09→天ヶ瀬八坂神社11:27→男井戸女井戸11:39→金剛寺11:40→森下陣屋跡11:45→中武馬車鉄道森下駅跡11:47→常保寺(猫地蔵)11:55→釜の淵公園12:02~10→雪おんな縁の地碑(小泉八雲)12:21~27→武尊神社12:31→昭和幻燈館12:42→住吉神社12:45→青梅駅12:54
合計6時間6分(休憩除く)
高低図
 登山記録
登山記録
行動記録・感想・メモ
4月3日(土)は、ようやくあきる野が終わったので、青梅に突入です。
青梅は平将門の子孫と称する三田氏という武士団の支配領域だったのですが、三田氏というのは良くわからない一族で、平氏系なのに秩父党の畠山氏を頂点とするネットワークともつるまず、一説によると鎌倉時代初期に畠山重忠が二俣川で討ち死にし、秩父党が滅んだ後、鎌倉幕府によってこの地を治めるように新たに派遣された一族で、もともと桓武平氏系の秩父党や村山党の支配領域だった青梅の支配を正当化するために同じ平氏系の平将門の子孫を名乗ったとも言われています。
仮に本当に将門の子孫だとすると、下総の将門の叔父である良文の後裔から分かれた相馬氏の系譜に乗っている相馬弾正忠胤実の子、胤興に三田弾正忠と注記して「家紋巴ヲ用」とあり、この三田弾正忠が青梅市の天寧寺に「大檀那平氏朝臣将門之後胤三田弾正忠政定」という銘文が刻まれた銅鐘を奉納した人物だとする説もあり、その場合三田氏は千葉から移住してきたことになります。
また、武蔵国荏原郡三田から起こったという説や、国立市の谷保の古くから三田氏館と呼ばれていた城山にある旧家に残る三田家系図には、「三田氏始め壬生吉志の姓たり」とあり、この壬生氏というのは御嶽山の武州御嶽神社を作った山の技術者集団で、それが土豪化したのが三田氏ということです。三田というのは「御田、神田」とも書き、元々は「屯田」=天皇の直轄地であり、府中に武蔵国府が築かれた時に使われた大量の材木は天皇の直轄地であった奥多摩から多摩川の水運を使って運び込まれたもので、壬生氏は元々それを切り出すために送り込まれた技術者集団ではないかと言われています。
三田氏は鎌倉時代から関東管領上杉氏の時代まで長きにわたり青梅を支配してきたのですが、小田原北条氏の時代になると、三田綱秀はいったん北条氏の配下に下るものの、信州に追いやられた上杉氏が長尾影虎(上杉謙信)を擁して関東に攻め入ると、再び上杉方に寝返り、辛垣城に籠城するも攻め落とされて、滅亡します。ただ滅亡したのはあくまで三田氏の宗家で、分家の一部は残り、後に徳川の旗本になった三田氏もいるそうです。
今日のスタート地点は青梅線の「軍畑駅」です。駅を出たらまず駅前にある「鎧塚」に寄って行きます。高さが9mもあるかなり大きな塚で、三田氏が滅んだ「辛垣の合戦」で命を落とした兵士の遺体や鎧・刀が埋葬された場所とのことです。
続いて多摩川を渡り、「柚木愛宕神社」へ向かいます。ここは即清寺の守護のために創建された神社なのですが、源頼朝公が畠山重忠に命じて即清寺と共に再建させたという伝説が残っています。愛宕神社の横の沢沿いにある「久石山不動尊」には鎌倉権五郎景政の念持仏と伝えられる不動明王が祀られています。でも後の岩の方が御神体っぽいです。別に、三田弾正の祖先で相馬師門の後裔師秀が辛垣城築城の際に、その鎮護のため愛宕神社を勧請したという話もありますが、辛垣城は北条氏との戦争のために新たに造られた城なので年代的に少し合わない気がします。
愛宕神社の次は、神社の別当寺であった「即清寺」に向かいます。弘法大師の甥、智証大師円珍和尚が諸国巡礼の折、寺の裏山、現在の吉野山園地の辺りに明王像を祀ったことが始まりといわれる真言宗豊山派の寺院で、その霊験を聞いた源頼朝が畠山重忠に命じて、伽藍を築かせ、関東に真言の教えを広めていた元瑜僧正を開山に迎えたといわれています。寺号の即清寺は重忠の真言宗での戒名、勇讃即清大禅定門から名づけられており、三田氏以前に秩父党が青梅に領地を持っていたのではという根拠の1つになっています。
再び多摩川を渡り、「宿薬師堂」へ向かいます。ここは小さなお堂なのですが、三田氏支族の神田家が、祖先を祀る堂宇として護持していたものらしいです。三田が神田と同義である好例です。
そして「海禅寺」です。ここは曹洞宗の三田氏の菩提寺だった寺です。三田氏最後の当主である綱秀の墓(首塚)と一族の墓があります。ただ首塚は墓ではなく、後世に作られた供養塔とも言われています。枡形山城のすぐ南麓にあるため、辛垣城落城の際兵火にかかり焼け落ち、さらに江戸時代にも火災に合い、今の本堂は元禄時代のものとのことです。
海禅寺から少し戻り、集落の道を山の方に入ると、「枡形山城」の登山道の標識があります。その登山道というか、作業用林道を登りきった場所が枡形山城跡です。枡形山城は辛垣城がある稜線に登る尾根の途中にあることから、その支城であるといわれています。海禅寺と繋がっているのでメイン通路だったのかもしれません。でも堀切や人工的に斜度を上げたような場所も設けられているので、敵にあえて登らせて、ここで一網打尽にする作戦だったのかもしれません。
「枡形山城」の尾根を登り切ると「物見山」に着きます。たぶん物見台だったのでしょう。物見山から自然の堀切のような「名郷峠」を越え、巻き道を見送って稜線を進むと、自然地形か人工地形か微妙な曲輪の跡があり、その先の虎口ような場所を登ると「辛垣城」の標識がある平坦地に着きます。その上の曲輪が辛垣山の山頂です。辛垣城は先ほども述べたように北条氏との戦争のために三田綱秀によって築かれた城です。城がある場所は青梅丘陵ですが、丘陵というより山なので攻略はかなり大変だったようで、北条方は城を落とすのに2年もかかっています。ここは、そんな山奥の割には思いのほか堀切や土塁などの遺構が残っているのが感動的なのですが、実は先週の勝峰山同様に石灰岩採掘の山で、その工事の跡も残っているそうなので全部信じていいものではなさそうです。
辛垣城まで来たので、ついでに雷電山にも寄って行きます。展望がないどうでもいい山だから行ってもしょうがいんだけどなーと思いつつ登ると、山頂には知らない立派な標識があり、北側の展望が開けていました。数年後には南側も伐採して大展望の山に変身してるんじゃなかろうか?
雷電山から元来た道を戻り、三方山経由で矢倉台まで青梅丘陵をハイキングします。雷電山から矢倉台手前の林道に入るまでは、登山者はあまりおらず、すれ違うのはトレイルランナーばかりです。当然マスクは無し。でも林道に入ると、マスクをして大声で会話している中高年のハイカーが一気に増えます。どちらが安全なのか?考えさせられます。
そして「宮ノ平駅」に下山したら、「和田乃神社」に寄って行きます。和田村の総鎮守だった神社で、メインの祭神は大山祇神、磐長比売神、茅野比売神なんですが、日向神社、波登神社、菅原神社、柳久保神社、細久保神社、熊野神社、愛宕神社、八雲神社、雨折神社を合祀していて、全部でなんと22もの神様を祀っています。
和田乃神社の下にあるのが、「明白院」です。三田氏の遺臣野口刑部丞秀房が開基の曹洞宗の寺で、本尊は勝軍地蔵菩薩。茅葺きの桃山時代の作風を残している貴重な山門は、次に行く「楯(館)の城跡」にあった田辺清右衛門邸の表門を移築したものだということです。あと米俵をかついだ狸の石像が有名で、ネズミが病気の狸にお米を運んだという伝説があるようです。
「楯(館)の城」は、辛垣城の支城的な城で、「辛垣城のある二俣尾地区入口への楯となる機能を有した城であるので楯の城と称する」ということで楯の城と呼ばれたらしいです。当然、辛垣城といっしょに落城。現在は民家が建っており、土塁のような物もあるのですが、線路沿いなのでハッキリとした確証は持てません。あと横の方に巨大な城壁のような物があるのですが、何か設備を造った残骸で、これは絶対に城とは関係ないと思います。
そして「天ヶ瀬八坂神社」と「男井戸女井戸」を覗いて「金剛寺」に向かいます。「八坂神社」は元は牛頭神社と呼ばれていたようで、そこに八幡神社と稲荷神社が合祀されているそうです。天ヶ瀬地区の鎮守社です。「男井戸女井戸」はまいまい井戸の一種かと思っていたら、河岸段丘からの湧水でした。いわゆる井戸のように地下に掘り下げた所から湧いているのではなく、自然の斜面から普通に湧き出している物を井戸と呼んでいたようです。今は女井戸の方は涸れていて、水が湧いているのは男井戸のみです。
さて「金剛寺」です。ここは真言宗豊山派の寺院で、勝峰山から青梅に逃れてきた平将門が、馬の鞭として使用していた梅の枝を地にさし「我が望み叶うなら根づくべし、その暁には必ず一寺建立奉るべし」と誓ったところ、この枝は見事に根を張り葉を繁らせたことから、京都蓮台寺の寛空僧正に開山を請たものの寛空は辞退、自刻の弘法大師像を送り、寺名を空海の灌頂号「遍照金剛」にちなみ「金剛寺」とし、安置された将門の念持仏・阿弥陀仏から無量寿院と号したといいます。この話は「梅の枝は立派に根付き、やがて花が咲き、 実を結ぶまでに育ったが、どうしたわけか梅の実はいつまでたっても青く、決 して熟すことがなかった。このことから「青梅」という地名が生まれた」という青梅の地名の由来の話と少し違うのですが、その整合性はどうなっているのでしょうか? ともあれ、将門の子孫の三田氏滅亡後も北条氏、徳川幕府からも手厚い保護を受けた青梅を代表する寺院とのことです。
金剛寺から青梅のメイン通りに出ると、「森下陣屋跡」があります。徳川家康が関東に入国した際に八王子に代官所が設置され、その出張所としてここに陣屋が置かれ、八王寺を焼け野原から復興させた大久保石見守長安がその任にあたったそうです。同じ場所にある「熊野神社」は陣屋の鎮守として建てられたものだそうです。
その道を渡った反対側に「中武馬車鉄道森下駅跡」があります。昔、狭山市と青梅市をつなぐ馬車鉄道(レールの上列車を馬が引く鉄道)があったそうです。
「常保寺」は臨済宗建長寺派の寺院で「招き猫地蔵」があります。あと昔はすぐ目の前の釜の淵を臨む景勝地にあった江戸時代の流行神の「白瀧不動尊」が、井伊直弼の子孫井伊直安子爵が別荘を造るというので、移転され、ここの境内にあります。
続いてその「釜の淵公園」へ行ってみます。ここは奥武蔵の巾着田を巨大にしたような多摩川の蛇行箇所に造られた公園で、青梅駅そばの川遊びのメッカになっている場所です。その他、桜も有名らしく、散りかけではありましたが、多くの人が訪れていました。河原にビニールシート敷いて桜を見物している家族連れがいたので、ここは宴会禁止にはならなかったようです。宴会は駄目か?
釜の淵公園から少し大回りして「調布橋」まで行くと、橋を渡ったところに「雪おんな縁の地碑」という物があります。雪おんなの話は、小泉八雲(ラフカディオ=ハーン)の『怪談』に収められているのですが、東北の話かと思ったら、八雲の家で奉公していた青梅の調布村出身の百姓の親子が語った話とのことでした。青梅、雪おんなが生息出来るほど雪が降るのかな~と思うのですが、地球温暖化の前は降ったのかもしれません。
昭和レトロな映画看板で有名な青梅を代表する建物である「昭和幻灯館」は映画館か観光案内所なのかなとっていたら、レトロな猫グッツを売っている店でした。ほかにも昭和の街並みなどのジオラマや映画看板を楽しむことができるようです。
その少し横にある「住吉神社」は、青梅村の鎮守で、町の真ん中に独立峰としてそびえる小山の上にあります。ここも、三田氏宗・政定父子および氏子の寄進によって、社殿を改修したり、社宝を奉納したりした記録が残っているそうです。あとここにも猫の神様がいました。青梅は猫で町興しをしようとしているのだろうか?
住吉神社から青梅駅に戻ったら今週の予定は終了です。三田氏にはまだ「勝沼城」があるのですが、回り方の都合で来週まわしとして、これから電車で河辺駅に移動して「梅の湯」に向かいます。
「梅の湯」は奥多摩をホームとしている登山者には説明不要の、河辺駅北口のビルに入っている日帰り温泉で、料金はGWや年末年始を除いて880円。泉質はph9.5のアルカリ性単純温泉です。温泉の浴槽が少ないのが珠に傷なのですが、奥多摩の帰りに寄るには駅から近くて便利な温泉です。そんな感じなので、緊急事態宣言も明けたことだし混んでるかなと思って恐る恐る入ったのですが、第4波の影響なのかガラガラに空いていました。土日は都心から登山者や特にトレイルランナーがたくさん来るので、地元の高齢者は避けているとも考えられますが、当面は混んで無さそうなので狙い目です。
梅の湯を出て、河辺駅周辺でラーメン屋を探すも見つからず、しょうがないので「幸楽苑」でか「野菜タンメン(塩味)」を食べて帰りました。珍しく写真を撮り忘れたので今日は写真無しです。幸楽苑の塩味は普通のタンメンの塩スープではなく、白湯スープを塩味にしたような色と味で、特に不味くは無いのですが、普通の塩味のタンメンを食べたくて注文したので違うのが出てきてイマイチでした。やっぱり塩ラーメンは塩ラーメンがいい。あと大手のわりにタッチパネルの使い勝手がイマイチなのも改善して欲しい。
中世の多摩散策コース(青梅市・羽村市・昭島市)
https://www.syougai.metro.tokyo.lg.jp/bunkazai/pro2016/tamajp.pdf
辛垣城 枡形山城 日向和田城 余湖 - 余湖くんのお城のページ
http://yogokun.my.coocan.jp/tokyo/oumesi02.htm
【河辺温泉梅の湯】公式
http://kabeonsen-umenoyu.com/