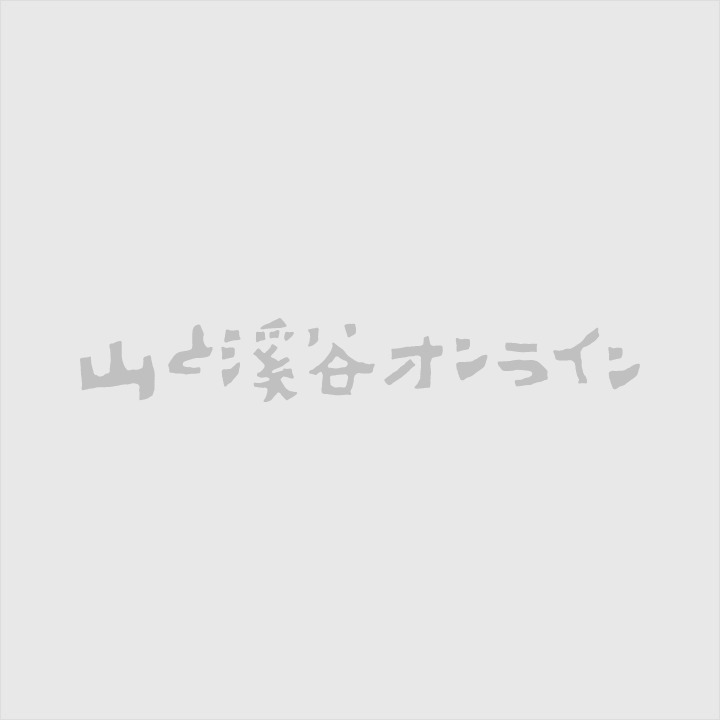行程・コース
行程・コース
天候
晴
登山口へのアクセス
バス
その他:
【往路】昭和病院前バス停・・・(立川バス)・・・国分寺駅・・・(国鉄中央線)・・・高尾駅・・・(徒歩)・・・十々里古戦場・・・(西東京バス)・・・造形大学前バス停
【復路】高尾駅・・・(国鉄中央線)・・・国分寺駅・・・(立川バス)・・・昭和病院前バス停
この登山記録の行程
西東京バス造形大学前バス停・・・北条氏照墓・・・八王子城跡・・・富士見台・・・尾根分岐・・・小仏関跡・・・国鉄中央線高尾駅
高低図
標準タイム比較グラフ
 登山記録
登山記録
行動記録・感想・メモ
【回想】出発は8時。立川バスと国鉄中央線を乗り継ぎ高尾駅へ。駅北口から高尾街道の登り坂を5分ほど行くと、道沿いに十々里古戦場(八王子市指定史跡)の案内板が出てきた。武田氏と北条氏(武田方の小山田信茂と北条方の横地監物)の戦いがあった場所で、小山田勢が横地勢を破ったという古戦場だが、今はその名残の欠片もみることはできない道路っ端だが、往時の様子に思いに巡らし先を急ぐこととした。
そのまま登り坂を進むとバス停があり、終点造形大学前(平成2年(1990)の移転まで東京造形大学のキャンパスが所在)まで乗車した。下車後向かう北条氏照墓(東京都旧跡)は、バス停から少し戻った左手の路地を奥へ進んでいくと小高い80mほどの丘の上にあった。ここも宗関寺の敷地内で、麓にある歴史資料館にも立ち寄った。
いよいよ本日最大の目的地である八王子城跡(国指定史跡)へ向かう。わずか446mの山だが小刻みに何合目かを示す標識が随所に見られた。八合目付近がかつて三の丸があった場所らしい。九合目からは木の間越しながら東面が一部開けてきて、関東平野の眺望を楽しんだ。頂上の一角に出ると八王子神社の大きな社が目前に現れた。最も高い場所が八王子城本丸跡。山頂全体は樹木に覆われ鬱蒼としているが、東面から南面にかけては雄大な展望を得られる。眺めの良い場所を陣取り昼食を摂った。大自然の中での弁当の味は格別だ。当初は来た道を戻る予定だったが、天候も良く時間に余裕もあったため、このまま前進し小仏方面へ下ることにした。途中の富士見台からは、その名のとおり純白の富士山を眺めることができた。カメラを持参していなかったのでこの絶景を収めることはできなかったが脳裏に焼きついている。富士見台からの下りはかなりの急坂で少々荒れ気味の道だったが、ほどなく中央自動車道沿いの道に出てしばらく並走(?)することになる。中央道と中央本線のガードをくぐると4時間10分に及んだ城山ハイキングコースは終わりを告げ、さらに進むと旧甲州街道の小仏関所跡(国史跡)に到着した。関所跡には建物はなく現在は公園になっている。真冬の穏やかな晴天のもと、史跡とハイキングを堪能する一日となった。
◆市指定史跡 十々里古戦場
「永禄12年(1569)10月1日、武田信玄の武将小山田信茂と滝山城主北条氏照の重臣横地監物とが一大血戦を行なったところである。この年、甲州の武田信玄は北条氏康の小田原城を攻めんとして甲州を出発し、碓氷峠を越えて武蔵方面の北条氏の諸城を次々と攻略しながら南下して、滝山城を攻めるため拝島に陣をしいた。一方信玄の武将、大月岩殿山の城主小山田信茂は小仏峠を越えて滝山城に向って押寄せたので、氏照の家臣横地監物等がこれを十々里の原で迎え撃とうとしたが、一戦にしてもろくも敗れ去ったと伝えられている古戦場である。」
◆都旧跡 北条氏照墓および家臣墓(宗関寺内)
「北条氏照は氏康の子で陸奥守を称した。滝山城主大石定久の後を襲い八王子に居住して、八王子、榎本、栗橋、小山などの数城を併有し、戦国時代広く勢力をもった。永禄12年(1569)9月武田勢と戦い、さらには天正18年(1590)小田原攻めのとき豊臣秀吉の武将前田利家、上杉景勝と戦い、このとき落城、7月11日小田原で自殺した。享年46。「青霄院殿透兵宗関大居士」。この氏照の供養塔は百回忌追善の際建立したものである。両脇は中山家範および信治の墓で、家範は八王子落城の際、城とともに討死した。中山勘解由家範である。中山信治は家範の孫で水戸藩家老中山備前守信治である。」
◆国指定史跡 八王子城跡
「八王子城は戦国時代の終りに近い頃小田原北条氏の一族北条氏照が、滝山城から移した城です。標高460メートルの本丸を中心に、小宮曲輪、松本曲輪をおき、さらにいくつもの曲輪を組み合わせてつくった山城で城域の総面積33万平方メートル関東屈指の大規模な山城です。城の特色は、それまでの多摩の山城ににはない石垣を持ち、それに空堀や土手、かきおろし(土でつくった急斜面)複雑な縄張り(配置)を持った点にあり中世と近世の中間的な形をもった城といえるでしょう。日常の営みはふもとの館でなされ、いったんことあればたくさんの曲輪にこもって戦うという考え方で築かれた城と思われます。天正18年(1590)6月23日、豊臣秀吉の小田原城攻めの一環として前田利家、上杉景勝両軍の攻撃を受けて落城しました。遺構から見ても城は未完成だったと思われ、その城にこもった地侍、農兵、職人、それに女子どもなど多数の人びとは、きびしい運命に見舞われて生命を落した人も多かったことでしょう。城主北条氏照は主だった家臣とともに、小田原城を守っていましたが、開城のあと兄氏政と自刃して果てました。城あとからは、今も当時の遺物等が出土し、なかには遠く中国から運ばれてきた陶磁器も発見されており、広大なアジア交易圏のひとつの終点だったといえる証拠です。また、城は落城後使用されず今日にいたっており、現在も遠い戦国の昔を語る貴重な曲輪や石垣、空壕等多くの遺構が残っています。指定面積 142万平方メートル」
◆国史跡 小仏関跡
「小仏関跡は、戦国時代には小仏峠に設けられ富士見関ともよばれた。その後、北条氏の滅亡により、徳川幕府の甲州街道の重要な関所として現在地に移されるとともに整備された。関所は、代官の支配下におかれ、元和9年(1623)以降4人の関所番が配備された。関所の通過は明け6ツ(午前6時)から暮6ツ(午後6時)までとし、しかも手形を必要とした。鉄砲手形は老中が、町人手形は名主が発行。この手形を番所の前にすえられた手形石にならべ、もう1つの手付き石に手をついて許しを待ったという。特に「入鉄砲に出女」は幕府に対する謀反の恐れがあるとして重視し厳しくとりしまった。抜け道を通ることは「関所破り」として「はりつけ」の罪が課せられるなど厳しかったが、地元の者は、下番を交替ですることもあって自由な面もあったらしい。明治2年(1869)の太政官布告で廃止され、建物も取りこわされた。面積 関所の旧構内と認められる遺跡の面積は約430平方米」