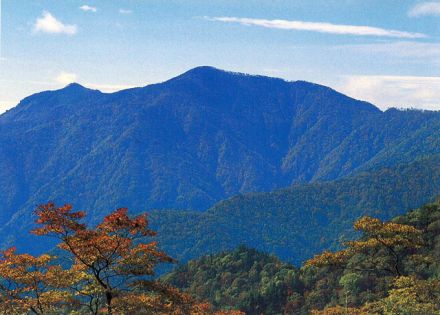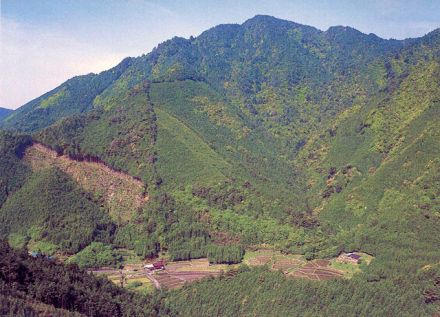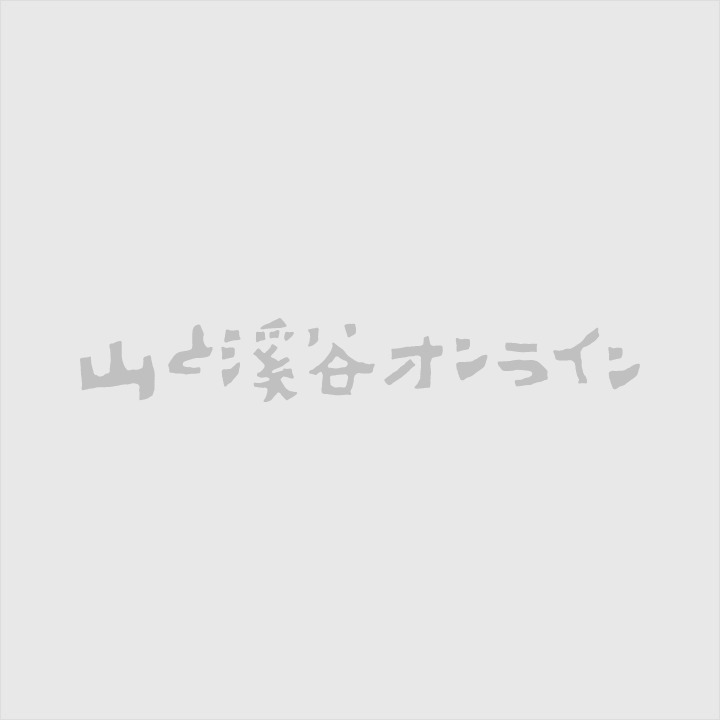行程・コース
行程・コース
天候
初日:晴れ後曇り 2日目:曇り時々雨・強風 3日目:晴れ 4日目:晴れ時々曇り 5日目:曇り後雨 6日目:晴れ時々曇り 7日目:曇り後雨
登山口へのアクセス
電車
その他:
近鉄吉野線・吉野駅で下車し、吉野ケーブルで吉野山駅へ。ここで路線バス(8:00~16:00にかけて30分または60分に1本。季節によって異なるのでHPで要確認)に乗り換えて終点・奥千本口まで約20分。バス停から金峯神社までは徒歩5分。早朝等でケーブルやバスが運行していない場合は徒歩(約90~120分)またはタクシー利用。
この登山記録の行程
初日:金峯神社(10:00)⇒四寸岩山(11:35)⇒二蔵小屋(12:40)
2日目:二蔵小屋(5:30)⇒大天井ヶ岳(6:30)⇒五番関(7:05)⇒洞辻茶屋(8:35)
⇒山上ヶ岳(9:40)⇒小笹宿(10:25 風雨で1時間停滞)⇒大普賢岳(12:15)
⇒七曜岳(13:30)⇒行者還岳(14:30)⇒行者還小屋(15:05)
3日目:行者還小屋(8:40)⇒一の垰(9:45)⇒聖宝宿(11:05)⇒弥山小屋(12:05)
4日目:弥山小屋(5:30)⇒舟の垰(7:35)⇒楊枝宿小屋(8:20)⇒両部分け(10:40)
⇒釈迦ヶ岳(11:35)⇒深仙小屋(12:30)⇒大日岳(13:05)⇒深仙小屋(13:20)
5日目:深仙小屋(5:20)⇒太古の辻(5:35)⇒天狗山(6:25)⇒涅槃岳(8:50)
⇒持経小屋(10:05)⇒平治小屋(11:25)⇒行仙岳(13:45)⇒行仙小屋(14:10)
6日目:行仙小屋(6:05)⇒笠捨山(7:25)⇒地蔵岳(8:35)⇒貝吹金剛(10:20)
⇒蜘蛛の口(11:30)⇒花折塚(12:55)⇒玉置山(13:55)⇒玉置神社(14:10)
7日目:玉置神社(6:20)⇒大森山(7:55)⇒五大尊岳(9:25)⇒金剛多和(10:15)
⇒山在峠(11:25)⇒七越峰(13:05)⇒熊野川奥駈起点(13:35)
⇒大斎原(13:55)⇒熊野本宮大社(14:30)
高低図
 登山記録
登山記録
行動記録・感想・メモ
GWを利用した大峯奥駈道縦走。この挑戦のため、半年前に本格的に登山を始めました。
縦走にあたり、最初に決断したのは「テントなし」で行くこと。ザックの重量を最大でも15~16kg程度に抑え、縦走中の巡航速度と体力維持を優先するためです。その代わり、数少ない山小屋等を泊まりつなぐスケジュールとせざるを得ず、行程プランの自由度がなくなりました。また、小屋の満員リスク回避のため早着も必須。結果的に、弥山小屋と玉置神社の2泊以外は無人の避難小屋(二蔵小屋、行者還小屋、深仙小屋、行仙小屋)を利用することになりました。テントを携帯すべきかどうか正解はわかりかねるものの、「山と高原地図」のコースタイムの7~8割の所要時間で歩き、小屋等においても寝る場所と休息をしっかり確保できたという点では狙い通りであったといえます。
行程中、危険個所として予め認識していたのは、①釈迦ヶ岳手前の岩場、②大日岳、③槍ヶ岳&地蔵岳、の3ヵ所。しかし、真に危険を感じたのは②大日岳のみで、その他は通常の体力・技術で十分にクリア可能なレベルだと思います。
道がわかりにくいと感じたのは、①小笹宿から阿弥陀ヶ森への登り、②阿弥陀ヶ森から脇の宿への下り、③稚児泊から七曜岳の区間、④仏生嶽への登り、⑤七越峯から備崎までの下り、の5か所。①②④は雨が流れた溝なのか登山道なのか区別がつきにくいので地形の読図とコンパスでの大まかな方向確認の併用がベターです。③は薄暗い樹林なので踏み跡がわかりにくい個所があるのでテープを目で追いかけることが必要でしょう。問題は⑤。ゴール間近で気がはやる中、テープはそこら中に手当たり次第に巻かれている感があり、どれが正しいのか非常にわかりにくいです。道は明確なんですが、コンパスを併用して、道が正しい方向に向かっているのかどうか確認が必要と思われます。これら5か所以外は道標もあり、はっきりした道なので迷うことはありませんでした。
体力的にキツイと感じたのは、①天狗山から涅槃岳に至るまでの区間、②倶利伽羅岳から怒田宿までの区間、③切畑辻から五大尊岳までの区間でした。いずれも南奥駈に入った後のこれでもかというアップダウンの連続する区間です。苦しい急坂をようやく登り切ったと思ったら目の前に急坂下りがあり、さらにその先には次に向かうピークが高くそびえているという図式です。ふくらはぎが攣りそうになるのでテーピングで何とかしのぎました。
雨に降られたのは通算2日程度。もともと多雨地域なのでこの程度はやむなし。レインウェアが邪魔で歩きにくいというのは事実ですが、カンカン照りで水分と体力を奪われるよりはずっとマシかもしれません。
飲料水の確保に関しては細心の注意が必要です。多少、ザックは重くなりますが汲めるときに目一杯汲んでおくことがおすすめです。確実に補給できそうなのは山上ヶ岳の宿坊、小笹宿、弥山小屋、玉置神社。比較的確度が高いと思われるのは持経小屋と行仙小屋。あまりあてにならないのは行者還雫水、鳥の水、深仙宿の香精水あたりでしょうか。いずれも2015年GW時点の状況です。
全般を通して言えるのは、①アップダウンの繰り返しに萎えない心、②10kmを60~70分で走れる程度の基礎体力、③早め早めの飲料水確保、が縦走成否の分かれ目ではないかと思われます。
フォトギャラリー:7枚
装備・携行品
| シャツ | アンダーウェア | ダウン・化繊綿ウェア | ロングパンツ | 靴下 | レインウェア |
| 登山靴 | バックパック | スパッツ・ゲイター | 水筒・テルモス | ヘッドランプ | 傘 |
| タオル | 帽子 | グローブ | 着替え | 地図 | コンパス |
| ノート・筆記用具 | 腕時計 | 登山計画書(控え) | ナイフ | 健康保険証 | 医療品 |
| 熊鈴・ベアスプレー | ロールペーパー | 非常食 | 行動食 | テーピングテープ | トレッキングポール |
| ストーブ | 燃料 | ライター |