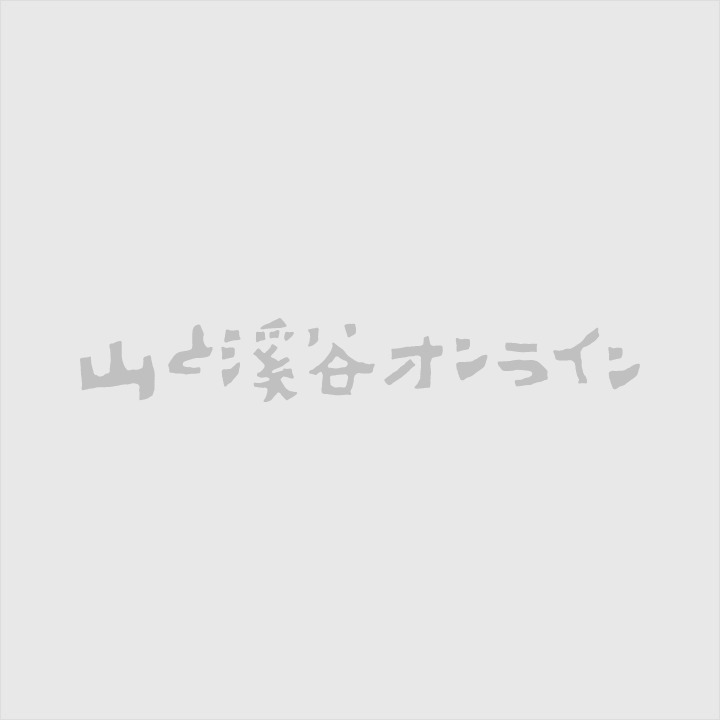行程・コース
行程・コース
天候
快晴
登山口へのアクセス
マイカー
その他:
GWだったのでバスで行こうと思いましたが、交通費もかなりかかってしまうので、車で大月ICで降りて139号を北上し松姫トンネルで小菅へ抜け、松姫峠の駐車場に駐車。松姫峠は12台駐車可能。トイレあり(バイオトイレでかなり奇麗)。4:30には松姫峠に着。1番乗りでした。
この登山記録の行程
松姫峠(05:17)・・・奈良倉山(06:01-06:46)・・・松姫峠(07:28-07:33)・・・鶴寝山(07:58-08:09)・・・分岐(08:33)・・・大マテイ山(08:59-09:26)・・・分岐(09:01)・・・分岐(09:56)・・・鶴寝山(10:21-10:55)・・・松姫峠(11:13)
高低図
 登山記録
登山記録
行動記録・感想・メモ
秀麗富嶽十二景五番山頂=奈良倉山へ行ってきました。
奈良倉山は、秀麗富嶽十二景選定時エントリーギリギリに変更によって滑り込んだ逸材の山です。最初は笹子雁ヶ腹摺山の予定だったそうです。それが急遽変更となって、見事に五番山頂に選出されました。きっとですが、選ばれていなければ訪れることはない山だったかもしれません。秀麗富嶽十二景はどこを登っても富士山が見事でできれば全部制覇したい秀峰の集まりです。ただ、この奈良倉山だけは他と違ってかなり離れた位置にあります。ほぼ奥多摩といってもいい山です。もうすぐ隣が三頭山です。上野原からバスで鶴峠に降り立って、この奈良倉山、そして三頭山にも登れます。今回は車で松姫峠まで細いカーブの多い道を通って、松姫峠をスタート地点としました。松姫峠自体がかなりの標高があって、ここからだと頂上稜線の縦走をすぐ楽しめるといったメリットがあります。
松姫峠ですが、あるお姫様がここを通ったことによって名前がつけられています。それが松姫さま。松姫さまは武田信玄の四女として生を受けます。当時は戦国の時代真っ只中で、武田信玄と織田信長の2大勢力があり、武田の松姫さまと織田の信忠との政略結婚になります。ところが徳川家康が台頭し、三方ヶ原で合戦が行われました。その時に織田信長は家康のために援軍を送ります。信玄は信長が家康に援軍を送ったことで、松姫さまと信忠との婚約を破棄となります。その後信玄の突然死、後を継いだ勝頼も天目山で討死し、武田家は滅亡。松姫さまは信玄の五男盛信の居城高遠城にいましたが、織田勢が攻めてくるということで、急ぎ甲府へ戻られますが、関東を指して落ちのびます。そのとき通過したのがこの現在の松姫峠と言われています。この険しい峠を通過したのは当時としてはすごいことだと思います。そしてその後陣馬山の和田峠を通過して八王子に着きます。そして広めたのが織物です。後世八王子織物として発展していくことになりました。そして八王子には松姫もなかというお菓子まであります。
と歴史の話が長くなりましたが、初めて松姫峠に立ち、こういったことが戦国時代にあったと思うととても考え深く、当時のことを知らなくても、そのお話に自分を置いてみたりしていまいます。松姫峠からは富士山も雁ヶ腹摺山、大菩薩連嶺も見えます。松姫さまもここまで来てこの景色をみてほっとしたかはわかりませんが、戦乱の世を生き抜くというのはとても大変なことなんだと思いました。
歴史はこのくらいにして、さあ松姫峠をスタートして、まずは奈良倉山へ行ってみましょう!
奈良倉山は、秀麗富嶽十二景に入っていたので、もちろん行ってみたい山として早くから知っていました。しかしなかなか山深くいくのが躊躇される感じでした。行くなら紅葉の秋か、新緑の春のどちらかで行ってみたいと思っていました。そして今回、挑戦してみようと計画をしました!最初はバスで鶴峠から登る予定でしたが、急きょ、車で松姫峠スタートに変更してトライです。これが大正解で、車でなおかつ駐車台数が10台くらいということだったので、なおかつGW。となりの道の駅小菅は超混む観光スポットだと知っていたので、車で行くなら必ず駐車できないとと思って夜中から出発して、4:30に1番乗りで松姫峠に着です。そして日の出前であったため、ここ松姫峠からも富士山が望め、朝陽が富士山に当たる朝の絶景を見ることができました!これは早起きの特権ということですね!車大正解です。松姫峠からの奈良倉山の登山道はなんか広い。まるでハイウェイです。充分に車が通れる林道という登山道です。行きは途中から分岐して左の山腹をトラバースして進む登山道で進みました。ほどなくするとまた林道に合流します。ここからしばらく林道を歩き、途中から奈良倉山の頂上に向かう山頂直下の登りになります。ちょっとした登りです。で、奈良倉山の山頂につきます。ところが秀麗富嶽十二景の山頂なのに頂上は樹林に囲まれて眺望はありません。実はここより南に坪山方面を縦走するルートに展望所があります!これが秀麗富嶽十二景の5番山頂の絶景です。人がまったくいなかったので、ここでのんびり時間をすごしました。数人しかすわれない展望所なので、多いときはここはすぐにぎわってしまいそうです。富士山は木と木の間に少し遠めに裾野を開いています。最後に滑り込ませたというのもなんか納得できるほど秀悦な富士の絶景です。
楽しみにしていた奈良倉山の山頂を後にします。それでここでどうしても見てみたいものがあります!ただ、どこにあるかは不明で登山道から少し離れている場所に「それ」があります。さきほど登山道は道幅の広い林道ということに言いましたが、その答えが「それ」です。奈良倉山から下りてきて林道にぶつかり、ちょっと進んだ行きに通ったトラバース道の合流手前に「それ」はありました。「それ」は、廃トラックです。トラックがそのまま壊れて放置してあります。登山道の広い道はこのトラックが走っていたということになります。またこのハイウェイの道はトレランのコースになっていて、ああ走りやすそうだと納得のみちです。帰りはこのハイウェイを通って松姫峠に戻しました。
これだけだとお散歩になってしまうので、今度は松姫峠から西へ行ってみよう!というコースにしました。松姫峠には「牛ノ寝大菩薩峠登山口」と看板がたててあります。これが西方への登山道の入口です。松姫峠からスタートだとここから鶴寝山と大マテイ山の2座を登ることが可能です。この登山道はとても歩きやすい。もちろんアップダウンは適度にありますが、危険エリアは全くなく、稜線縦走が楽しめます。1つあるとすれば標識は途中いくつかありますが、多少迷いそうになるところですか。特に後半の大マテイ山は間違いやすいです。まず鶴寝山。とにかく新緑がキラキラ奇麗です。一番いい季節なのかもです。陽ざしにあたってさらに黄緑がきらめくので気持ちの良いものです。小鳥も多く、たくさんさえずっています。頂上直下は少し斜度がありますがすぐ鶴寝山の頂上です。ここにはベンチが2つあります。そしてここからは、奈良倉山よりも景色がはっきりする富士山をみることができます(個人的にはこちらの富士山の方がいいなあって思った)。ベンチもあるので休憩には最適です。鶴寝山を後にして先に進むと2つに分岐する場所に着きます。どちらも小菅に続く分岐で合流します。右は「巨樹のみち」、左は「日向のみち」と呼ばれています。行きは「巨樹のみち」で行くことにしました。すごい大きな木の乱立です。新緑の季節なのでとにかく「黄緑」が奇麗で、涼しさを感じます。尾根の右側を通っていくルートですね。巨樹を楽しみながらしばらくすると道の駅小菅に向かう分岐点につきます。そこからほんの少しいくと大マテイ山にいく2つのルートの分岐になります。が!ここには標識がありません。雰囲気的には左にいくルートしかないという感じなので、ほとんどの人が左ルートに行くのではと思います。大マテイ山へこれから向かうのですが、登山計画をしているときにふと思ったことがあります。ルートは2つ大マテイ山にはあるのですが、北側ルートへ行った場合、頂上がない?という感じで地形図は描かれています。と必然的に左ルートを進まざるを得ません。ちょうど大マテイ山の南の山腹をトラバースするルートです。とすると谷道を九十九折に登るのと牛ノ寝へ向かう道の分岐点になります。大マテイ山は九十九折で登ります。今回のコースで唯一急登の場所です。淡々と登ると大マテイ山の山頂になります。辺りを樹林で囲まれていますが、少しだけ富士山が木々の間からみれます。この大マテイ山の頂上でしばし休憩です。休みがてらここで気になっていた北側のルートです。この奥に絶対通ってるはずだと思って、道のない広い頂上を北へ向けて歩いてみました。そしたら、途中からうっすらと踏み跡があり、標識の立つ北側ルートを発見しました。帰りはこの北側ルートで戻ろうと思います。道の駅小菅との分岐点にもどり少し行くとまた2分離しています。「巨樹のみち」と「日向のみち」です。帰りは「日向のみち」で行きます。風の通りはこちらの方があります。それと木々の間から富士山と大菩薩連嶺を見ることができます。それで鶴寝山にまた戻ってきました。ここで富士山を見ながらの昼食にしました。やっぱここは絶景です。「関東の富士見百景」という看板も立っていました。若い男女の集団が登ってきて、山頂はにぎやかになって、みんなで集合写真を撮るところをみながらの昼食でした。とっても楽しそうでよいグループですね。ここから先へ行くときには「お騒がせしました」とちゃんと言ってくれた人がいてとってもよい若者たちだなあって思いました。さて、あとはゆっくり下って松姫峠に戻ります。
このルートは大菩薩まで続く「牛ノ寝通り」です。今日歩いた雰囲気では、牛ノ寝を歩いて見たいと思いました。こんな尾根歩きがずっと大菩薩まで続いているので、せめて榧ノ尾山まで行ってみたいと思いました!
やっと奈良倉山に登頂することができました!それも早朝の誰もいない静かな山行でよい新緑の風景を楽しめました。
(登山DATA)
エリア:中央本線沿線の山 小菅
山名:奈良倉山(ならくらやま)
標高:1,348.9m
岩質:泥岩
ルート:【縦】奈良倉山~鶴寝山~大マティ山(松姫峠)
グレーティング: 体力 2、定数 17、難度 A EK度数 20(比較的楽)
特徴:秀麗富嶽十二景(5番山頂)=選定締め切りギリギリに滑り込む逸材の山、新緑と紅葉が美しい、松姫峠、廃トラック
フォトギャラリー:120枚

松姫峠に4:30に着。ちょうど太陽が昇るときにつきました。

松姫峠では、雁ヶ腹摺山から伸びる稜線の奥に富士山を望めます。これから朝陽があがります。

松姫峠から大月方面に下ることはできません。ここの通行止めです。

雁ヶ腹摺山が赤く色づきました。この尾根は雁ヶ腹摺山のすぐ北から伸びる「楢ノ木尾根」と言われています。右端の一番高い2つの頂き、左が雁ヶ腹摺山の山頂です。右が大樺ノ頭です。そこから尾根が伸び左サイドにある2つの頂きへ達します。右から泣坂ノ頭、左が大峰です。富士山は泣坂ノ頭にかかるように見えます。

富士山も白い頂がうっすらピンクに染まっています。朝早くに着くとこういう絶景を見ることができます!今日は最高の快晴です!

さらに角度を変えると大菩薩連嶺を望めます。雁ヶ腹摺山~黒岳~奥牛ノ雁ヶ腹摺山とつらなっています。朝陽があたってとっても奇麗ですね!

松姫峠。

ここが奈良倉山への登山口。

奈良倉山登山口。

こんな立派な登山道です。道が太いです。まるで車が走っていたようです。

ほどなく行くと林道と左へトラバースしていく道の2つに分かれます。どちらでも奈良倉山へ行けます。

トラバース道に入りましたが踏み跡が少し薄いので、これ行けるのかなあって不安に最初なりますが、徐々にしっかりしてきます。

奈良倉山へ向かう1つ手前にピークがあります。トラバース道はそのピークを左から巻いた道です。また林道は右から巻いています。

ちょうどこれからそのピークを巻くところですが、木々の間から遠く山並みが奇麗に見えています。天気がとってもいいので、これなら景色は期待できます!

北側に来ました。新緑で森がいきいきしています。1290m付近の等高線にそって巻道になっています。

こんなきれいな森がこのトラバース道でずっとみることができます。気持ちのいい散策路って感じですね。

林道と合流です!トラバース道の方が北に張り出して巻くため距離と時間を稼ぎます。のんびりと森林を楽しむには静かでよい巻道だと思います。

林道合流からすぐこの看板があります。ここなんか丘に登る細い道があります。ルートは右の林道です。こうなってるとあの丘の上はどうなってるんだろう?とかどっち?とかいろいろ思いますね。が、またここに戻ってくるので、まずはせっかく早く来ているので、山頂を目指したいと思います。この答えは後程(笑)。

1290m付近のもう「道路」というような林道です。こんな山の中にハイウェイがあるようです。トレランのコースだとうなづけます。

ここが奈良倉山山頂への入口です。左手に標識があり、ここから左の1段上の道を進みます。もちろん右の林道から行って、頂上直下の南斜面を登ることで山頂にいくことができます。がここは入口にはいって山頂を目指したいと思います!

1310m付近。山頂直下なので斜度が増します。が登りやすい登山道なのでゆっくり登りましょう!

1320m付近。この辺りが一番急ですかね。遊びのない直登ですから、ふくらはぎに来ますw。

1340m付近。少し傾斜が緩みました。頂上まであと少し。

1340mを超えて、あれが頂上ですね!

奈良倉山 1,348.9mの山頂です!あれ??奈良倉山は秀麗富嶽十二景ですよね・・。樹林に囲まれて富士山はどこにも見えないです。

奈良倉山、秀麗富嶽十二景の山頂標識です。

そして、二等三角点「佐野峠」がここにあります。実際の佐野峠はもう少し南に位置しています。

ところで、富士山ですが、どこから見ることができるかというと登ってきた登山道のところに松姫峠を指す標識がたっています。そこから左側の開けた場所が見えます。そこが展望所です。

松姫峠を指す標識のところから木々の間に富士山見えてます!

富士山展望所。木が伐採されていて、囲まれた木々の額の中に富士山は描かれていたという感じです。

少しズームアップするとこんなです。手前の峰々の先に優雅な富士山が裾野を開く姿です。秀麗富嶽十二景としては一番小さい富士山?ではないかと思います。というのも大月市の最北端に位置しているので小さめにはなりますね。

さらにズームアップ。いや~やっぱり見事な富士山です。それもまだ6:30です。誰もいなくて独り占めです(笑)。朝が一番奇麗な姿を見せてくれるので、この時間にここにこれてこの景色に逢えて大満足です。

富士山山頂部です。

少し角度を変えて撮影をしてみると、富士山の右側にはいろんな山々があります。まず富士山の右下にある頂上部は三ッ峠山です。そして手前の奇麗な緑の稜線ですが、これは雁ヶ腹摺山から東へ伸びる「楢ノ木尾根」で右の丸い頂が「泣坂ノ頭」左の尖った頂きが「大峰」です。
これが秀麗富嶽十二景第五番山頂「奈良倉山」からの富士山です!

松姫峠へまた戻ろうと思います!

温度計がありました!12℃ですね。すごい寒いということもなく、1枚羽織る程度の気温でした。

奈良倉山を下山です。

林道の合流点に戻りました。またハイウェイの林道です。ここからしばらく平らな道です。

奈良倉山西側の1290m付近は真っ平な平坦の尾根になっています。そこの端までくると高度を下げます。その左側は木々に覆われていますが、木々の間から大菩薩連嶺の稜線がくっきり見えてます。

そして登山道右側のちょっと高い位置に「それ」はありました(笑)。一番見たかったものです。近くに行ってみましょう!

人工物!!!廃トラックです。奈良倉山の林道がハイウェイのように広かったのは昔このトラックがここを走っていたということですよね。

インスタ映えしそうな廃トラック。

奈良倉山1つ手前のピークの分岐です。行きは右のトラバース道から来たので、帰りはハイウェイの林道を進むことにします。

考えることなくのんびりとハイキングって感じです。松姫峠から奈良倉山はお散歩感覚で森林を楽しめるコースです。

木々の間から富士山と雁ヶ腹摺山から伸びる「楢ノ木尾根」が見えています。写真だと木になってしまいますね(笑)

これなら見えますね!

富士山です!

松姫峠に戻ってきました!朝とはまた違った富士山と楢ノ木尾根です。

松姫峠の富士山です。

そして雁ヶ腹摺山・黒岳・牛奥の雁ヶ腹摺山です。

松姫峠7:33。今度は後半戦です。この看板「牛ノ寝大菩薩峠登山口」と書かれています。そうここから牛ノ寝通りというのを通って、大菩薩嶺へ行くことができます。ここからスタートして、鶴寝山とずっと気になっていた大マテイ山の2座を縦走したいと思います。

まずはいきなりこの登りw。松姫峠からすぐピークがあります。その登りです。目の前の森が黄緑の新緑です。ここからこの先はまさに新緑の森です。この新緑を楽しみに歩く登山って感じです。

奇麗な新緑です。少し登りますが、それも気にならないほどの新緑の美しさです。ついつい上を見上げてしまいます。

尾根伝いにずっとあるいてきて、ここから最初の頂き鶴寝山への頂上直下の登りになります。

ここが直登すれば鶴寝山へ、左の巻道で頂上を巻くこともできます。頂上へはこんな感じの登山道が続いて急ではなく登れるので登りやすいです。

もうすぐ頂上です!

鶴寝山1368mの山頂です。山頂には2つですがベンチがあるので、そこに座って富士山をぼーっと眺めるのはとってもいいです。

ここからも奈良倉山同様に富士山の絶景に会えます!

少しズームアップするとこんな感じです。雁ヶ腹摺山からの楢ノ木尾根の奥に富士山をみることが出来ます。松姫峠ではちょうど泣坂ノ頭にかかった富士山でしたが、鶴寝山では泣坂ノ頭よりも右になるので富士山がばっちりの角度です。もしかして奈良倉山の富士山よりもこちらの方が絶景?かもしれません。

もっとズームアップするとこんな感じ。富士山は遠いですが、とても良い形の富士山です。

角度を変えると雁ヶ腹摺山やさらにおくの黒岳も見ることができます。

鶴寝山を後にして少し進んだところ。登山道は平坦なとても歩きやすい道です。

1550m付近で分岐があります。まっすぐと左です。ここで登山道は2つに分かれます。どちらを進んでも小菅に行く分岐にたどりつきます。が、景色が大幅に異なります。まっすぐは「巨樹のみち」です。左は「日向のみち」です。名称からなんとなく想像できますね!今回はまず行きはまっすぐで巨樹のみちを行こうと思います。帰りに日向のみちで戻ろうと思います。

1つピークをこえたところに「巨樹のみち」という標柱が立っていました。じゃあ、行ってみましょう!

いきなりです。まるで踊っているかのような巨樹のお出迎え。ここからはいろんな巨樹の表情を見ながら奥へと進みます。

では巨樹のみちをたのしみましょう!

・・・

・・・

・・・

・・・もう森が美しすぎて言葉はいらないですね!新緑の季節は森が輝くのでこの季節が一番いいかもしれません。もちろん新緑だということは秋は紅葉が見事なので、これは11月頃また紅葉を見に歩いて見たいものです。

小菅への分岐です。右へ行けば小菅、まっすぐ行けば大マティ山です。

小菅の分岐から少し先に進んだここ。地形図上ですとここも分岐です。登山計画をしているときに大マテイ山へ行こうとした場合南側からは登山道が頂上へ行けるように示されていますが、北側ルートだと山頂には行けない?って表記になっています。これが最大の疑問点でした。明らかにルートは北側から進んだ方が楽です。南からは山腹斜面の急登を登らなければなりません。北から攻めて道なきところを進もうかとも思いましたが、まずは地形図通りで行こうと南ルートへと計画。標識もなく普通に歩けば真ん中の木の左を進むことになると思います。

なにも気にせず南ルートに入っていました(笑)。ここで位置を確認したら、南ルートでした。先ほどの分岐の写真は実は帰り北ルートで戻ってきた際に撮影したものでした。もともと今回は南ルートからと思っていたので、このまま進みます。

穏やかな新緑の森が続いています。大マテイ山はほとんど情報もなかったのでどんな登山道なんだろうって思っていましたが、こんな森がずっと続いていてのんびり登山には最適な道です。

気持いいです!

真正面が大マテイ山の方角になります。登山道はここから右に巻道になります。

巻道は山腹の斜度がある部分に作られています。左斜面に注意して先を進みましょう!

ここが大マテイ山の1つ前のピークの最南端の場所です。これから北上します。

左へ斜度のある中腹をトラバースしています。

時折登山道に大きな木がなぎ倒されたまま残っていたりもしてました。おっ!あれが分岐ですね。

ここが大マテイ山への分岐地点です。登山道は左に大ダワへ向かっています。ここからこの谷合に入り、急登を登らなければ大マティ山へ行けません。北側ルートならこういう急登がないのでほんとうは北ルートで行きたいなあって思いましたがなんか頂上にいけないとそれも困るので、ここを登るよりないですね!

まさに九十九折の急登です。今日はここまで穏やかなお散歩登山という感じだったので、少しはこういう急登もないとねということで頑張ります!

急登といっても登山道自体は凸凹もなく平坦で歩きやすいので問題はないです。

とにかく登ります!新緑きれいですね。小鳥のさえずりもMAXで気持ちのいい森です。

傾斜も緩みまもなく頂上っぽくなってきました。

この先が頂上のようです!

大マティ山1409.2mの山頂です。この頂上標識の大マティ山の下に括弧で書かれた部分に不思議な気持ちに・・(山沢入)って書いてあります。最初入沢山?って思ったのですが、ここには・・・

ここには・・・三等三角点「山沢入」があります。山沢入という名前なんですね!ちなみに手前に小菅への分岐点があったと思いますが、そこは「山沢入のヌタ」というそうです。

大マティ山の山頂です。ベンチが1つ。ここに来る人は少ないと思うので、座ってのんびり木々に囲まれるのもよいと思います。おにぎりでも食べるのもよいですね。

大マティ山の山頂は樹林に囲まれていますが、富士山が楢ノ木尾根のかなり上部で見れます。ここまでくると富士山の見える位置は大きく変わりますね!

木々に囲まれてはいますが、けっこう景色見えたりします。雰囲気のあるいい頂上です。来たかったので満足ですね!
それでやっぱり解決したくて、この頂上から北ルートへは行けないのか?けっこう平の広い頂上です。北面は森なんですがこのすぐ下にきっとあると思うのです。それでこの写真をとってさらに少し道なきところを行ってみました・・・・すると少し踏み跡がありました。

と・・・・なんと北ルートです。それも北ルートには大マティ山はこっちの標識も指示がされていて北ルートを進んでも登れることがわかりました!でも分岐点の指示がないので、北ルートに入り込めないかもという問題は残りますね。小菅の分岐のすぐなので、それさえわかれば次回からは北ルートで!って行けますね。帰りは北ルートで戻ります!

この北ルートも森が美しい!というかこの山域は遠くの景色は望めないけど、森を楽しむにはすごいいい場所だと感じました。季節によっても顔が変わると思いますので、その時期の顔を見に来るのもよいかと思います。

こうやって新緑の写真を撮りたくなるほどです。

ちょうど大マティ山とその1つ手前のピークの鞍部です。ここから北ルートは左にトラバースします。

こういったトラバース道が続きます。

ここにも巨樹が立ちます。見事です!

1つ手前のピークも超えました。

この明るい森の右の斜面を超えれば南ルートがあるはずです。北ルートは左に斜面をそって曲がります。この先その尾根に上に突き当たるのですが、間違って尾根を進まないように!道迷いのきっかけになります。実際ちょっと進んでしまいました・・・

この道が正解です!これを下りれば合流できます。おりきると先ほどここが分岐点と示した看板のない分岐につながります。

小菅の分岐(=山沢入のヌタ)から見た登山道です。緩やかな登ります。このすぐ先に・・・

巨樹のみちと日向のみちの分岐があります。帰りは日向のみちで戻ります!(まっすぐ行かず右に入り込みます)

右斜面のトラバース道を進みます。

ほどなくすると明るい森になります。

ひなたっていうのがよくわかります(笑)。

陽ざしの差し込む穏やかな登山道を進みます。

右側には木々の間から大菩薩連嶺の山がなんとなくみれます。が写真にとっても木になってしまうので心の目で想像ください。

しばらくすると・・・「日向のみち」の標柱です。あとでわかったことですが、この標柱みたときに違和感を感じたんです。日向のみちって知らせるためならもっと手前にこれがあってもいいと思いますが、かなり進んだまもなく合流というところにこれがあります。地形図で写真の撮影場所を確認したら、巨樹のみちの標柱と日向のみちの標柱はほぼ同じ場所に設置されています。

進路は南にトラバースしています。

トラバースの先端にきたら、ここからやっと稜線が撮影できました。

トラバースの先端には標識が立ちます。

で、合流します。

鶴寝山への登りに差し掛かりました!

少し登ります。

富士山を見ながら休憩とりたいなあって足早になります(笑)。

頂上稜線になって平になります。もう少し。

鶴寝山に戻りました。

富士山は朝と変わらず雲1つない絶景のままです。

松姫峠へ向けて尾根を進みます。緩やかに下りているので歩きやすいです。

松姫峠に戻りました!
装備・携行品
| シャツ | アンダーウェア | ソフトシェル・ウインドシェル | フリース | ロングパンツ | 靴下 |
| レインウェア | 登山靴 | バックパック | 水筒・テルモス | ヘッドランプ | 予備電池 |
| タオル | 帽子 | グローブ | サングラス | 地図 | コンパス |
| ノート・筆記用具 | 登山計画書(控え) | ナイフ | 健康保険証 | ホイッスル | 医療品 |
| 虫除け | 熊鈴・ベアスプレー | ロールペーパー | 携帯トイレ | 非常食 | 行動食 |
| GPS機器 |