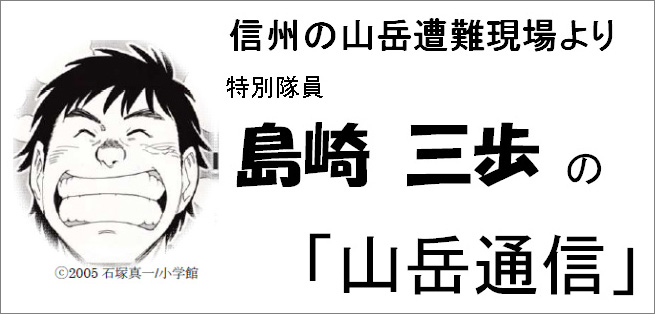日高山脈で起きた国内最大級の雪崩と、感動を呼んだ『雪の遺書』。1965年3月の北海道大学山岳部の雪崩遭難事故。
雪山での重要なリスクの一つである雪崩。1965年3月に起きた「国内最大級の雪崩規模」とされる『北海道大学山岳部の雪崩遭難事故』と、感動を呼んだ『雪の遺書』を資料に、雪崩のメカニズムを読み解き、その教訓を考える。
遅ればせながら、新年あけましておめでとうございます。山岳防災気象予報士の大矢です。旧年中は私の拙いコラム記事をお読みいただきまして大変ありがとうございました。山岳での気象遭難を少しでもなくすことができればと願って書き始めたこのコラム記事ですが、今回でなんと40回目となります。本年もどうぞよろしくお願いいたします。
さて、雪山で警戒すべき重要なリスクの一つとして雪崩があります。直近では2017年3月27日に起きた那須岳雪崩遭難事故(第13回コラム記事)の悲劇が記憶に新しいと思います。過去にも重大な雪崩遭難事故は何度も繰り返されています。今回ご紹介します1965年(昭和40年)3月14日の北海道大学山岳部の雪崩遭難事故もその一つで、国内最大級の雪崩によって起きています。
かなり前の遭難事故ですが、この事例で学ぶべきことは多いと思います。6名のメンバーの中で唯一即死を免れた沢田義一リーダー(享年24)が4日間の生存中に残した『雪の遺書』についてもご紹介いたします。この『雪の遺書』によって、今でも語り継がれる有名な遭難事故となりました。そして過去の調査資料などで不足している詳細な気象状況については、JRA-55(気象庁55年長期再解析データ)によって解析してみました。

北海道大学山岳部の雪崩遭難事故の概要
この遭難事故は『雪の遺書 日高に逝ける北大生の記録』(著者:沢田義一)として、沢田リーダーの生い立ちや遭難事故の詳細がまとめられ、大和書房から出版されています。もう廃版になっているようですが、私は名古屋市の鶴舞中央図書館の書庫に保管されているのを見つけて読んでみました。おそらく、全国の主要な図書館であれば保管されていると思います。概要をまとめると以下のようになります。
1965年3月11日、沢田義一をリーダーとして北海道大学山岳部の6人パーティーは、日高山脈の札内岳(1895m、図1)を源頭とする札内川に、上札内から入山した。支流の十ノ沢を詰めて稜線に登り、カムイエクウチカウシ山(1979m)、神威岳(1756m)、幌尻岳(2052m)などにアタックし、24日に戸蔦別川(とったべつがわ)から八千代に下山する計画であった。
12日は札内川を遡行して、八ノ沢付近に露営。13日は一日中、雪が降り続く中を十ノ沢の出合まで進み、川床から約3m上にあるテラス状の場所に雪洞を掘って露営した。しかし14日の午前2時頃に大規模な雪崩が発生して雪洞で就寝中のパーティーを襲い、沢田リーダーを除く5名は即死(推定)、沢田リーダーは幸運にも口の回りに隙間があったため即死を免れた。 沢田リーダーはナタを使って脱出を試みるが、遂に力尽きて雪洞内で亡くなった。
現地は雪深く雪崩の危険があるため捜索は難航し、何度かに分けて捜索活動が続けられた。そして雪解けが進んできた6月13日に雪面の窪みが見つかり、そこを掘り起こすと沢田リーダーの遺体が現れた。17日には沢田リーダーの遺体の約1m下で、残る5名も就寝中に雪崩が襲った時のまま並んで横たわっている状態で発見された。

沢田リーダーが残した『雪の遺書』
鎮魂のため歌われた北海道大学山岳部の部歌
沢田リーダーの遺体のポケットには、防水のためにポリ袋に入った2枚の地図が見つかりました。地図には「処置・遺書」と書かれ、地図の裏には2000字を超える遺書が書かれていました。そして、この遺書によって沢田リーダーは閉じ込められた雪洞の中で4日間生存していたことが明らかになりました。
雪崩に埋もれた雪洞のわずかな隙間で書かれた遺書は、インクが所々にじんでいて痛々しいです(書籍の巻頭に遺書の一部の写真があります)。ナタで雪を掘って脱出を試みるも地上の明かりが見えず遂に死を覚悟したこと、自分の家族だけでなく、亡くなったメンバーたちとその母親にも詫びる文面などがあり、遺書に書かれた沢田リーダーの思いは強く胸を打つものがあります。
沢田リーダーが残した遺書は『雪の遺書』として全文が当時のテレビや新聞などで報じられ、日本中に大きな感動を呼びました。「札内川園地」内の村営「日高山脈山岳センター」には、『雪の遺書』の全文やパーティーの遺品が展示されていますが、『雪の遺書』の全文は書籍以外にも、例えば、亡くなったメンバーのうち2人の出身校である札幌南高の13期東京同期会ホームページ「雪の遺書 (再掲)」などで読むことができます。
発見された時点ではまだ雪が深く搬出が困難なため、6人の遺体は現地で荼毘(火葬のこと)に付されています。そこでは捜索活動に駆け付けた北海道大学山岳部の部員やOBたちが歌った北海道大学山岳部の部歌「山の四季」が、谷間に悲しく響いたそうです。「山の四季」は有名な歌ですので、お聞きになったことがある方も多いと思います。
『沢を登りていまいつか わらじも足に親しみぬ 三日三晩の籠城も すぎて楽しき思い出よ いざゆこう我が友よ 日高の山に夏の旅に 北の山のカールの中に眠ろうよ』
「山の四季」3番目より
爆風によって樹齢110年の木がなぎ倒された
北海道大学山岳部パーティーを襲った雪崩は「1965年札内川なだれ」と命名され、現地調査をした北海道大学低温科学研究所によって「1965年札内川なだれ調査報告」(以下、北大報告書)としてまとめられています。
北大報告書によると、雪崩の全長は約3km、雪崩によって堆積したデブリは約40万トン、長さ約1km、幅30~100m、平均厚さは約10mで、雪崩の階級としては国内最大級だったとのことです。『雪の遺書 日高に逝ける北大生の記録』によると、雪崩の体積は120万立方メートルで、東京ドームの容積(124万立方メートル)とほぼ同じサイズの巨大な雪崩でした。
図3に示すように、雪崩は札内岳分岐付近の稜線の南東斜面の複数の地点で発生して、分岐点沢に沿って下降していったん合流しています。そして雪崩は札内川出合からは札内川本流を下降して、十ノ沢出合付近に設営した雪洞(図3の右下)を襲い、更に約200m下降してようやく雪崩は止まっています。分岐点沢での倒木や破壊の状況から、雪崩の主力は斜面の東側半分(図3の上の方)から落下してきたと推定されています。

雪崩は最初の経路となった分岐点沢から札内川を下降して雪洞を襲った。
雪崩が起こした風(なだれ風)の衝撃で、標高差60m以上の高さにある木までなぎ倒されています(図3中央下から右下の風倒地帯)。なだれ風は分岐点沢だけでなく、雪洞の北側で札内川本流の木もなぎ倒しました。
北大報告書によると、“なだれ風で当時の雪面附近から切断された樹幹は最大直径70cm,樹齢110年に及ぶものがあった” とのことですので、少なくとも100年間はこの木を倒すほどの大規模な雪崩は発生していなかった・・・、つまり100年に一度の大規模な雪崩であったということができると思います(ちなみに春に多い全層雪崩ではなく表層雪崩でした)。
襲った雪崩は「泡雪崩」、最も破壊力がある恐るべき雪崩
このような爆風を伴う雪崩は、泡(ほう)雪崩と呼ばれています。雪崩の中では最も破壊力がある恐るべき雪崩です。1938年12月27日に起きた泡雪崩は有名で、黒部川第三発電所建設のための鉄筋コンクリートの工事宿舎を600m吹き飛ばして84名の死者が出る大惨事になりました。
泡雪崩は多雪地帯で気温が低く、大量の雪が降っている時、またはその直後の積雪が安定しない時に発生しやすいといわれています。そのため泡雪崩は、新潟県や富山県の豪雪地帯を中心に「ホウ」「ホウラ」「アワ」「アイ」などと呼ばれ恐れられてきました(出典:Wikipedia)。直近では、平成18年豪雪が起きた2006年1月に北アルプスの岳沢ヒュッテを全壊させた雪崩も、その被害状況から泡雪崩と推定されています。
遭難事故が起きた日高山脈の積雪期は雪が深く、谷幅が狭く逃げ場がない札内川上流部では過去に何度も雪崩遭難事故が起きています(TOUCH55さんのブログ【中札内村】札内川上流地域殉難者慰霊碑を参照)。
日高山脈は襟裳岬に向かって海に向かって突き出ているため、両側の海からの湿った空気の影響を受けやすいことが、降雪量の多い原因になっていると思われます。このような地理的条件にある日高山脈では、条件さえ揃えば泡雪崩が発生しても何ら不思議はないと思われます。北大報告書には泡雪崩とは書かれていませんが、泡雪崩であった可能性は高そうです。
恐るべき雪崩の発端は巨大雪庇の崩壊
3/26~4/5の間で行われた第一次捜索隊による観察では、“稜線沿いに張出し20mを越す雪庇と,その崩落の跡が見られ, 叉,なだれ斜面を横切っているクラックが見られた。” と報告されています。このことから北大報告書では、雪崩のきっかけは、“稜線の東側(札内川側)に張り出した雪庇(図3参照)の崩落であった可能性が強い。”としています。
このような巨大な雪庇は、風下側に庇(ひさし)状に張り出したオーバーハングを持った通常の雪庇とは違って、庇の部分は小さく風下側は絶壁に近い形状になっています(図4参照)。いわば、稜線の風下側に巨大な吹き溜まりがへばり付いているようなものです。2000年(平成12年)3月5日に大日岳で行われた登山研修所主催の「大学山岳部リーダー冬山研修会」で、巨大な雪庇が崩落し、2名の研修生が死亡した時も雪庇はこのような形状をしていました(出典:文部科学省 大日岳遭難事故の概要)。

晴天の後の南岸低気圧で大量の雪が積もった
まず、沢田パーティーの行動記録と近くで行動していた北海道大学山スキー部の行動記録、及びJRA-55によって再現した地上天気図から気象状況を振り返ってみました。12日はオホーツク海と日本海の低気圧に挟まれて気圧の尾根になったため、現地の札内川では快晴の天気に恵まれています(図略)。しかし一転して13日は南岸低気圧による悪天のため、正午から豪雪となって14日朝まで降り続いています(図5)。

JRA-55によって1965年3月12日9時から3月14日9時までの札内岳分岐点付近の1時間降水量と積算降水量の推移を解析した結果を図6に示します。降水量を10倍すると降雪量の目安になりますので、降雪量は単位のmmをcmに読み替えてください。13日の6時頃から降雪が強まって、夜までに積算降雪量は110cmに達したことが分かります。この南岸低気圧による急激な降雪量の増加によって、大量の雪が積もったことが雪崩の原因の一つでした。

2月に降った雪の層に弱層が形成され、
前日に大量の雪が積もったことが真因
北大報告書では、“前半,東風により国境稜線の西側に発達していた雪庇は,風向の変化(東風→西風)に従って消失(埋没)し,後半には稜線東側に巨大な雪庇が新しく成長した” との記載があります。しかしわずか1日で20mを超える巨大な雪庇が稜線の東側に成長するとは思えませんので、それ以前から既に稜線の東側には大きな雪庇が存在したのではないかと推定しています。
JRA-55によって1965年2月1日9時から3月14日9時までの札内岳分岐点付近の1時間降水量と積算降水量の推移を解析した結果を図7に示します。図6と同じく降雪量は単位をmmからcmに読み替えてください。

2月14日と21日に積算降雪量が1mを超える大量の雪が降ったことが分かります。そして、いずれも日高山脈に大雪を降らせた低気圧の通過後は強い冬型気圧配置になっており、強い西風が吹いていました。そのため稜線付近に大量に積もった雪が東に移動して、稜線の東側に巨大な雪庇を形成したのではないかと推定しています。そして21日の低気圧が通過する前の20日は移動性高気圧によって天気が回復しているため、2つの低気圧による雪の層の間に弱層が形成された可能性が高いと思われます。
弱層は雪庇の内部だけでなく、雪崩の経路となった稜線の南東側斜面でも形成されたはずです。3月13日の南岸低気圧による大量降雪が、弱層を内蔵した巨大な雪庇の崩落を引き起こし、それが同じく弱層をかかえた南東側斜面での巨大な雪崩につながったのではないでしょうか。2月は冬型気圧配置になることが多く、風は西風が主体であるため、風下側になる南東側斜面では吹き溜まりとなって稜線よりも多くの雪が積もっていたと思います。
北海道大学山岳部の雪崩遭難事故の教訓
全長3kmのうちのあと200m手前で雪崩が止まっていたら、恐らくメンバーの多くは助かっていたと思います。それほど生と死は紙一重でした。雪洞の設置位置も川床から3m上のテラス(近くを通過した北海道大学山スキー部の証言による)であり、札内川が上流に向かって右にカーブする内側でしたので、適切であったと思います。
雪洞を設置した当時の現地は雪が深く谷を埋めていましたが、無雪期ならば川床から10~15mぐらいあります。 もし、札内川のカーブの外側(十ノ沢側)に雪洞を設置していたら、一般に流体の速度はカーブの外側の方が速いため、爆風で倒壊した木々と同じように雪洞はパーティー6名とともに跡形もなく吹き飛んだか押しつぶされていたと思われます。そしてもう少し雪崩の規模が小さかったら、分岐点沢から下降してきた雪崩は、札内川との出合のカーブで減速して雪洞まで達しなかったはずです。100年に一度の規模の巨大な雪崩が、6名の尊い命を奪ってしまいました。
遭難事故の舞台となった日高山脈は急峻で整備された登山道はなく、長い間、日高山脈は未踏の地でした。例えば沢田パーティーが最初に目指したカムイエクウチカウシ山は峻険な山容であるため、アイヌ語で「熊(神)の転げ落ちる山」という意味の名前が付けられています。この遭難事故の当時も、日高山脈には登攀困難な未知の山というロマンが残っていたようです。
そして当然ながら、訓練を積んで技術を持ったパーティーしか入山が許されない山でした。死を前にして、あれほどの遺書を残した沢田リーダーが率いたパーティーは、間違いなくその資格があったと思います。
当時の天気予報はそれほど精度が高くなかったため、南岸低気圧による13日の日高山脈での大量降雪は予想できなかったと思われます。しかも、麓にある気象庁の広尾(位置は図3参照)の観測所では13日の最高気温は-1.2℃ですが、わずか5cmの降雪(積雪深は79cm)でした。これは日高山脈での13日の豪雪には、山岳地形の影響があったことを意味しています。
冬型気圧配置の時に、日本海から来た雪雲が山に当たって、山の斜面による強制上昇によって雪雲が発達して日本海側の山岳で大雪になるのと同じ原理です。南岸低気圧が通過する時には、海からの風が直接当たる山域では平地よりも大雪になる可能性を想定しておくことが必要と思います。これが、この遭難事故が残した貴重な教訓の一つです。
現在でも南岸低気圧による雪の予想は難しいですが、1965年の遭難事故当時よりも遥かに予報精度は向上しています。また過去の雪の状況も、気象庁の過去の気象データ検索で知ることができ、あらかじめ弱層の存在もある程度は推定することができます。平地の天気予報はそのまま使えませんが、山岳地形の影響や弱層の存在を考慮して、最悪のシナリオを想定して常に安全サイドで行動するように心掛ければ、雪崩事故に遭う確率は確実に減ります。このような今回の教訓を生かすことが、亡くなった沢田リーダーたち6名への何よりの供養になると思います。合掌・・・。
プロフィール

大矢康裕
気象予報士No.6329、株式会社デンソーで山岳部、日本気象予報士会東海支部に所属し、山岳防災活動を実施している。
日本気象予報士会CPD認定第1号。1988年と2008年の二度にわたりキリマンジャロに登頂。キリマンジャロ頂上付近の氷河縮小を目の当たりにして、長期予報や気候変動にも関心を持つに至る。
2021年9月までの2年間、岐阜大学大学院工学研究科の研究生。その後も岐阜大学の吉野純教授と共同で、台風や山岳気象の研究も行っている。
2017年には日本気象予報士会の石井賞、2021年には木村賞を受賞。2022年6月と2023年7月にNHKラジオ第一の「石丸謙二郎の山カフェ」にゲスト出演。
著書に『山岳気象遭難の真実 過去と未来を繋いで遭難事故をなくす』(山と溪谷社)
山岳気象遭難の真実~過去と未来を繋いで遭難事故をなくす~
登山と天気は切っても切れない関係だ。気象遭難を避けるためには、天気についてある程度の知識と理解は持ちたいもの。 ふだんから気象情報と山の天気について情報発信し続けている“山岳防災気象予報士”の大矢康裕氏が、山の天気のイロハをさまざまな角度から説明。 過去の遭難事故の貴重な教訓を掘り起こし、将来の気候変動によるリスクも踏まえて遭難事故を解説。