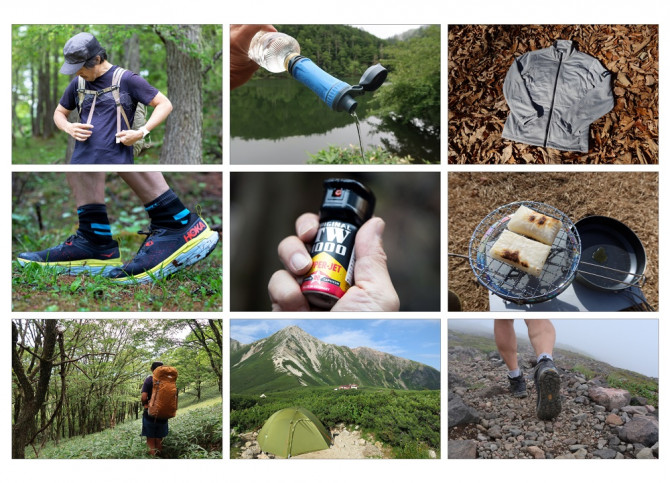雪山登山入門・ステップアップは八ヶ岳がおすすめ! 初級から上級まで7コース
八ヶ岳はさまざまなレベルのルートがあり、晴天率がよいことからも、雪山登山に人気の山域だ。そんな八ヶ岳のレベル別おすすめルートを紹介する。
目次
【初級】高見石・白駒池 凍結した白駒池の上を歩く
高見石~白駒池周辺は、北八ヶ岳の冬の美しさを凝縮したような場所で、雪山の魅力を存分に楽しめる場所だ。氷結して雪原へと変わる白駒池、なだらかな雪の斜面、雪を被って樹氷と化した樹木と、雪山の美しさをひと通り楽しめる。

コース途中には通年営業の山小屋もあり安心だ。高見石小屋および白駒荘、青苔荘、麦草ヒュッテと多くの山小屋が営業している。(営業日時には注意)
登山口となる渋ノ湯からの登山道には登山者も多く、トレースも期待できる。初心者が初めて雪山で過ごす場所には安心できる山域だ。
関連リンク
行程・コース
最適日数:1泊2日 5時間57分
総歩行距離:10,859m /上り標高: 798m 下り標高: 798m
行程:【1日目】
渋ノ湯(08:00)・・・賽ノ河原地蔵(09:30)・・・高見石(10:10)
【2日目】
高見石(07:00)・・・白駒荘(07:25)・・・白駒池北岸(07:35)・・・白駒池分岐(07:40)・・・麦草峠(08:12)・・・丸山(09:02)・・・高見石(09:17)・・・賽ノ河原地蔵(09:47)・・・渋ノ湯(10:47)
渋ノ湯(08:00)・・・賽ノ河原地蔵(09:30)・・・高見石(10:10)
【2日目】
高見石(07:00)・・・白駒荘(07:25)・・・白駒池北岸(07:35)・・・白駒池分岐(07:40)・・・麦草峠(08:12)・・・丸山(09:02)・・・高見石(09:17)・・・賽ノ河原地蔵(09:47)・・・渋ノ湯(10:47)
関連する登山記録
目次
この記事に登場する山


今がいい山、棚からひとつかみ
山はいつ訪れてもいいものですが、できるなら「旬」な時期に訪れたいもの。山の魅力を知り尽くした案内人が、今おすすめな山を本棚から探してお見せします。