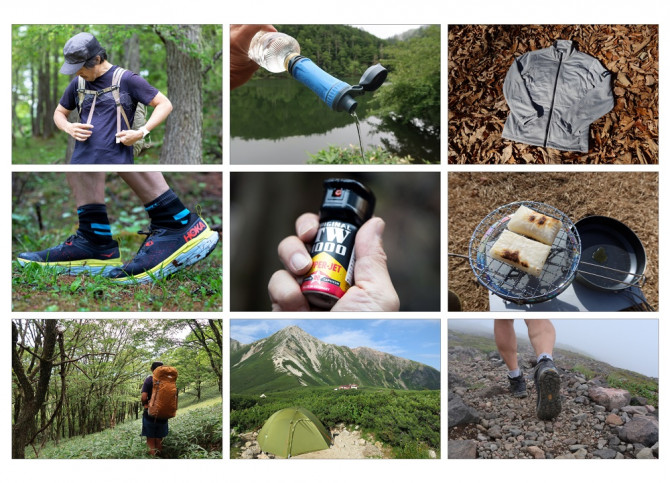クライミング事故の責任は誰にある? 登山の娯楽性と危険性に切り込むノンフィクション【前編】
この事故が起きたとき、キャリントンは、エクザムのほかの生徒と同様、シュイナード・イクイップメント社製のカルプ・アルパインハーネスを身につけていた。クライミング用のハーネスとしてはスタンダードな、それまでとくに問題があるとはされていなかったものだ。キャリントンが落ちた直後、ブリッドウェルは穴のなかで呆然としている生徒たちと合流するために、ルートの上からラペリングで降りていった。すると岩肌からくぼみのなかに視線を移したとき、キャリントンのハーネスがまだロープにぶら下がったままなのを見つけた。そして穴のなかに引き込んで一瞥すると、くそっ、と言って投げ捨てた。ハーネス自体は無傷だったが、キャリントンの腰に固定されているはずのストラップが、金属製のバックルから完全に抜けていたのだ。二度目に滑ったとき、彼がなんのひっかかりもなく、いきなり落ちてしまったのはこのせいだった。ただ、このハーネスは、本来はバックルが外れたとしても機能するようにできているはずだったので、とりわけショックは大きかった。もしちゃんと装着していれば、バックルではなく結びつけられたロープ自体が、ベルトの両端をしっかりと保持する役割をする。つまり、ストラップをバックルに通し忘れたとしても、ハーネスが体を支えてくれるはずだったのだ。
なぜキャリントンは正しくハーネスをつけていなかったのか?
この謎はこのあと、ブリッドウェルを苦しめ、この事件を何カ月にもわたって調査した、アメリカ合衆国国立公園局のレンジャーやエクザム・マウンテンガイドサービスのガイド、シュイナード・イクイップメントの社員、弁護士、そして保険会社の損害査定人たちを悩ませることになる。ただ、穴の入り口にぶら下がっていたハーネスを一目見ただけで、ブリッドウェルはこのクライミングのあいだ見逃していたある事実に気づいた。はじめる前にあれほど注意したにもかかわらず、キャリントンは正しい結び方をしていなかった――ロープをハーネスのタイインループに直接通すというメーカーの指定の方法ではなく、ウエストストラップに留めたロッキングカラビナに結びつけていたのだ。たしかにこの方が楽だし簡単だが、これではハーネスの安全性はカラビナのバックルにすべてかかってくることになる。死亡事故が起きたことによるショックが一段落し、責任の所在の追及が本格的にはじまると、キャリントンが〝いつ〞そして〝なぜ〞このような危険な方法でハーネスにロープを取り付けたのか、多くの人がその答えを知りたがるようになった。
想像がつくかもしれないが、そうした人間のなかには弁護士も少なからず含まれていた。1988年8月22日、事故からちょうど2年後、出訴期限が切れる1日前に、エドワード・キャリントンの勤務先であったヒューストンのフィッシャー・ギャラガー・ペリン&ルイス法律事務所が、未亡人であるローザ・キャリントンに代わって、ブリッドウェルとエクザム・マウンテンガイドサービスを、そしてさらにシュイナード・イクイップメント社を訴えたのだった。
だが、ハーネスが正しく使われていなかったのは明らかだったため、シュイナード・イクイップメントに対する訴訟は、無理筋であると思われた。また、エクザム・マウンテンガイドサービスは北米でもっとも古く、おそらくはもっとも尊敬を集めている登山ガイド会社であり、年間で1日分の講習を3000回近くおこなっているにもかかわらず、55年間の歴史のなかでたった2人の死亡者しか出していない(しかもこの事故が起きるまで、1964年以降ではゼロだった)。これはまさに驚くべき記録であり、本訴訟においても同社の有利に働くだろう。もし原告の弁護団の〝餌食〞になる者がいるとすれば、ジム・ブリッドウェルが最有力候補であると思われた。
ただ、アメリカのクライミングコミュニティのなかでは、ブリッドウェルはスケープゴートにされるほど悪いことはしていないという意見が多かった。「ガイドが付いているからといって、クライミング中に頭のスイッチをオフにしていいというわけではない」と匿名希望のあるベテラン登山ガイドは言う。「結局のところガイドにできるのは、客が無茶するのを止めることぐらいなんだから」
(じつは私自身も、1967年にティトン山脈にガイド付きで登ったときに、無茶をしたせいでキャリントンと同じような事故を起こしかけたことがある。当時13歳で、エクザム・マウンテンガイドサービスの中級ロッククライミングクラスを2日前に修了したばかりだった私は、グレッグ・ロウというガイドに連れられてグランドティトンを登っていた。事前に丁寧な指導を受けていたにもかかわらず、この朝に限って私は腰回りのもやい結びを失敗し、山頂に向かう難所の途中で結び目がほどけてしまったのだ。滑落することなくなんとか自力でビレイポイントまで降りてロープを回収し、ロウからきつく叱られるだけで済んだが、ロープをぞんざいに扱ったせいで、一歩間違えれば死んでいるところだった)
だが、ローザ・キャリントン側のフィッシャー・ギャラガー・ペリン&ルイス法律事務所の弁護士たちは、キャリントンがロープのつけ方を間違えたのが事実だとしても、ブリッドウェルにはそれを指摘して直させるべきだったと主張した。前日にエクザム・マウンテンガイドサービスの初級クラスでロッククライミングの技術を習ったばかりの初心者であるキャリントンに、つねにロープを正しく装着させることこそ、プロのガイドとしてブリッドウェルに科せられた最大の義務だったはずだと原告団は訴えたのだ。事実、エクザム・マウンテンガイドサービスのマニュアルには、「ガイドはすべての結び目を確認すること」と繰り返し明記されている。だが、ブリッドウェルは、あの死亡事故につながった登攀の前にキャリントンがしっかりとハーネスを装着し、ロープもちゃんと結ばれているのを確認したと、最初から一貫して主張している。
ブリッドウェルの弁護団は当初、登攀のどこかの時点で――おそらくは最初のピッチのあと、ビレイポイントの上で――ブリッドウェルが気づかないうちにキャリントンがおそらく小便をするためにロープをほどいたのだろうと主張した。それから急いで、カラビナを通すという手軽だが間違った方法でロープをハーネスに結びつけたのだろう、と(キャリントンの仲間の一人が、彼はそのやり方を1984年にガイド付きでレーニア山に登ったときに習ったのではないかと推測している)。これはいかにもありそうなシナリオだったが、同行者の一人がこの「ホール・イン・ザ・ウォール」でのクライミングの直前にキャリントンがトイレに行っていたと証言したことで説得力を失った。さすがにその数分後にまたもよおすというのはありそうもないし、実際、彼がクライミング中に小便をしている姿を見た者は誰もいなかった。
ただ、キャリントンがいつ、なんのために結び方を変えたのかはさておき、ハーネスのバックルさえちゃんと締めておけば、この間に合わせのカラビナ式のやり方でもなんとかなったのは事実だ(実際、状況次第では、十分に注意を払った上でという条件付きながら、多くのクライマーがとくに命を危険にさらすことなくこの方法を用いている)。バックルがちゃんと留まっていなかったことも、正式なやり方でロープを結んでいなかったことも、それだけでは死につながるものではない。だがこの2つが組み合わさったことが、キャリントンの運命を決めた。
(続)
※本記事は『WILDERNESS AND RISK 荒ぶる自然と人間をめぐる10のエピソード』(山と溪谷社)を一部掲載したものです。
『WILDERNESS AND RISK 荒ぶる自然と人間をめぐる10のエピソード』
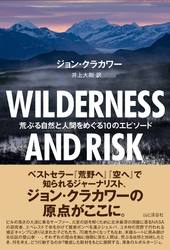
『空へ――「悪夢のエヴェレスト」1996年5月10日 』や『荒野へ』の著作で知られる、アメリカの人気ジャーナリスト、ジョン・クラカワーの、自然と人をめぐる10のエピソードを収録したエッセイ集。
著:ジョン・クラカワー
訳:井上大剛
価格:1760円(税込)
【著者略歴】
ジョン・クラカワー
1954年、アメリカ・マサチューセッツ州生まれ。ノンフィクションライター・ジャーナリスト。アメリカの代表的アウトドア誌『アウトサイド』での執筆活動で知られ、代表作に全米ベストセラー『荒野へ』(1996年)、『空へ−悪夢のエヴェレスト-』(1997年)、『信仰が人を殺すとき』(2003年)などがある。アラスカのデビルズ・サム単独登攀などの記録をもつクライマーでもある。
WILDERNESS AND RISK 荒ぶる自然と人間をめぐる10のエピソード
ベストセラー『荒野へ』(1996年)、『空へ−悪夢のエヴェレスト-』(1997年)で知られるジャーナリスト、ジョン・クラカワーの初期エッセイをまとめた『WILDERNESS AND RISK 荒ぶる自然と人間をめぐる10のエピソード』が発売された。 ビルの高さの大波に乗るサーファー、北米最深の洞窟に潜るNASAの研究者、 70歳ちかくなってもなお、未踏ルートに挑み続ける伝説の登山家・・・。 さまざまな形で自然と向き合う人間模様を描き出す10編の物語から、 1986年に起こったクライミング事故を通して、訴訟社会アメリカの姿を 浮き彫りにするストーリーを、本書から一部抜粋して紹介しよう。
こちらの連載もおすすめ
編集部おすすめ記事

- 道具・装備
- はじめての登山装備
【初心者向け】チェーンスパイクの基礎知識。軽アイゼンとの違いは? 雪山にはどこまで使える?

- 道具・装備
「ただのインナーとは違う」圧倒的な温かさと品質! 冬の低山・雪山で大活躍の最強ベースレイヤー13選

- コースガイド
- 下山メシのよろこび
丹沢・シダンゴ山でのんびり低山歩き。昭和レトロな食堂で「ザクッ、じゅわー」な定食を味わう

- コースガイド
- 読者レポート
初冬の高尾山を独り占め。のんびり低山ハイクを楽しむ

- その他
山仲間にグルメを贈ろう! 2025年のおすすめプレゼント&ギフト5選

- その他