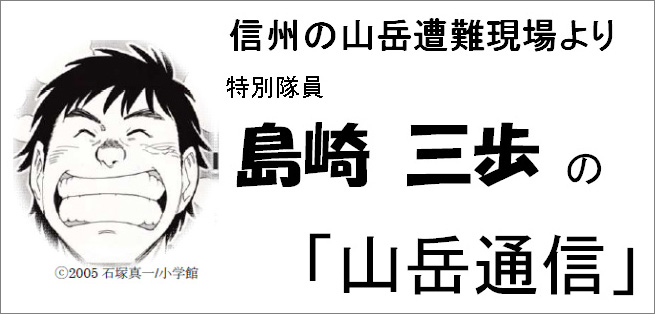日帰り登山で楽しめる! 5月におすすめの花の山 関西編
5月。春から夏に移り変わるこの季節、山ではさまざまな種類の花が咲き誇ります。この季節にこそ登りたい4ルートを紹介します。
5月、花山行のススメ

 推薦人:梶山正
推薦人:梶山正
1959年生まれ。カメラマン。20代でナンガ・パルバット、30代で厳冬期黒部横断、40代でペルー・アンデスなど、国内外で困難な登山を実践。96年に京都大原の山里に引っ越し、関西の山を登りながら撮影を続ける。著書に『ポケット図鑑 日本アルプスの高山植物』(家の光協会刊)など。
寒い冬が去り、春を迎えると、関西の山ではさまざまな花が咲き始める。まずスプリング・エフェメラルやアセビやコブシの花などだ。5月になるとシャクナゲやアカヤシオ、ヤマツツジなどツツジ科の花が多い。群生地と花期を調べて山へ向かえば、花を見逃すことはまずないだろう。
樹木の花ではなく、ニリンソウやクリンソウなど群生する山野草は見つけやすいが、単独でポツンと咲く小さな花を見つけるのは難しい。現場で花の写真を撮っておき、家で図鑑やネットで調べて名前がわかるとうれしいものだ。そんな山行を繰り返すうちに、植物だけでなく山や自然に対する見方も広がっていくはずだ。また、同じ山でも時期をずらして通ううちに、新たな発見もあるだろう。
日本海側の山地に広く分布する、オオバキスミレ南限の山
赤坂山(あかさかやま)
福井県・滋賀県/821m
マキノ高原温泉さらさバス停〜粟柄越(あわがらごえ)〜赤坂山(往復) 日帰り/5時間5分

野坂(のさか)山地の赤坂山は滋賀・福井県境に位置し、高島トレイルの一角を担う。琵琶湖の西北端にあるので、山頂からは琵琶湖の展望だけでなく若狭(わかさ)湾や伊吹(いぶき)山、金糞(かなくそ)岳など見渡すことができる。赤坂山は植林されずに多くの自然林が残されているため、さまざまな山野草の花を楽しめる。オオバキスミレはその代表例だ。雪が多い日本海側に生息し、北海道から北陸まで広く分布するが、この赤坂山が南限とされている。
登山コースは、スキーやキャンプなどアウトドア行楽地であるマキノ高原から往復するのが一般的だ。山頂近くの峠を越える粟柄越は、若狭と近江を結ぶ歴史深い古道であり、古い石畳や地蔵様なども残されている。


MAP

山で見られる花
4月から5月はオオバキスミレ、シハイスミレ、イカリソウ、カタクリ、コタチツボスミレ、キンキマメザクラ、サラサドウダンツツジ、ウスギヨウラク、ツクバネウツギなど。ここではイワウチワにそっくりなトクワカソウが林床に群生する。6月になるとキンコウカ、コアジサイ、ササユリなどが見られる。
アクセスと山麓情報
公共交通機関はJR湖西(こせい)線マキノ駅から湖国バス”マキノ高原線”で「マキノ高原温泉さらさ」下車(220円)。マイカーの人はマキノ高原に入ってすぐの登山者用駐車場(無料)を利用できる。山麓の日帰り温泉は マキノ高原温泉さらさとマキノ白谷温泉八王子荘がある。
明るい岩稜に、鮮やかな色を添えるアカヤシオ
仙ヶ岳(せんがたけ)
滋賀県/961m
池山(いけやま)西バス停〜白糸の滝駐車場〜南尾根〜仙ヶ岳〜白谷〜白糸の滝駐車場〜池山西バス停 日帰り/6時間55分

鈴鹿(すずか)山脈南部の仙ヶ岳は東西2つの峰からなる。西峰が本峰で、東峰には仙の石と呼ばれる奇岩がある。東峰から延びるP1からP5までの南尾根は岩稜帯が続く。5月になると、そこはアカヤシオの花が鮮やかな色を添えて、登山者の目を楽しませてくれる。アカヤシオの5つの花びらは丸く優しげな雰囲気だ。
登山コースは池山バス停を起点として周回する。マイカーだと白糸の滝駐車場まで行ける。営林署小屋跡よりイタハシ谷を経て不動明王のコルに登り、岩に彫られた不動明王と出会う。コルから南尾根に出て、アカヤシオを見ながら岩稜帯をつなぐ。仙の石がある東峰から仙ヶ岳山頂に立ったあとは、白谷を下ろう。御所谷出合を過ぎると、沢沿いにハシゴや鎖場があり、気を抜けない。営林署小屋跡より先は往路を戻る。


MAP

山で見られる花
5月はアカヤシオ、ミツバツツジ、フモトスミレ、タチキランソウ、ニシキゴロモ、イワカガミ、ガクウツギ、タニウツギ、ベニドウダン、サルトリイバラなど。6月に入るとシロヤシオ、アブラツツジ、ハクサンボウフウ、ヤマニガナ、ハハコグサ、コアジサイ、オオナルコユリなどが見られる。
アクセスと山麓情報
白糸の滝駐車場(約5台無料)より先の林道は、落石や倒木などあり、車は通行できない。山麓の美しい渓谷の景勝地である石水渓(せきすいけい)では、春から秋まで石水渓キャンプ場が利用できる。近くの日帰り温泉は鈴鹿さつき温泉や鈴鹿天然温泉 花しょうぶなどがある。
静かな峠道を越え、クリンソウの花に癒やされる
雲取山(くもとりやま)
京都府/911m
花脊(はなせ)峠バス停〜旧花脊峠〜寺山〜雲取(くもとり)峠〜雲取山〜芹生(せりょう)〜旧花脊峠〜峠下バス停 日帰り/7時間

京都北山の雲取山は、かつて山と溪谷社から刊行された『関西百名山』に選ばれてはいるが、目立つ山ではない。ほぼ同じ高さの尾根が山の四方を取り囲む。山腹にはいくつもの小さな谷が刻まれており、地形が複雑である。ひとつの山行で静かな尾根歩きと、沢歩きのどちらも楽しめるのが魅力と言えるだろう。
まず花脊峠バス停から天狗杉を経て旧花脊峠へ向かう。明治後期に車道ができるまで使われた旧花脊峠には、杉の老木と地蔵堂がたたずむ。北へ延びる雑木林の尾根道をたどり、雲取峠を経て雲取山に立つ。木々に囲まれた山頂からは展望が利かない。二ノ谷から二ノ谷出合へ下ると、緩やかな沢沿いの道となる。クリンソウの花を見つつ、芹生の村から芹生谷沿いの林道を登る。京見(きょうみ)坂を経て、旧花脊峠から峠下バス停へ下る。


MAP

山で見られる花
尾根筋は杉植林が少なく自然林が多い。5月はフジ、ヤマツツジ、カマツカの花などが見られる。灰野(はいの)川沿いの湿気が多い谷筋には、クリンソウの群落がある。林道沿いではサギゴケやタニウツギ、種々のウツボグサの仲間などが咲く。また雲取峠にはリョウブが群生しており、7月になると白い花が咲き乱れる。
アクセスと山麓情報
公共交通機関は、出町柳(でまちやなぎ)駅前発の広河原(ひろがわら)行き京都バスのみ。運行数は平日2本、土日祭日は3本と少ない。マイカー利用の場合、峠下付近は道が狭くて駐車スペースはない。山麓の鞍馬(くらま)は古刹鞍馬寺がある小さな観光地。飲食店はあるがコンビニなどはない。鞍馬より先では行動食を買える店がない。
ツクシシャクナゲが群生するシャクナゲ坂が魅力
大台ヶ原山(日出ヶ岳・おおだいがはらやま)
奈良県・三重県/1695m
大台ヶ原ビジターセンター~シオカラ谷吊橋~大蛇嵓(だいじゃぐら)展望台~尾鷲辻(おわしつじ)~日出(ひで)ヶ岳~大台山上駐車場 日帰り/3時間40分

紀伊半島の奈良と三重県境にある大台ヶ原山とは、最高点にある一等三角点の基準点名である。一般に日出ヶ岳と呼ばれる最高点は、三重県の最高峰であり日本百名山のひとつでもある。5月下旬になるとシオカラ谷吊橋から、牛石(うしいし)ヶ原と大蛇嵓分岐点を繋ぐシャクナゲ坂では、たくさんのツクシシャクナゲの赤い花が咲き乱れる。紹介コースは東大台エリアにあり、西大台エリアのような入山申請をする必要はない。急なシャクナゲ坂は、登りに使う方がシャクナゲをじっくり楽しめるだろう。
まず駐車場からシオカラ谷吊橋へ下る。シャクナゲ坂を登って切れた岩の突端にある大蛇嵓展望台へ登り、東大台周回路を反時計回りに進む。開けた笹原の正木(まさき)峠を経て、日出ヶ岳山頂に登って駐車場に戻る。


MAP

山で見られる花
5月上旬はトサノミツバツツジで、下旬からツクシシャクナゲ。6月に入るとアケボノツツジ、ヤマツツジ。6月に入るとシロヤシオ、ベニドウダン、シロヤシオ、コアブラツツジなどツツジ科の花が咲く。7月に入るとヤマアジサイ、コアジサイ、ノリウツギ、 ガクウツギなどアジサイ属の花が見られる。
アクセスと山麓情報
大台山上駐車場(無料)は約200台駐車可能。大台ヶ原ビジターセンターでは、大台ヶ原の自然や登山情報が得られる。駐車場に隣接する売店では行動食や土産品など購入でき、食堂も利用できる。また、大迫ダム近くの入之波(しおのは)温泉山鳩湯(やまばとゆ) では日帰り入浴を利用できる。
山を歩く、花を楽しむ
全国で人気の花の山、関東周辺「花の百名山」のコースガイドや、花に関するコラムを掲載。
こちらの連載もおすすめ
編集部おすすめ記事

- 道具・装備
- はじめての登山装備
【初心者向け】チェーンスパイクの基礎知識。軽アイゼンとの違いは? 雪山にはどこまで使える?

- 道具・装備
「ただのインナーとは違う」圧倒的な温かさと品質! 冬の低山・雪山で大活躍の最強ベースレイヤー13選

- コースガイド
- 下山メシのよろこび
丹沢・シダンゴ山でのんびり低山歩き。昭和レトロな食堂で「ザクッ、じゅわー」な定食を味わう

- コースガイド
- 読者レポート
初冬の高尾山を独り占め。のんびり低山ハイクを楽しむ

- その他
山仲間にグルメを贈ろう! 2025年のおすすめプレゼント&ギフト5選

- その他