雪山遭難が続発した2022〜23年の冬を振り返る
2022〜23年の冬山シーズンは山岳遭難が相次ぎ、発生状況はコロナ禍前に戻ってしまった。雪山登山での事故はもちろん、バックカントリースキーや低山ハイキングの遭難も目立った。
文・写真=野村 仁

事故が多い北アルプス八方尾根
山々も冬の装いを解き始め、気持ちよく歩ける季節となってきました。春本番になる前に、この冬の遭難状況をふり返ってみましょう。今期の特徴は、①発生数が多い、②バックカントリー遭難が多い、③雪崩と滑落による死亡事例が多い、④発生場所が全国各地に分散している、という点だと思います。
全体的状況
マスコミ報道やインターネットの情報を収集して遭難状況を確認しています。私が集めた事例数は、12月36件、1月57件、2月67件、合計160件でした。ここ数年の状況と比較すると、かなり多かったといえます。コロナ禍の影響があったと考えられる2020~22年は90~110件、コロナの影響が出る直前の2019年は約150件でした。今シーズンはコロナの影響による登山自粛ムードが薄らいで、冬山登山を再開した人が多かったと予想されます。
厳冬期の12~2月でも遭難が多いのは、通常の雪山登山に加えて、バックカントリー遭難と低山ハイクでの遭難が多いからです。私の収集した事例数から推定すると、3月上旬の9件を含めた遭難事例169件の内訳は、雪山登山85件(約50%)、バックカントリー35件(約20%)、低山ハイク32件(約20%)となります。このほかに、スキー場周辺で発生した管理区域外での遭難が17件(約10%)ありました。
年末年始の発生状況
1月18日に警察庁の遭難統計データが発表されました。年末年始(12/29~1/3)の遭難発生状況は40件(54人)、うち死亡者1人、負傷者20人でした。過去5年間では最も多く、過去10年間でも2番目に多い発生数となりました。コロナ禍の影響はほぼなくなったと考えられます。
警察庁データでは死亡者1人とありますが、12/30富士山(20代男性)、1/2八ヶ岳(40代男性)の死亡者数を含めると3人になります。富士山の事例は12/27~28に事故が発生したと推定されます。八ヶ岳の事例は1/6に遭難者が発見・収容されました。
バックカントリー遭難多発
マスコミではバックカントリー遭難が大きく報じられました。バックカントリー遭難が多いのは北海道、長野、新潟です。北海道では、羊蹄山(1/13、3/5)、日高・ペケレベツ岳(3/5)で雪崩死亡事故が起こっています。キロロスキー場付近では30代女性が行方不明です。長野では乗鞍天狗原(1/29)で外国人男性2人が雪崩で死亡しました。八方尾根(1/8)でも30代男性2人が行方不明です。野沢温泉スキー場周辺(1/28)で30代男性が雪崩で死亡、同日50代男性が埋没死しましたが、これはバックカントリーではなくスキー事故と考えられます。新潟でもバックカントリー遭難は多かったですが、死亡事例はありません。群馬の谷川岳(1/29)、上州武尊山(2/3)では雪崩死亡事故がありました。
バックカントリー遭難は多発しましたが、死亡事故は一部のみで、ほとんどは道迷いで動けなくなり救出されています。また、バックカントリーとはいえないスキー場周辺で起こった事例(当事者はバックカントリー用装備を持っていない)も、マスコミ報道ではバックカントリーと言ってしまっていることが多いです。このため、バックカントリー遭難は多発イメージが強調されすぎている傾向があります。
バックカントリーで最も危険なのは雪崩であることが、遭難事例から明確に示されています。雪崩のリスク判断や対策は専門性が高くて難しいです。バックカントリーをめざす人はまず雪崩対策に真剣に取り組むことです。

(北アルプス乗鞍天狗原)
全国で頻発した雪山登山遭難
雪山登山での遭難はバックカントリーよりも多く、しかも全国の山で起こっています。死亡事故はそれほど多くないですが、無雪期と比べて重傷事例が多いように感じます。北海道では大雪・旭岳(12/22)と日高・野塚岳(2/27)で死亡事故が発生しました。東北では真昼岳(1/8)で40代男性が死亡しました。
八ヶ岳では赤岳で2件(1/2、3/4)滑落死亡事故がありました。北アルプスでは死亡事故はなく、南アルプス易老渡(1/22)で落石による死亡事故、甲斐駒ヶ岳(2/21)、富士山御殿場口(12/30)で滑落死亡事故がありました。関東近県では奥秩父東沢渓谷(1/29)、鶏冠山(2/6)で滑落死亡事故がありました。初冬の男鹿山塊鹿又岳(12/4)で60代男性が行方不明になっています。また、新潟県の菅名岳(1/13)で50代男性が雪崩により死亡、米山(2/4)で60代女性が低体温症死しています。

(八ヶ岳)の岩場地帯
西日本では、白山周辺の野伏ヶ岳(2/18)、大峰・大普賢岳(12/14)、比良・蓬莱山(12/3)、石鎚山(12/24)で死亡遭難事故がありました。宮之浦岳(1/26)では韓国人男性が行方不明になっています。
現代の雪山登山は長期テント泊などは少なく、1~2日の短期間のものが主流になっています。冬山登山スタイルの変化に応じて大規模な遭難は少なくなり、小規模な遭難がさまざまな山域で分散的に発生しています。
低山も危険な冬山登山
冬山でも低山歩きが活発に行なわれているため、低山でも遭難事故が頻発して、かなりな頻度で死亡事故も起こっています。低山遭難が多いことは現代の特徴といえるでしょう。
関東では栃木の根本山(1/10)、古賀志山(1/21)、神奈川の大山三峰山(12/10)、千葉の高宕山(1/17)で死亡事故がありました。多くは滑落事故で、高齢者がめだっています。
岐阜県の金華山は事故の多い山ですが、12/16に70代男性が死亡、2/12に30代男性が行方不明になりました。また大黒山(3/5)でも60代男性が行方不明です。西日本では岡山の砥石山(12/27)、広島の象山(1/29)、十方山(2/26)で滑落死亡事故がありました。
プロフィール
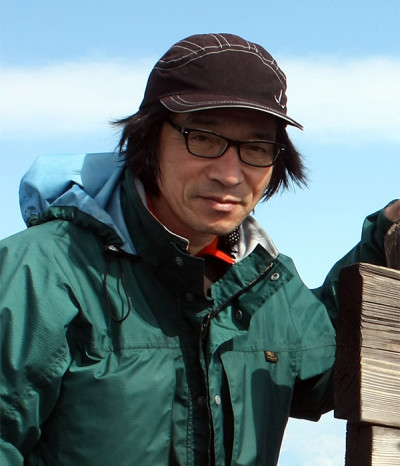
野村仁(のむら・ひとし)
山岳ライター。1954年秋田県生まれ。雑誌『山と溪谷』で「アクシデント」のページを毎号担当。また、丹沢、奥多摩などの人気登山エリアの遭難発生地点をマップに落とし込んだ企画を手がけるなど、山岳遭難の定点観測を続けている。
山岳遭難ファイル
多発傾向が続く山岳遭難。全国の山で起きる事故をモニターし、さまざまな事例から予防・リスク回避について考えます。
















