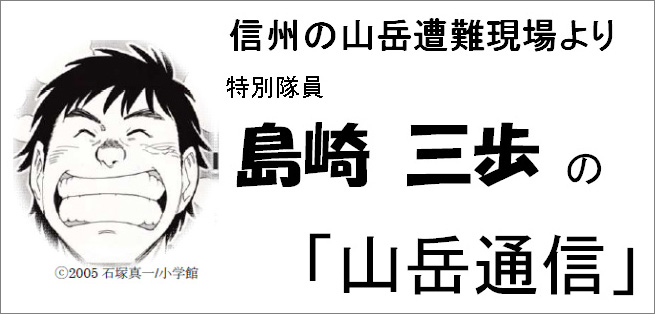【書評】人間と羆との死闘の歴史を刻む名著が復刻『羆吼ゆる山』
評者=伊藤健次
なんと彫りの深い記憶だろう。
著者は1917年生まれ。製炭業に携わる家族と北海道の奥山で過ごした日々の回想記だ。67歳で利き手の右手を負傷し、左手で字を書く練習をしつつ、つづられた一冊。過去を振り返った記述のはずだが、そこには驚くべきリアリティがあり、ページをめくる手が止まらなくなる。
本書は『アラシ 奥地に生きた犬と人間の物語』に続く、ヤマケイ文庫での今野作品復刻第2弾である。
主な舞台は日高(ひだか)山脈。西側の原始河川、染退川(しべちゃりがわ、現在の静内川)から元浦(もとうら)川にかけての広大な流域だ。私も思い入れの深いフィールドで、もう一冊の名著『秘境釣行記』とともに何度も読んだ。そのたび、あまりに鮮やかなディテールに、その場で同じ時を過ごし、同じ空気を吸っているような錯覚を覚え、今野保という人間の「記憶の質」に圧倒されるのである。
小学2年生の時、初めてヒグマに出会った日から物語は始まる。
「おじさーん、どこへ行くのー。裸足で山を歩くとトゲがささるよー。早く降りておいでよーっ」
片道5㎞の学校帰り。黒い人影らしきものと裸足の足跡を見た少年は、野生の世界に呼び寄せられるようにその影を追ってしまう。母に注意されていた異界の入口でもある桑の林を抜けて――。
戦前~戦後の北海道での山暮らしとはつまり「羆吼ゆる山」に踏み込んだ生活だ。傍らには命に関わる強力な野生動物がいる。それを狩り、生活の糧としてきたアイヌ民族の先達がいる。
12歳で銃猟を始めた少年は、腕利きのアイヌの猟師と親交を深め、狩猟の知恵や驚異的な経験を聞く。大グマの懐にしがみつき刺し違えた七郎。金毛と呼ばれるヒグマと仙造の切ない交流。沢造が語るぺテカリ源流の詳細な狩猟記はまるで、朗々と謡われるアイヌ神謡。今は失われた毛皮猟師の生活が、つぶさに浮かび上がる。
本人の体験だけでなく、他者が語る狩りの話さえ実写映像を目前にしたように具体的だ。この描写の源泉はどこにあるのか――。
今野一家は夏には猟師らと日高の源流に分け入り、20日あまりも釣りや狩りをして過ごしたという。日常も山の中なのに、さらに足を延ばし奥山に密着している。少年は幼い頃から原始の山谷の声に耳を澄まし、人の語る声を聞き取ってきたのだ。優れた書き手である前に、とても繊細で鋭敏な聞き手なのだと思う。熱気に満ちたヒグマとの死闘はもちろん、川で遭難した弓子の話が胸を突くのは、そうした著者の心根によるだろう。
日高山脈の地下に眠る地層が鮮やかに露出したかのような一冊。『羆吼ゆる山』には今野保という豊かな川が滔々と流れている。
今、同じ川をたどりながら、私は今野さんが語る日高の残像に嫉妬している。

羆吼ゆる山
| 著 | 今野 保 |
|---|---|
| 発行 | 山と溪谷社 |
| 価格 | 1,210円(税込) |
今野 保
1917年生まれ。製炭業を経て、炭鉱に26年間勤務。その後、土木会社を設立。事故で右手を負傷するが、左手で文字を書く練習を行ない、執筆活動を始める。著書に『アラシ 奥地に生きた犬と人間の物語』(ヤマケイ文庫)、『秘境釣行記』(25年春にヤマケイ文庫から復刊予定)ほか。2000年逝去。
評者
伊藤健次
1968年生まれ。写真家。北海道大学山スキー部OB。北海道岩見沢市在住。著書に『川は道 森は家』(福音館書店)、『伊藤健次の北の生き物セレクション』(北海道新聞社)ほか。
(山と溪谷2024年12月号より転載)
登る前にも後にも読みたい「山の本」
山に関する新刊の書評を中心に、山好きに聞いたとっておきもご紹介。
こちらの連載もおすすめ
編集部おすすめ記事

- 道具・装備
- はじめての登山装備
【初心者向け】チェーンスパイクの基礎知識。軽アイゼンとの違いは? 雪山にはどこまで使える?

- 道具・装備
「ただのインナーとは違う」圧倒的な温かさと品質! 冬の低山・雪山で大活躍の最強ベースレイヤー13選

- コースガイド
- 下山メシのよろこび
丹沢・シダンゴ山でのんびり低山歩き。昭和レトロな食堂で「ザクッ、じゅわー」な定食を味わう

- コースガイド
- 読者レポート
初冬の高尾山を独り占め。のんびり低山ハイクを楽しむ

- その他
山仲間にグルメを贈ろう! 2025年のおすすめプレゼント&ギフト5選

- その他