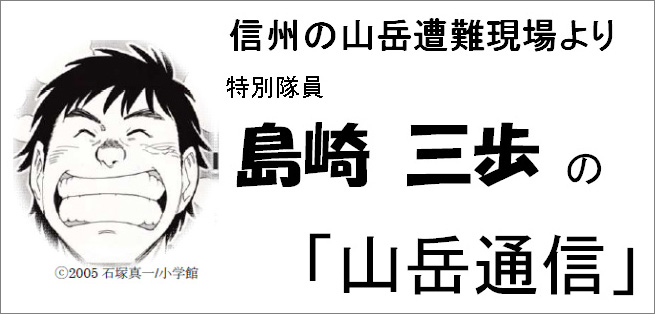身近な生き物の意外な事実 『野ネズミとドングリ タンニンという毒とうまくつきあう方法』
評者=盛口 満(沖縄大学教授)
時々、小学生を相手に授業をする。たとえば……と言って、ドングリを子どもたちに見せ、「ドングリを好きな動物は何?」と質問をする。すると、一斉に「リス!」という答え。ところが、リスはドングリを食べない。ドングリを食べ、かつ母樹の下から散布する働きをしているのは野ネズミの仲間だ。しかし、その野ネズミも、ドングリを迂闊に食べると死んでしまう。僕にとっても衝撃のこの事実を知ってからだいぶ時間がたつが、世間一般では、「ドングリといえばリス」という構図はまだまったく変化していない。だから、どのようにしてこの事実が解明されていったかというこの本の内容は、多くの人にとっては未知の物語だろう。
専門的な内容の本であるけれど、わからないところは飛ばして読んでも充分におもしろい。ドングリをリスが食べないのも、ネズミが食べて死んでしまうことがあるのも、ドングリにはタンニンという成分が含まれているからだ(ドングリの苦みの元)。一方、ネズミはこの毒成分を唾液と腸内細菌を使って、なんとか抑え込むことにも成功している(だからドングリの毒に馴れると食べることが可能になる)。この仕組みを明らかにするためには、ネズミの唾液を採取する必要があるけれど、ネズミの唾液を採取するのにも難問があって……。また、アメリカと日本ではドングリの成分に違いがある。アメリカのリスはドングリを食べる。ここらへんが「ドングリ=リス」の構図の出どころのよう。まだまだ紹介したりないが、字数が足りない。ドングリの季節の前に、必読!
(山と溪谷2022年5月号より転載)
登る前にも後にも読みたい「山の本」
山に関する新刊の書評を中心に、山好きに聞いたとっておきもご紹介。
こちらの連載もおすすめ
編集部おすすめ記事

- 道具・装備
- はじめての登山装備
【初心者向け】チェーンスパイクの基礎知識。軽アイゼンとの違いは? 雪山にはどこまで使える?

- 道具・装備
「ただのインナーとは違う」圧倒的な温かさと品質! 冬の低山・雪山で大活躍の最強ベースレイヤー13選

- コースガイド
- 下山メシのよろこび
丹沢・シダンゴ山でのんびり低山歩き。昭和レトロな食堂で「ザクッ、じゅわー」な定食を味わう

- コースガイド
- 読者レポート
初冬の高尾山を独り占め。のんびり低山ハイクを楽しむ

- その他
山仲間にグルメを贈ろう! 2025年のおすすめプレゼント&ギフト5選

- その他