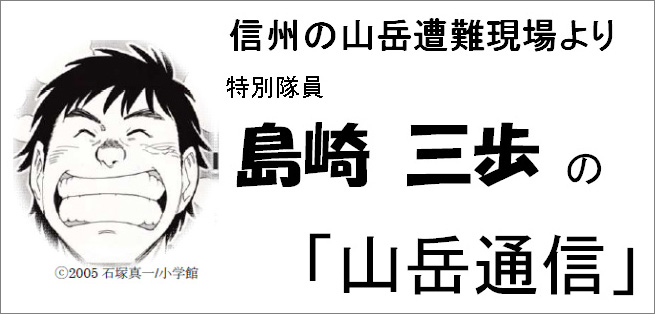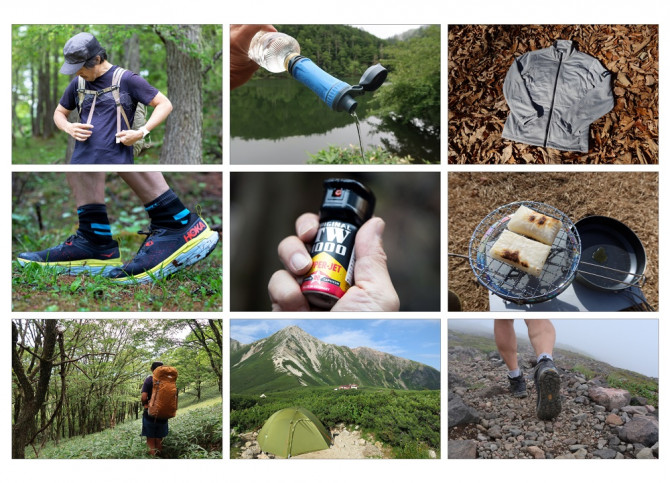富士山測候所の手書き観測記録が語る真実。1954年11月28日雪崩大量遭難事故の検証と将来予想
1954年の初冬の時期、富士山で雪山訓練をする登山者40人を襲った雪崩。これほどの規模の雪崩を、なぜ予測できなかったのか。その理由を読み解くとともに、暖冬が続く近年においても、雪崩の危険性は高まっている理由を説明する。
文・図版=大矢康裕
9月下旬のお彼岸を過ぎると、あれほど長く続いた35℃越えの猛暑がいつの間にか去っていきました。10月に入ってさらに涼しくなると、お彼岸には間に合わなかった彼岸花も咲き、「暑さも寒さも彼岸まで」とはよく言ったものです。そして10月20日に北海道の札幌で初雪の便りが聞こえてくると、山岳では早くも冬山シーズンに入ります。
今回のコラム記事では、冬山シーズンの始まりの11月末に起きた、1954年の富士山雪崩大量遭難事故について解説したいと思います。冬季の富士山は、アイゼンの歯が刺さらないほどのカチカチのアイスバーンによる滑落事故のイメージが強いですが、この雪崩事故はそんな常識を打ち破るほど強烈な印象を残しています。
本記事では当時の気象状況を富士山測候所の貴重な観測記録と気象庁第3次長期再解析JRA-3Q(ジェイラ・サンキュー)データを用いて再現し、検証してみました。そして気候変動によって将来の雪崩はどうなっていくのかを調査した結果、これまで誰も知らない驚くべき事実が判明しましたので、それについても本記事で解説いたします。

1954年11月28日の富士山雪崩大量遭難事故の概要
では、1954年11月に富士山で起きた雪崩大量遭難事故とはどのようなものだったのでしょうか。雪崩事故の概要はWikipedia、遭難当時の状況は「十大事故から読み解く 山岳遭難の傷痕」(羽根田治著、2020年、山と溪谷社)、日本山岳会会報1955年1月号、「山岳雪崩遭難と対策」(大井正一〈気象庁〉、日本気象学会機関紙「天気」1955年1月号)などで公開されていますので、興味がある方はぜひご一読ください。それらの文献からこの雪崩遭難事故の概要をまとめると以下のようになります。
初冬の富士山は、アイゼン歩行・ピッケルワークや滑落停止のための冬山トレーニングのメッカとして毎年のように多くの登山者がやって来る。1954年(昭和29年)11月28日も富士山は大学山岳部や社会人山岳会の人たちでにぎわっていた。そして10時40分ごろに、吉田口登山道のすぐ脇の吉田大沢で2回にわたって大きな雪崩が発生した。雪崩は吉田口の夏道登山道(尾根)や吉田大沢の7合目付近で日本大学、東京大学、慶応義塾大学のパーティの合計40名を襲い、15名(日本大学8名、東京大学5名、慶応義塾大学2名)が死亡した。
雪崩は吉田大沢の上部で発生して、標高差1600m、長さ4000mに達しており、11月の富士山としては前例のない巨大な規模のものであった。雪崩が発生した当時、南岸低気圧によって富士山7合目付近は暴風雪となっており、新雪が50cmくらい積もっていたという。吉田大沢では登山者はアイゼン歩行ではなく、新雪をラッセルしながら登っていた。また、富士山測候所の9時の気温は-6.6℃であり、平年より5℃ほど高かった。
図2に雪崩事故の概念図を示します。雪崩は吉田大沢を真っ直ぐに下っただけでなく、7合目から6合目の間から夏道登山道を乗り越えてツバクロ沢にも押し寄せ、吉田大沢と夏道登山道の7合目から6合目にいた登山者を巻き込んで、ともに3合目の少し上まで押し寄せてようやく止まっています。

図1の写真では冠雪の末端が5合目付近であることから、雪崩の規模の大きさが実感できると思います。この雪崩の直接の原因は南岸低気圧であり、JRA-3Qデータを使って再現した1954年11月28日12時の地上天気図を図3に示します。南岸低気圧が急激に発達しながら富士山の南を東に進んでいました。なお、JRA-3Qデータは6時間ごとのデータしかありませんので、図3は9時と15時の平均値を計算して作成しています。

富士山測候所の観測記録とJRA-3Qデータの解析で見えてくる真実
ご存知の通り、富士山には測候所があり、1932年(昭和7年)から2004年(平成16年)までの72年間、有人観測を実施していました。1895年(明治28年)に野中到・千代子夫妻が初めての富士山頂での越冬観測に挑んだ実話に基づく新田次郎の小説「芙蓉の人」を読まれた方もいると思います。目的を果たせず途中下山したものの、この命がけの挑戦が富士山測候所設立の礎(いしずえ)になりました。
残念ながら2004年夏季が過ぎると有人観測は終了し、富士山測候所は廃止され自動観測になってしまいました。しかし、72年間にわたる富士山測候所の観測記録は大変貴重なもので、この雪崩遭難事故の気象状況についても当時の観測記録から知ることができます。
図4に富士山測候所の実際の気象観測データの例として、雪崩遭難事故が起きた1954年11月の3時間ごとの気温の観測記録を示します。

これは富士山測候所の職員たちが手書きで残した記録であり、所々に書き直しがある生々しいものです。28日に雪崩が起きる直前の9時の気温(赤枠)を見ると「93.4」となっていますが、これは氷点下の気温はマイナスの記号「-」が手書きでは判別しにくく、マイナスの気温に100を足して記録していたため、実際の気温は逆に100を引いた「-6.6℃」となります(冒頭にある事故の概要の気温の出典)。
この富士山測候所の手書きの記録を読み取って、1954年11月18日~29日の3時間ごとの富士山頂の気温と風速の推移グラフにしたものが図5です。

図6では11月27日15時~28日15時の富士山頂の風速・風向の1時間ごとの詳細を示しています。富士山測候所の記録では日ごとの積雪深さしかありませんので、JRA-3Qデータを用いて1954年11月18日9時から28日21時の富士山の1時間降雪量と積算降雪量の推移を再現したものが図7です。


これらのデータから、19日に通過した南岸低気圧(図割愛)によって30cmほどの降雪があり、21日後半からの気温の低下によって積雪表面が凍結し、28日の南岸低気圧による大量の降雪がその凍結した雪面の上に積もって表層雪崩を起こしたであろうということが読み取れると思います。
また、図6に示したように通り、28日の7時から9時にかけて、いったん風は弱まったものの、10時~11時には風速30m/sを超える非常に強い風が吹き荒れています。まさに「暴風雪」となりました。注目すべきは風向で、6時までは概ね南東(SE)の強風でしたが、風向が東(E)に変わると風が弱まり、10時から東北東(ENE)や北東(NE)の風になる猛烈な風が吹いています。
南東の風によって吉田大沢では吹き溜まりとなって大量の雪が積もり、風向が東北東や北東に変わって烈風がまともに吉田大沢上部の吹き溜まりに当たったことによって、雪崩が発生したという可能性が非常に高いと思います。
日本山岳会会報1955年1月号でこの雪崩発生の原因の一つとして上記の指摘がありますが、富士山測候所の観測記録とJRA-3Qデータによる再現で裏付けができたと思います。
雪崩遭難事故の真因:「疑似好天」が起きて被害が大きくなった
このように、この雪崩遭難事故では2つの南岸低気圧による「先行降雪と雪面氷結」「その上に大量降雪」と「風向の変化」が大きな要因になっていました。このようなこと自体は複数の南岸低気圧が通過した時には起こりうる現象で、決して珍しいことではありません。問題は28日の7時から9時にかけていったん風が弱まっていることです。
この原因を探るために、JRA-3Qデータを使って再現した1954年11月28日3時、9時、15時の700hPa等高度線・風速(色分け)の様子を図8に示します。

700hPaは標高約3000m(7合目付近)に相当し、等高度線は地上天気図の等圧線に相当します。南岸低気圧の北側に形成された風が強いエリアが、南岸低気圧の東進とともに東に移動していますが、9時に風速が弱まっていることがわかります。
南岸低気圧が発達する過程で、なんらかのメカニズムによって風が弱まったようです。南岸低気圧が急激に発達した15時には等高度線の間隔も狭くなって、風が非常に強くなっています(地上天気図で等圧線の間隔が狭くなると強風が吹くのと同じ理由です)。
28日朝の出発直後の7時から9時にも風速25~30m/sの強風が続いていれば、あるいは危険を感じ取って撤退したパーティーも少なからずいたのではないでしょうか。この風に関する「疑似好天」のため、冬山訓練を続行してしまったことが被害を大きくした真因と思われます。南岸低気圧による雪崩リスクを知り、いったん風が弱まっても決してだまされないことが、この雪崩遭難事故から学ぶべき貴重な教訓と思います。
過去から現在の富士山頂の観測記録が示す未来への道標(みちしるべ)
では気候変動のなかで積雪は減るため、将来はこのような雪崩遭難事故はなくなっていくのでしょうか。富士山測候所の観測記録やその後の無人観測データを解析してみると、驚くべき結果になりました。
図9に1933年から203年の富士山頂の年間の最低・平均・最高気温の推移を示します。平均気温は100年あたりで1.36℃、最高気温は同2.3℃上昇しているのに対して、最低気温は同0.45℃しか上昇していません。そして最低気温は、2023年1月25日に観測史上4位の-36.3℃を記録したのをはじめ、観測史上5位までの記録は後半に発生しています。つまり気候変動にかかわらず、強い寒波が来る時は来るのです。これが現在でも毎年のように日本海側の地方でドカ雪による被害が起きている原因の一つと思います。

さらに図10に1951年から2004年の富士山測候所の年間の最深積雪の推移を示します。年間の最深積雪というのは、その年に最も雪が積もった時の積雪の深さです。1992年ごろまでは最深積雪はなんと増加傾向になっています。1996年から2004年は増加が止まっているように見えますが、記憶に新しい2014年2月14日の南岸低気圧による大雪を考慮すると、現在に至るまで最深積雪の増加は続いているのかもしれません。年による変動はありますが、現在でも大雪が降る時は降ることを意味します。これは仮想的なシミュレーションではなく、実際に起きている事実です。つまり、最低気温の維持傾向と最深積雪の増加傾向を考えると、将来も雪崩のリスクは決してなくならないということになります。

惜しむらくは、富士山測候所での有人観測の終了です。竜巻並みの最大瞬間風速91m/sの記録が残る富士山頂のような過酷な環境では、下界のような風や積雪の自動観測ができないのです(計測器がすぐに壊れるため)。時代の流れで仕方がないとは思いますが、そこで実施された過去の貴重な観測記録を決して埋もれさせてはなりません。そこに残る記録を読み取って丁寧に解析してあげて、命を吹き込むことによって、このように私たちに未来に対する道標(みちしるべ)を示してくれるのです。
プロフィール

大矢康裕
気象予報士No.6329、株式会社デンソーで山岳部、日本気象予報士会東海支部に所属し、山岳気象の研究や山岳防災活動を実施している。
日本気象予報士会CPD認定第1号。1988年と2008年の二度にわたりキリマンジャロに登頂。キリマンジャロ頂上付近の氷河縮小を目の当たりにして、長期予報や気候変動にも関心を持つに至る。
2017年には日本気象予報士会の石井賞、2021年と2024年には木村賞を受賞。2022年6月と2023年7月にNHKラジオ第一の「石丸謙二郎の山カフェ」、2023年12月に「世界の何だコレ!?ミステリー年末SP」などに出演。
著書に『山岳気象遭難の真実 過去と未来を繋いで遭難事故をなくす』(山と溪谷社)
山岳気象遭難の真実~過去と未来を繋いで遭難事故をなくす~
登山と天気は切っても切れない関係だ。気象遭難を避けるためには、天気についてある程度の知識と理解は持ちたいもの。 ふだんから気象情報と山の天気について情報発信し続けている“山岳防災気象予報士”の大矢康裕氏が、山の天気のイロハをさまざまな角度から説明。 過去の遭難事故の貴重な教訓を掘り起こし、将来の気候変動によるリスクも踏まえて遭難事故を解説。
こちらの連載もおすすめ
編集部おすすめ記事

- 道具・装備
- はじめての登山装備
【初心者向け】チェーンスパイクの基礎知識。軽アイゼンとの違いは? 雪山にはどこまで使える?

- 道具・装備
「ただのインナーとは違う」圧倒的な温かさと品質! 冬の低山・雪山で大活躍の最強ベースレイヤー13選

- コースガイド
- 下山メシのよろこび
丹沢・シダンゴ山でのんびり低山歩き。昭和レトロな食堂で「ザクッ、じゅわー」な定食を味わう

- コースガイド
- 読者レポート
初冬の高尾山を独り占め。のんびり低山ハイクを楽しむ

- その他
山仲間にグルメを贈ろう! 2025年のおすすめプレゼント&ギフト5選

- その他