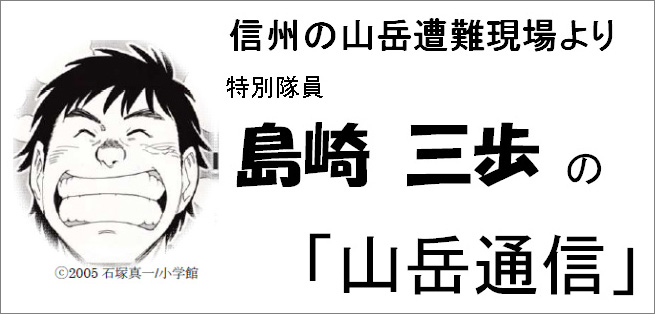山で生まれ、山で生きる。紀伊半島で継承されてきた、炭焼き、林業の歴史を綴った名著が復刊
炭焼きの家に生まれ育った著者・宇江敏勝さんが山の生業や暮らしを綴った記録文学の名著『山びとの記』がヤマケイ文庫で復刊。初版が刊行された40年前、すでに失われつつあった山の営みと文化を本書(第一章 炭焼きと植林「山を住居として」)から一部抜粋して紹介します。

祖父から父へ、そして私へと受け継がれてきた炭焼きは、いわば家業とでも言うべきかも知れない。しかも社会的地位あるいは経済的基盤、そして生活環境からして、まことに水準が低いというか、むしろアウトローの生業でしかなかった。家業あるいは職業というよりも、しがない稼ぎ、山稼ぎといったほうがふさわしい。登山家はそこに山があるから登る、ということだが、われわれは山に生まれたから、そこに山があったから、山で生きるより仕方がなかったのである。
山稼ぎにもさまざまな職種がある。高度な技術と大がかりな組織でもって、長期間におよぶ事業もある。たとえば古いものでは鉱石の採掘、新しくはダムの建設などがそれだ。ダムの建設事業は、山稼ぎと呼ぶにはあまりに近代科学的すぎてぴんとこないけれども、水という森林資源にかかわる仕事として、頭の片隅に留めておきたい。後には私も、十津川村の山中で、ダムに水没する地帯の木を伐って除く作業に従事するのである。
鉱山業も多くは山中における仕事であった。現在ではほとんど廃鉱となってしまっているが、熊野から吉野にかけての山々にも、鉄鉱石や石炭を採掘した跡を見ることができる。山師たちは深山幽谷を彷徨し、有望な鉱脈を発見すると、人を入れて掘ったのである。
そして木に関連する仕事がある。これは水の利用や鉱物に比べてはるかに範囲が広く、また一般的なものといえよう。ダムは一度建設すると半永久的であり、鉱物の採掘も一回きりのものだが、森林は伐採してもまた新しい芽を出して再生し、あるいは植林によって、より利用価値の高い木材の生産もなされてきた。現代では森林は伐採するばかりでなく、植林し手入れもするという具合に作業が循環しているのがふつうである。
建築用材や紙の原材料として、われわれの生活に欠くことのできない木材の生産は、昔から現代にいたるまで、山に生きる者のもっとも一般的な生業とされてきた。伐採にかかわる作業、それを搬出する作業がある。伐採跡はそのまま放置しても森林は再生するけれども、自然に任せておくと長い年月がかかり、経済的効率も悪いので、建築用材として優秀な樹種―杉、檜、松、カラマツ―を植林するという作業も行なわれる。これらの木は植えておけば自然に山林になるというものではなく、下草刈り、蔓切り、そのほか長年にわたって手入れをしなければならないから、伐採よりも造林(植林と撫育)のほうが作業量としては多いのである。
森林はまた薪や木炭など、われわれの生活に必要な燃料を生産するところでもあった。現在では里はおろか山小屋までもプロパンガスが浸透しているけれども、二十年ばかり前には、薪や木炭を暖房用あるいは炊事用の主要な燃料として使用していた。同時にそれを生産し、消費者に提供する炭焼きという生業が存在したのである。
木炭の利用は暖房・炊事用のみにとどまらず、工業用燃料として、金属加工などにも多く用いられた。その歴史は古く、奈良時代すでに、高級燃料として宮中や貴人のあいだなどで広く用いられていたといわれるが、奈良の大仏を鋳造した際のエネルギー源も、すべて木炭であった。大仏の仏体・蓮座の鋳造に使用された木炭の量は一万六六五六石にものぼった(岸本定吉『炭』)。今日の量に換算すれば約八○○トン、炭俵(一五キログラム入り)にして、五万三○○○俵使用したことになるという。
木炭は明治以降は家庭用燃料として広く普及をとげるが、同時に重工業の発達につれて、需要にいっそう拍車がかかるのである。製鉄や鍛冶はもちろんのこと、汽船も自動車も、そして人気のあのSLも、木炭やその加工品を燃料として走っていた時代があった。大正六年になると、工業用に奪われて、家庭用木炭が極端に品不足になり、東京や大阪などの大消費地では「木炭飢饉」と騒がれるほど深刻な事態だったという(畠山剛『炭焼物語』)。石油ショックならぬ木炭ショックである。価格は暴騰し、製炭業が奨励されたことはいうまでもない。
戦後、昭和二十四年になって木炭の政府統制は解かれるが、二十年代の終わりごろまでは、まだ木炭の時代であった。三十年代に入ると、電気、石油、都市ガス、プロパンガスなどに押されて、木炭の需要は激減するのである。昭和三十二年までは全国で二○○万トン以上生産されていたものが、その後は毎年減少し、昭和四十八年には年間八万トンにすぎなくなったという(岸本定吉、前掲書)。
現代では一部工業用として使用されるほかは、茶の湯炭や、鰻の蒲焼、ビフテキなど高級料理の燃料として、辛うじて命運を保っているありさまである。
※本記事は『山びとの記 木の国 果無山脈』を一部掲載したものです。
『山びとの記 木の国 果無山脈』
郷愁を呼び覚ます、記録文学の名著。
紀伊半島で育まれた山林労働の歴史と文化、そして思考。
奥深い熊野の山小屋から生まれた稀有な山の自叙伝がヤマケイ文庫で復刻。
編集部より
このたび弊社では、宇江敏勝さんの『山びとの記』をヤマケイ文庫に収録・刊行しました。
先祖代々、炭焼きの家に生まれ育った著者が、山仕事に従事するかたわら自らペンをとった記録文学は1980年に中央公論社から刊行されたのち、2006年に新宿書房のシリーズに収められたものです。
初版から40年たちますが、在りし日の伝統的な山の生業や暮らしを克明に記した本作は、昭和の貴重な林業史となっており、また、“山びと”としての来し方を振り返る文章は静謐であたたかく、日本の風土や自然に対する郷愁を呼び覚ましてくれます。
『山びとの記 木の国 果無山脈』
著: 宇江 敏勝
発売日:2021年9月18日
価格:1100円(税込)
【著者略歴】
宇江敏勝(うえ・としかつ)
1937(昭和12)年、三重県尾鷲市の炭焼きの家に生まれる。和歌山県立熊野高校を卒業後、紀伊半島の山中で林業に従事するかたわら、文学を学ぶ。作家、林業家。新宿書房より、「宇江敏勝の本」シリーズ(全15冊)、「民俗伝奇小説集」(全10巻)などがある。
山びとの記
郷愁を呼び覚ます、記録文学の名著。 紀伊半島で育まれた山林労働の歴史と文化、そして思考。 奥深い熊野の山小屋から生まれた稀有な山の自叙伝がヤマケイ文庫で復刻。