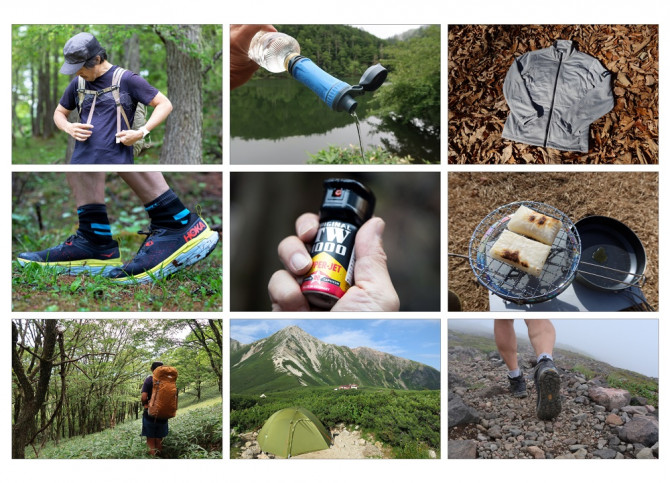働いて、食べて、寝る…昭和40年代、林業作業現場のとある一日
炭焼きの家に生まれ育った著者・宇江敏勝さんが山の生業や暮らしを綴った記録文学の名著『山びとの記』がヤマケイ文庫で復刊。初版が刊行された40年前、すでに失われつつあった山の営みと文化を本書から一部抜粋して紹介します。
今回は、果無山脈での造林作業の一日を日記から再現した部分より抜粋。カシキ(炊事係)や仲間との会話に、労働と生活の情景がありありと浮かびます。

地拵え作業の一日
つぎにナメラ谷における地拵え作業の一日を、当時の日記から再現してみたい。昭和四十二年十二月一日の模様である。
―― 四時起床。他の連中はまだ寝ているが、今朝は私が当番なのである。つまり朝はカシキのおばさんの仕事が忙しいので、交替でそれを手伝うのだ。一回につき二○○円の手当てがつく。
もう大釜の中で飯が煮詰り、味噌汁がいつもの朝と同じ、あたたかく懐かしい匂いを漂わせている。丸顔で小柄なおばさん(五十五歳くらい)は、流し場で漬物を切りながら、朝がた便所の方角で変な物音がして怖かったと言う。バタンバタンて鳴っとったよ。なんの音やろ、小便したかったけど、さびしいてよう出て行かなんだ、と。
発電機を廻して電灯をつけるのも当番の役目だ(それまでカシキはローソクの明りで仕事をしているのである)。発電機は、飯場の外に小さな建物をつくって入れてある。外は暗く、懐中電灯をともして出かけた。栃の木が屋根の上に黒々と大枝を拡げ、その梢に星がある。寒い。凍てのために発電機は始動しなかった。何度も紐を引いて腕がくたびれた。
やむをえずカーバイトランプに火を点けた。その明りで、アジの干物を焼き、一四人分の弁当箱に飯を詰めた。それで当番としての仕事は終わり。五時近く、通路の両側の棚ベッドから、男たちが這い出してくる。朝食のメニューは、飯、味噌汁、たくあん漬、それに弁当のおかずの残り物の炒り大豆、生卵。
今日も現場は本谷の「ロ」林班である。小屋からそこまでは、稜線を登り、山腹を横に辿っておよそ三十分の道程だ。五時三十分、私は仲間より少し早く、弁当袋とともに猟銃を持って出かけた。朝の薄暗い山道で、早起きの雉やヤマドリが餌を漁っているのに、ときどき出喰わすからである。騒ぎ立てないでそっと近寄れば、射止めることもできるのだ。だが今朝は山鳩すら見かけなかった。
南の方角のまだ暗い山頂に、灯火が二つ見えていた。眼を凝らしてみると、それらはかすかながら動いている。熊野灘の沖合を航海する船の灯だ。この山からは数十キロの彼方、船体は見えず、海も朝靄に遮られて空と見分けがつかない。強い風が鳴りひびいて吹いている。ここは山の八合目あたりで標高一○○○メートルくらいであろうか。
現場に着き、焚火を始めていると、仲間の五人もやってきた。焚火で手を温めながら、下刈鎌と鉈を研ぐ。それから煙草をいっぷく吸って一斉に作業を始めた。
午前中の作業場は、立木はほとんどないが、伐採された木の末が積み重なっていて、前進を妨げられる。六人が山腹の斜面へ上から下へ縦に並んで、働きながら前進する。切断した木や枯草を一方に積んで片づけるのだが、枯木が厚く重なっているのに出会うと、仕事がはかどらないのである。薄い草叢だけの部分になると、しめしめといった気持だ。小さな谷を隔てた向こうの「イ」林班では、Nたちの班が今日から作業を始めた。N班は四人なのだが、一人は風邪で休んでいて、いま見えているのは三人だけだ。ときどきそちらを眺めると、太い木を抱いて持ち上げたり、枯れて固いやつを必死で叩くなど、彼らも難渋している様子である。
昼飯どきにはまた焚火をする。
昼飯のおかずは、アジの干物と炒り大豆の醤油漬と、たくあん。私はすこぶる健啖家である。人並みの弁当箱では足りず、いつも飯盒に八分目ほど飯を詰めてくるのだ。それを念入りに時間をかけてたいらげる。仕事が飯を食うのだと思う。
飯が三分の一ほどになったとき、おかずのアジはもうなくなっている。そこで残りの飯に醤油漬の炒り大豆を載せ、茶を入れて茶粥をつくることにした。焚火の上に置き、いっぷく吸いつけて待つ。やがてそれは沸き立ってきた。私はおもむろに飯盒を焚火から下して蓋をとり、熱いので新聞紙をあてがって持ち、ふたたびゆっくりと食事を再開するのである。飯盒は鉉のつけ根の片方に穴があいているので、そこのところを向こう側にしなければならない。箸でもって熱い流動物をたしなむように口に運び、そのなかに混っている大豆をていねいに噛みしめる。やがて粥の温もりが内臓から疲労した五体へじんわりと拡がってゆき、その束の間、幸福感のようなものを味わうのである。
昼食後は、枯れた草叢に寝ころんで小一時間昼寝。朝のうちの風が嘘のようにおさまって、暖かい陽射しが甦ってきた。カラスが啼く。すぐ近くの枯木にとまって、その羽音や啼くときの息遣いが荒々しく、押しつけがましく、眠りを妨げられる。それは啼くというよりも唸っているといった感じだ。
午後は立木のなかで働く。しかしその立木のあいだにも、伐採した木の末が縦横に横たわっていて、作業は午前中よりもさらに遅滞する。手首が捻挫でもしたかのように痛む。主として腕に負担をかける仕事を長く続けてきて、慢性の筋肉痛になってしまったのである。とくに寒い季節がいけない。痛みを我慢しながら憂鬱な気持で働いていると、下刈鎌の刃が石にあたって欠けた。
遠い山から銃声が聞こえた。今日は鹿猟の解禁日なのだ。
「ああ、今年は鹿のくちあけにも休めなんだなあ」とCが嘆息まじりに言う。
「鹿撃ちにはもってこいの日和や」とTが相槌をうつ。
作業班では、CとTと私の三人が狩猟免許をもっている。解禁日までに「ロ」林班の地拵えを終えようとして頑張ってきたのだが、間に合わなかったのである。銃声を聞くと、なんだかすべての獲物を他人にとられてしまいそうな、口惜しい気持だ。
四時三十分、作業終了。道具を置いていっぷく吸いつけながら、仲間たちと遠い山々を指して、あれはなんという名の山だ、とか、兵生の集落はあの下のあたりにあるんだ、といった話をする。見飽きた山々、暗く暮れ沈んでゆく物音も色彩もない淋しい光景。また寒くなってきた。
小屋に帰ると、他の班の者が戻るのを待つあいだ、石にあてて欠けた下刈鎌を研ぐ。カシキのおばさんがそばへ来て、水道のホースが裂けている、とか、雑役をしているE少年が、わずかな稼ぎにもかかわらず、その金を使わず、親にもびた一文渡さず、貯金もせず、全部現金で持っているそうや、といった話をする。
「ほなもう一○万円くらい持っとるかい?」と私が訊くと、
「そがいにも持ってないやろのう」とおばさんは言った。「お金は一〇万円ほど貯めるまではひまかかるんやぜ。一○万円貯めたら、そこからむこうはわりと早いけど」
発電機が唸って、小屋に電灯がともった。夕飯のおかずは、高野豆腐と干シイタケの煮物、塩鯖の焼いたもの、たくあん。食事代は個人の回数を記帳しておき、月末の勘定から差引くことになっている。一食につきほぼ一○○円である。
飯の前に焼酎を飲む。焼酎をやるのは私だけで、ほかの連中は日本酒を飲んでいる。その代金も月末の勘定から差引かれるのである。
夜、交替で風呂を使いながら、ある者は洗濯をするし、ある者はストーブで身体を暖めながら、この事業所のことを悪しざまに言っている。親方や宿舎や食事を非難したり、作業が困難で儲からないなどと愚痴をこぼすことは、労働者にとって日常欠くべからざる慰安なのである。
一番端の部屋(そこは娯楽室になっている)で将棋を指している者、横合いから眺めて口出しをしている者もいる。私は食卓で二日分の日記をまとめて書いた。おばさんは、夜食に即席ラーメンを煮て(こんなことは毎晩ではない)、私の前に一皿を置き、奥の娯楽室へも運んだ。その後で一人が出てきておばさんに言う。「おばさんよ、ぜいたく言うて悪いけど、卵一つずつくれんやろか、ラーメンへ入れるんや」
「いま卵食べた人は、あしたの朝はなしやで」とおばさん。すると卵をとりにきた使者は、奥の部屋へどなって言うのである。「おい、いま卵食べたらあしたの朝はないんやとう。それでもかまわんのか!」
「かまわんよ、美味いものは宵のうちに食えちゅうわだ」という返事が返ってきた。
が、やがて彼らも寝てしまう。夜が更けるにつれて冷えこみがきびしくなってきた。私はストーブにあたりながら、井伏鱒二著『黒い雨』を読む。小便に出てみると、外の洗面所では飛び散った水しぶきが、あたり一面に凍っていた。風呂場のそばを通りかかると、食事の後片づけを終えたおばさんが風呂に入ろうとして、着物を脱いだところだった。
「すまんけど、水を汲んできてくれんやろか、熱うて入れんのや」とおばさんは言った。
私はバケツで洗面所に貯めてある水を運んだ。「すまんのう、また水道が凍ったらしゅうて、水が出らんのや」とおばさんが恐縮したように言う。裸形がまともに見えて、年に似合わず肌白く、立派なものだと私は思う。
寝る前に私は、手首にシップ薬を塗り、包帯を巻く。湿布薬の強い匂いに慰められて寝に就いた。
※本記事は『山びとの記 木の国 果無山脈』を一部掲載したものです。
『山びとの記 木の国 果無山脈』
郷愁を呼び覚ます、記録文学の名著。
紀伊半島で育まれた山林労働の歴史と文化、そして思考。
奥深い熊野の山小屋から生まれた稀有な山の自叙伝がヤマケイ文庫で復刻。
編集部より
このたび弊社では、宇江敏勝さんの『山びとの記』をヤマケイ文庫に収録・刊行しました。
先祖代々、炭焼きの家に生まれ育った著者が、山仕事に従事するかたわら自らペンをとった記録文学は1980年に中央公論社から刊行されたのち、2006年に新宿書房のシリーズに収められたものです。
初版から40年たちますが、在りし日の伝統的な山の生業や暮らしを克明に記した本作は、昭和の貴重な林業史となっており、また、“山びと”としての来し方を振り返る文章は静謐であたたかく、日本の風土や自然に対する郷愁を呼び覚ましてくれます。
『山びとの記 木の国 果無山脈』
著: 宇江 敏勝
発売日:2021年9月18日
価格:1100円(税込)
【著者略歴】
宇江敏勝(うえ・としかつ)
1937(昭和12)年、三重県尾鷲市の炭焼きの家に生まれる。和歌山県立熊野高校を卒業後、紀伊半島の山中で林業に従事するかたわら、文学を学ぶ。作家、林業家。新宿書房より、「宇江敏勝の本」シリーズ(全15冊)、「民俗伝奇小説集」(全10巻)などがある。
山びとの記
郷愁を呼び覚ます、記録文学の名著。 紀伊半島で育まれた山林労働の歴史と文化、そして思考。 奥深い熊野の山小屋から生まれた稀有な山の自叙伝がヤマケイ文庫で復刻。