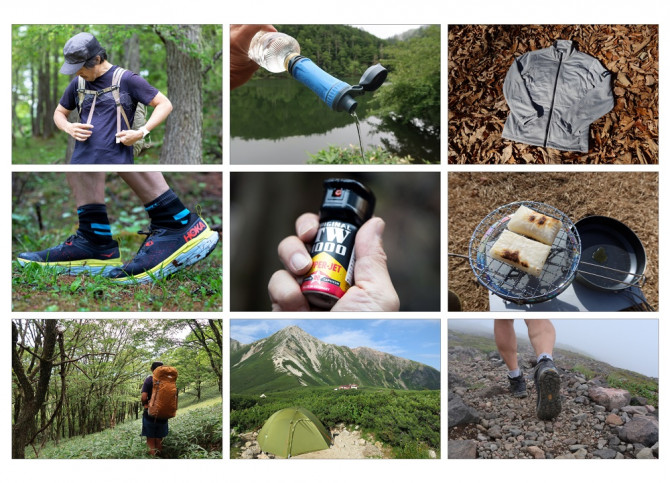ハトはなぜ公園に集まるの? ドバトの強かな生き方
馬鹿っぽい、汚い、何考えているのかわからない……など、マイナスイメージも多く、時には害鳥として駆除もされる身近な鳥、ハト。そんなハトの世に知られていない豆知識がたくさんつまった本『となりのハト 身近な生きものの知られざる世界』(山と溪谷社)より、思わず誰かに話したくなるハトの秘密のエピソードをご紹介。
第3回目は公園で生きるハトの秘密です。

ドバトというハトはいない
じつはドバトというハトはいない。
ここまで散々、ドバト、ドバトと書き連ねておいて、いまさらこの人は何を言い出すのかと思うかもしれない。正式な名前ではないという意味である。生物の正式な日本名は和名といい、鳥の場合は日本鳥学会が定めている。
ドバトの正式な名前、すなわち和名はカワラバトである。そのため鳥類図鑑にはドバトではなく、カワラバトの名前で載っている。ただ、それだと読者はわからないことがあるから、カワラバト(ドバト)と書かれていることも多い。ちなみに和名を学名という人もいるが、これは誤り。学名は、ラテン語で表記する世界共通の生きものの名前であって、カワラバトの学名はColumba liviaとなる。
では、ドバトという名前は何なんだろうか。
簡単にいうと、ドバトは野生のカワラバトを人間が捕まえて飼育し、世代交代をさせながら品種改良した飼養品種の総称である。マガモを家禽化したアヒル、セキショクヤケイを家禽化したニワトリと同じで、カワラバトを家禽化したのをドバトと呼んでいるのだ。けっして、大群でドバッといるからドバトという名前になったわけではない。
いろんな色がいる
さて、そのドバト、北海道から沖縄まで全国にくまなく分布する鳥である。絶海の孤島である小笠原諸島にすら、かなりイレギュラーだが姿を見せることがあるというから、その飛翔能力には舌を巻く。やはりあの鳩胸はただ者ではない。
全長(嘴から尾羽の先までの長さ)は約三三センチメートル。鳥としては中型の部類だ。嘴は小さくて、鼻のところにはコブのような盛り上がりがあり、これはハトに共通する特徴である。目は虹彩が赤く瞳が黒い。そのため血走ったような目つきになり体の色は、基本的には青みがかった灰色である。首から胸にかけては金属光沢に輝く羽毛が生えていて、見る角度によって青や紫に怪しく変化する。この色は構造色といって、羽毛に微細構造があって、光の当たり方によって見える色が変わるのである。
ところが、公園に大群でたむろしているハトたちを眺めると、灰色の鳥ばかりではないことに気がつく。その色のバリエーションは厳密に分類すると一五〇にもなるといわれ、大きく分けると、翼に黒線がある「灰二引」、翼が黒く白い斑点がある「黒ゴマ」、体が黒と灰色のまだら模様の「灰ゴマ」、ほぼ全身が黒い「黒」、全身や翼が茶色い「栗」、全身が真っ白な「白」の六パターンがある。そのうちの「灰二引」が、野生のカワラバトとほぼ同じ色や模様をしている。
いったいどうして、ドバトにはこんなに色のバリエーションがあるのだろうか。それは野外にいるすべてのドバトが、かつては人が飼っていた鳥か、またはその末裔で、家禽が野生化した鳥だからである。
普通、生きものは種によって色や模様にそれほどバリエーションがない。例えば、スズメは世界のどこでも同じ色や模様をしている。生存に有利な色や模様の個体が生き残ってきたため、だいたい同じような色や模様になるのだ。ただ、同じ種であっても生息する地域が違うと、色や模様が多少異なることもある。ところが、ドバトは同じ場所に棲んでいるのに、いろんな色の鳥がいる。そのわけは人間が飼育し交配を重ねて作り出した品種だからで、言ってみれば、人間の選り好みで生み出した結果なのである。その作った品種を常に野外に供給し続けているから、さまざまなバリエーションのドバトをいつでも見ることができるのだ。
ドバトはなぜ公園にいるの?
さて、ドバトといえば公園である。最近はエサやり禁止の公園が多くなり、あまりドバトを見なくなったが、少し前までは公園に行くと噴水の周りにドバッと群れている光景によく出会った。では、彼らは公園で何をしているのだろうか。じつは、ある人に会うのが目的で来ているのである。
そのある人とは、エサをくれる人たちである。ドバトがいる公園には必ずエサをやる人たちがいる。たまたま持っていたお菓子をハトにやる人や、なかにはわざわざハトのために大量の食パンを持参する人もいて、入れ代わり立ち代わりエサをやっていく。一〇年くらい前までは、売店でハトのエサまで売っていたくらいだから、ドバトにとって公園は簡単に食べものが手に入るすてきな場所なのである。
公園のドバトはいつも地面にいるイメージがあるが、それは食べているときの一時でしかない。ほとんどの時間は、木の上や建物の屋根の上などにとまって休んでいるのだ。ある調査では日中、採食していた時間は全体の二〇%しかなく、七〇%は休んでいたという。エサをくれる人が現れると、それっ!と地面に舞い降りて、ガツガツ食べ、食べ尽くすとまた屋根の上にとまってウトウトする。そんな優雅な時間をドバトは公園で過ごしていたのだ。
公園に来る理由はもう一つある。それは求愛である。
地上に降りているドバトの群れを見ていると、ときどき、一羽を追いかけ回している鳥がいるのに気がつくことがある。これが求愛行動真っ最中の光景だ。追いかけているのがオスで、追われているのがメス。しばらくすると、オスは喉を大きくふくらませて、あの玉虫色に輝く首の色をメスに見せつけるように、くるくると回りだす。
そのとき「クルッポー、クルッポー」と鳴き声を出してメスに求愛するのである。童謡ではハトは「ポッポッポー」と鳴くとされるが、けっしてドバトは「ポッポッポー」とは鳴かないのだ。
この後、メスに気に入られると、二羽は寄り添うようになり、オスはメスの首の辺りを羽づくろいしたりして、さらに親密度が高まる。これで求愛は成功だ。しかし、見ているとたいていはうまくいかず、メスはエサに釣られてどこかに行ってしまうことが多い。
第一章でも書いたように、ハトの繁殖期間は一年中なので、この求愛の様子も一年中見ることができる。とても面白い行動なので、ハトの群れがいたら注目してみてはいかがだろうか。
※本記事は『となりのハト 身近な生きものの知られざる世界』(山と溪谷社)を一部掲載したものです。
『となりのハト 身近な生きものの知られざる世界』
ハトの世に知られていない豆知識がたくさんつまった、身近な生きものの世界を見る目が変わる一冊
『となりのハト 身近な生きものの知られざる世界』
著: 柴田佳秀
価格:1485円(税込)
【著者略歴】
柴田 佳秀(しばた・よしひで)
1965年、東京生まれ。東京農業大学卒業。テレビディレクターとして北極やアフリカなどを取材。「生きもの地球紀行」「地球!ふしぎ大自然」などのNHKの自然番組を数多く制作する。2005年からフリーランスとなり、書籍の執筆や監修、講演などをおこなっている。主な著書・執筆に『講談社の動く図鑑MOVE 鳥』(講談社)、『日本鳥類図譜』(山と溪谷社)、『カラスの常識』(子どもの未来社)など。日本鳥学会会員、都市鳥研究会幹事。
となりのハト 身近な生きものの知られざる世界
ハトの世に知られていない豆知識がたくさんつまった、身近な生きものの世界を見る目が変わる一冊! 馬鹿っぽい、汚い、何考えているのかわからない……など、マイナスイメージも多く、時には害鳥として駆除もされる身近な鳥、ハト。 そんなハトには、知られざる驚きの能力と、人との深いつながりがあった。 本書より一部を抜粋して掲載します。
こちらの連載もおすすめ
編集部おすすめ記事

- 道具・装備
- はじめての登山装備
【初心者向け】チェーンスパイクの基礎知識。軽アイゼンとの違いは? 雪山にはどこまで使える?

- 道具・装備
「ただのインナーとは違う」圧倒的な温かさと品質! 冬の低山・雪山で大活躍の最強ベースレイヤー13選

- コースガイド
- 下山メシのよろこび
丹沢・シダンゴ山でのんびり低山歩き。昭和レトロな食堂で「ザクッ、じゅわー」な定食を味わう

- コースガイド
- 読者レポート
初冬の高尾山を独り占め。のんびり低山ハイクを楽しむ

- その他
山仲間にグルメを贈ろう! 2025年のおすすめプレゼント&ギフト5選

- その他