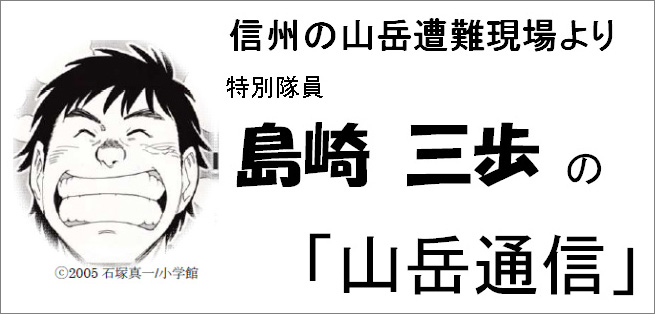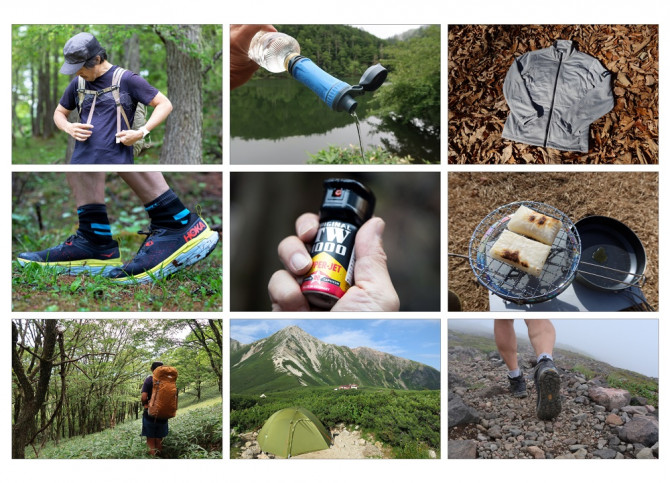道迷いからの滑落。重傷を負いながらも13日目に生還。当事者が6年ぶりに現場再訪
2016年10月大峰山系・弥山。ひとりで弥山に登った冨樫さんは、下山時に道に迷い、滑落して重傷を負う。その場で救助を待ったが、救助隊はやってこない。生きて帰るために男性が下した決断とは・・・。
文=羽根田治、写真=神谷年寿
その冨樫さんが現場を再訪したのは、2022年秋のことである。この日もあいにくの雨だったが、ナメリ坂を上がるころにはだいぶ小降りになっていた。頂仙(ちょうせん)岳の西側を巻くトラバース道に差し掛かったところで、冨樫さんには見覚えがある地形が現われた。そこは斜面が小さく崩壊して登山道が一部途切れている場所で、ここを越えて下山してきた記憶があった。迷ったのは、その先の、木々がまばらな広場のような場所だった。疑わしいのはナベの耳と、1598mピークの北側の鞍部の2カ所。この2つの場所をじっくり検証してみた結果、いちばん可能性が高そうなのが後者だった。

「明確に『ここです』とは言えませんが、このあたりだと思います。今は標識も赤テープもたくさんあるから、すぐに『こっちだな』とわかりますが、当時は目印がほとんどなかったから、どっちの方向に行っても正しいルートのような気がしたんです」
滑落した場所までは特定できなかったが、状況は鮮明に思い出せる。
滑落後、意識を取り戻して時間を見ようとしたら時計がなかったが、近くに落ちているのが見つかった。携行していた水を飲み干してしまい「これで命尽きたか」と観念したが、幸運にもそばに湧き水があった。
「それで私は神様から『生きろ』と言われたような気がしたんですね。『まだ子どもも小さいのだし、生きて帰って、子どもが大きくなるまで仕事をがんばれ』と」


体が動かせないので、じっと救助を待つしかないが、ガレ場でただ体を横たえていても、体中が痛くなるだけだった。なるべく体に負担がかからないようにしようと考え、体に当たる石をどけ、体がずり落ちないように木の枝で穴を掘り、穴から湧く水を吸わせるため枯れ葉を集めて下に敷くなどした。その作業で1日4、5時間は時間を潰せた。
また、いつも山に持ち歩いていた測量野帳に、事故の経緯と心情、反省点、生還してからのことなど、ボールペンのインクがなくなるまで書き綴った。
「肋骨が折れているから呼吸も非常に苦しかったし、背骨も折れていたのでかなりの激痛がありました。とにかく黙っていても辛いし、寝ていても辛い。その辛さを忘れるためにも、なにかをしていたかったんです」

今回、現場で事故を振り返ってみて冨樫さんが感じたのは、目印が見つからなかったとき、なぜすぐに最後に確認した目印まで引き返さなかったのか、ということだ。
「あのとき、引き返さずに次の目印を探し回ってしまったから、13日間、山の中で過ごすハメになりました。無理せずに引き返せば1日の遅れで済んだんです。それに尽きます」
冨樫さんにとって今回の現場検証は6年ぶりの登山で、「やっぱり山っていいな」と実感したという。今は、もう一度しっかり体を鍛え直して、また山に登りたいと思っている。
(『山と溪谷』2023年3月号より転載)
「山と溪谷ch.」で関連動画を配信中!
事故現場を再訪して検証したときの動画は、こちらでチェックできる。冨樫さんが事故当時を振り返りながら、当時の心境を語っている。
プロフィール

羽根田 治(はねだ・おさむ)
1961年、さいたま市出身、那須塩原市在住。フリーライター。山岳遭難や登山技術に関する記事を、山岳雑誌や書籍などで発表する一方、沖縄、自然、人物などをテーマに執筆を続けている。主な著書にドキュメント遭難シリーズ、『ロープワーク・ハンドブック』『野外毒本』『パイヌカジ 小さな鳩間島の豊かな暮らし』『トムラウシ山遭難はなぜ起きたのか』(共著)『人を襲うクマ 遭遇事例とその生態』『十大事故から読み解く 山岳遭難の傷痕』などがある。近著に『山はおそろしい 必ず生きて帰る! 事故から学ぶ山岳遭難』(幻冬舎新書)、『山のリスクとどう向き合うか 山岳遭難の「今」と対処の仕方』(平凡社新書)、『これで死ぬ』(山と溪谷社)など。2013年より長野県の山岳遭難防止アドバイザーを務め、講演活動も行なっている。日本山岳会会員。
関連記事
こちらの連載もおすすめ
編集部おすすめ記事

- 道具・装備
- はじめての登山装備
【初心者向け】チェーンスパイクの基礎知識。軽アイゼンとの違いは? 雪山にはどこまで使える?

- 道具・装備
「ただのインナーとは違う」圧倒的な温かさと品質! 冬の低山・雪山で大活躍の最強ベースレイヤー13選

- コースガイド
- 下山メシのよろこび
丹沢・シダンゴ山でのんびり低山歩き。昭和レトロな食堂で「ザクッ、じゅわー」な定食を味わう

- コースガイド
- 読者レポート
初冬の高尾山を独り占め。のんびり低山ハイクを楽しむ

- その他
山仲間にグルメを贈ろう! 2025年のおすすめプレゼント&ギフト5選

- その他