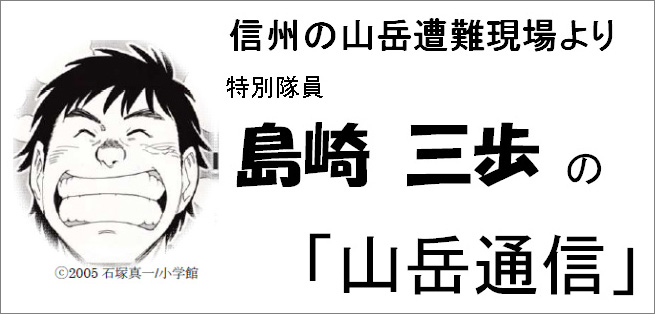グランドジョラス北壁の夏と冬。1年5ヶ月にわたるヨーロッパアルプス登山の集大成【凪の人 山野井妙子②】
ヨーロッパアルプスやヒマラヤなどで数々の登攀を成功した山野井妙子(やまのい・たえこ)は、世界的なクライマーとして頭角を現わす。しかし、その道は平坦ではなく、マカルーとギャチュン・カンの登攀では両手足の指の多くを失う壮絶な経験をする。彼女の記録的な登攀の裏にある、穏やかで動じない「凪」のような心のありようと、その人生の軌跡――。妙子の半生を追った書籍『凪の人 山野井妙子』より、シャモニーに長期滞在しながら夏と冬のグランドジョラス北壁に挑んだ箇所を抜粋して紹介しよう。
文=柏 澄子
夏のグランド・ジョラス北壁
1981年8月6日、妙子は笠松美和子とともにシャモニーのアパートを発ち、グランド・ジョラス北壁を目指した。14時にロープを結び登攀が始まる。すぐに小雨が降り始め、どうしたものかとふたりは顔を見合わせるが、一時的なものだろうと判断し登攀を継続した。当時、妙子たちはシャモニーガイド組合の事務所に毎日貼り出される天気予報を見に行って、情報を入手していた。むろん、グランド・ジョラスに向かう前も日々、ここの天気予報をチェックしていた。事務所はシャモニーの町の中心部にある教会のすぐ隣にあるが、妙子たちの時代から40年以上経ったいまでも、変わらずここには毎日天気予報や山の情報が貼り出されている。
雨はなかなかやまず、笠松は「まるで滝登りだ、たまらない」と、『岳人』(1982年2月号)に書いている。妙子は、雨で水分を含んだスリングを絞りながら回収していたほどだ。やがて雨はやみ、夕暮れが迫るなか登り続ける。22時、雪の詰まったテラスでビバークの準備に入った。笠松の記事には、「ピッケルを振るい、雪を踏み固め、ツェルトをセットした。ゆったりと腰をおろせるいい場所だ。食糧は少ないが、それで充分だ。鍋の雪と一緒に緊張もとけてゆく。空には星が出ている」とあり、荒天のなかの登攀を終え、リラックスした様子が伝わってくる。
翌朝、一杯のスープを口にしたのち、7時に登攀開始。ここからは乾いた岩壁が続く。ふたりとも、登山靴からクライミングシューズに履き替える。昨シーズンまでセカイチョーという名の運動靴で登っていた妙子も、パラゴというラバーソールのクライミングシューズを入手していた。
この日は天気がよく青空が広がっていた。周辺のルートでは落石が頻発しているのを目にした。下を見ると人影があり、この日に取り付いた知人のパーティかなと、ふたりは思っていた。妙子たちから1日遅れで日本人の2パーティがウォーカー稜に取り付いていた。ひとつはふたりもよく知る星野と小林要。彼らは前日にレショ小屋でもうひとつのパーティの4人と一緒だった。
小林たちが先行し、4人パーティもすぐ続いていた。小林によると、リードする星野から「ラク」と大声が聞こえ、見上げると大量の落石の隙間から空がのぞいているほどの岩雪崩だった。小林は目の前の残置ハーケンにアブミをかけてしがみつき、落石をやり過ごした。落石が収まり、小林も星野も無事でほっとしていると、下のパーティから「助けてくれ」とコールがあり、急ぎ下降した。後発の彼らのもとにたどり着いた小林と星野は救助にあたったが、結果、4人のうち2人が死亡し、残りの2人はケガを負った。不幸な事故であったが、グランド・ジョラス北壁は、実力相応のクライマーがトライしても、コンディション次第では登れないこともある。この年に完登した日本人は、妙子たちだけだった。
こんなことが起きているとは妙子も笠松もつゆ知らず、登り続けていた。やがて三角雪田を抜けると、先行していたフランス人の2人組に追いつき、ここから先はふたりを追う形になった。ウォーカー稜は岩のセクションのほかに雪壁があったり、ときには岩にベルグラ(薄氷)が張っていたり、クライマーには総合的な力が求められる。シャモニーで経験を積んできた妙子にとっては、それがおもしろかった。
16時、雪をたっぷりと戴いたウォーカー峰に登頂。少し休んだのちに、イタリア側へ下った。懸垂下降を繰り返し氷河に降り立ったところで、雹が降り始める。ツェルトをかぶって様子を見たが、やがて雪に変わり濃霧に包まれた。結局、そこで一晩を越すことになった。
8月8日、快晴。麓のボカラーテ小屋に向かってふたりは下った。笠松は疲れて膝も痛んできたが、妙子はいたって元気だった。笠松は「アルム地帯に出た時はすごい解放感を感じた。フェレの谷への下りは何とも美しく、見るものすべてが眼にしみる思いで降りて行った。長尾(妙子)もきっとそうだったにちがいない」と書いている。ふたりの心は満たされていた。
さて、下山したふたりは、国境となるモンブラントンネルを抜けてシャモニーに帰らなければならない。そんなときの手立てはヒッチハイクだ。妙子と笠松はふたりで何度もヒッチハイクをしているので、いつのことか記憶は定かでない。ともあれ、乗れそうな車が走ってくると面長で美人顔の笠松を前に出してヒッチハイクを試みたり、あるときはそれぞれ別々に見つけたりした。妙子がヒッチハイクした車に乗って走っていると、その脇をバイクの後部座席にまたがった笠松が追い抜いていったこともあった。のどかで、のびのびと旅ができた時代だった。
夏から秋、冬へ
夏の盛りが過ぎると、日本人クライマーの多くは帰国の途につき、シャモニーは静かになる。妙子はウォーカー稜ののち、笠松とプチト・ジョラス西壁コンタミヌルートを登攀。山崎祐和とはプチト・ジョラス西壁の左端辺りに新ルートを開拓した。これを山崎は「エプロンノールウエスト(北西側稜)」と名付け、地元のガイドブック『ギド・バロー』に発表した。このルートはナチュラルプロテクションを使いながらフリーで登る岩のルートであったが、妙子はナッツの使い方に慣れていなかったからか、振り返るとセットしたはずのナッツがすべて外れて、ビレイをする山崎の手元にたまってしまうこともあった。妙子はこのときのことを、「岩の内容も充分満足できたし、自分がルートを選んでいく楽しさを味わった。日本でもルート開拓の経験はあるが、あまりにもスケールが違いすぎる。はるかに内容の大きなものばかりだった」というような内容を、のちに大蔵喜福から受けたインタビューで答え、『岳人』(1994年12月号)に掲載されている。
秋になるとクライマーたちは旅に出たり、アルバイトに精を出す。パリのレストランで働く者、南フランスでワイン用のブドウの収穫にいそしむ者などがいるが、妙子は友人とふたりでヒッチハイクをしながらローマへ遊びに行った。このころは妙子たちに限らず、旅に出る者のほとんどがヒッチハイクを利用し、シャモニーに戻ると、互いのヒッチハイクの武勇伝を話して楽しんだ。
妙子がのんびり旅に出たのにはわけがある。鈴木惠滋に「冬に一緒に登ろう」と誘われていたからだ。惠滋は家族と一緒に長期間シャモニーに滞在して登り続けており、1979年にはドロワット北壁の冬季単独初登攀を成し遂げていた。ドロワット北壁はシャモニーのなかでも最難のルートのひとつだった。妙子は惠滋に誘われたことがうれしく、彼のこの一言で、滞在を延ばすことを決めたのだ。
手元にあった成田行きの航空券をキャンセルするために、帰国するクライマーに託し、日本の旅行会社に持って帰ってもらった。いくばくかの返金があり、それをシャモニーに届けてくれたのは別のクライマーだった。冬の滞在資金の足しになった。いまであればオンライン上で簡単にキャンセルできるけれど、当時インターネットは普及前だった。チケットも払戻金も、運ぶのは人間だった。
惠滋との最初の1本はグランド・ジョラス北壁ウォーカー稜に決まった。夏に妙子が登っているからという理由もあった。
そのためクリスマスのころになると、スキーの経験がほとんどなかった妙子は、惠滋から特訓を受けた。グランド・ジョラス北壁の取付まではスキーを使うからだ。行きはシールを貼ったスキー板で、取付まで続く氷河を登る。登攀後は、取付にデポしたスキーを回収しなければならない。そして回収後は、山麓まで滑って降りることになる。スキーの技術は、冬のグランド・ジョラスには必須だった。短期間だったけれど特訓の成果があり、妙子は急斜面であろうが滑り降りることができるようになった。とはいっても、きれいなターンを描くというよりは、持ち前の脚力で板を押さえながら直滑降気味に滑っていたのだが。
厳冬のシャモニー
冬のグランド・ジョラス北壁の記録は、多くはない。
日本人が初めて成功したのは、1971年元日。11日間奮闘したのは、山学同志会のメンバーと植村直己の6人、日本のトップをゆく猛者たちだった。隊長は小西政継であり、1967年にマッターホルン北壁冬季第3登を成し遂げており、のちにネパールのジャヌー北壁を初登攀する実力者だ。植村直己は、前年に日本人初のエベレスト登頂者になっていた。彼らはアプローチのレショ氷河やイタリア側の下山路を入念に偵察し挑んだ。6人がそれぞれ力を発揮したが、全員が凍傷を負い、4人が手足の指を切断する結果になった。妙子たちが登る約10年前のこと。当時は時の流れがゆっくりで、いまの10年とは異なるため、氷河やルートの状況は、ほぼ同じようなものだっただろう。装備やウェアに少々の進化はあっただろうが、そう大きくは変わらない。
それを考えると、この後語る妙子と惠滋の冬季グランド・ジョラス北壁が、いかに困難ななかやり遂げたレベルの高い登攀だったかわかるように思う。
年が明け、いよいよ惠滋とふたりでグランド・ジョラス北壁に向かう日がやってきた。
1982年1月18日、友人のサポートを受けてウォーカー稜の取付に程近いレショ小屋に入った。翌日より登攀を開始し、登頂したのは25日。山学同志会ほどではなかったが、それでも長い日数がかかった。途中までツルベで(ロープのトップを順次交代しながら)登っていたが、終盤は惠滋が手に凍傷を負ったため、妙子がリードし続けた。妙子は登る前は、夏の経験があるからルートはわかると考えていたが、大違いだった。岩は雪の下に隠れ、残置ハーケンも埋もれてしまっていた。傾斜の緩い箇所はなおさらだ。それらひとつひとつを掘り起こし、雪を落としながら登っていくのに時間を要した。天候は荒れ、予想よりも日数がかかり、ふたりで少しの食料を分け合いながら食いつないだ。

26日、イタリア側のノーマルルートを下降し、夕方にはシャモニーに戻った。ふたりが惠滋のアパートに到着すると、妻の節子がミートソースを作って待っていた。お腹を空かせているからさぞ食べるだろうと思ったが、その量たるや節子の想像をはるかに超えていた。ふたりともそれぞれ6皿をペロリと平らげた。節子は合計2kgのパスタを茹でた。
細身の惠滋は、痩せてあばら骨が浮き上がっていた。58kgあった体重が53kgになっていたのだ。一方の妙子は72kgの体重になんの変動もなかった。ふたりの違いはどこにあったのか。妙子が振り返るには「私はいつでもどこでもよく眠れる。お尻がひっかかる程度の狭いビバークポイントもあったし、吹雪いた夜もあった。それでも毎晩ぐっすり眠れた。惠滋さんは経験がある分、先々のことに気をまわし、あまり眠れなかったのかもしれない。違いはそこだけ。それが体重減につながったのかもしれない」と言う。
妙子は、冬季のグランド・ジョラス北壁を登った初めての女性になった。
妙子と惠滋の縁はその後も長く続くが、惠滋は2020年に病死。いまとなっては惠滋に聞きたくても聞けないことがある。
惠滋はそれまでにも、数々の困難な登攀を成し遂げてきた実力者だった。当時、シャモニーには妙子よりも強くて経験のあるクライマーもいただろうし、惠滋と登りたい人も多かっただろう。けれど惠滋は、妙子を厳冬の登攀に誘った。当時の妙子の手帳を読むに、それ以前にふたりが一緒に登った記録はない。
なぜ、妙子をパートナーに誘ったのか。一緒に登らなくとも、長いことシャモニーという小さな町でそれぞれが暮らして登っていれば、その記録から互いの実力がわかるのかもしれない。また、惠滋は妙子の人柄はよく知っていただろう。どんなときもイライラすることはなく、根気強い。気分にむらがなく穏やかである。そんな妙子とであれば、冬の厳しい天候のなかでどんな困難にあっても、粘り強く登って還ってくることができると思ったのだろうか。長く厳しい登攀であればあるほど、クライミングの実力以上にパートナーの性格や性質が重要になる。惠滋は妙子を信頼していたに違いない。
グランド・ジョラス北壁を終えたふたりは、日本からやってきた木村辰夫と3人で次なるルートに向かった。木村もまた、何年もシャモニーに通っているクライマーである。町のはずれにあるガイアンの岩場側に、日本人クライマーたちが集まって、暮らす家があった。通称「踏切小屋」。踏切の近くにあったため、その名がついた。木村は踏切小屋の主のように暮らし、いく年もヨーロッパアルプスを登っていた。
3人が向かったのはモンブランのプトレイ山稜にあるボナッティ・ゴビルート。「レビュファ100選」には載っていないが、100番目に近い困難なルートだと思われる。ボナッティ・ゴビルートは岩壁から始まり、それを抜けたあとモンブランの山頂に至るセクションが氷雪壁や雪稜になる。
2月11日、惠滋と妙子はスキーを使い、木村は徒歩でギグリオーネ小屋に入った。翌日、ボナッティ・ゴビルートに取り付く。それから10日間かけて登攀を終え、下山したのは2月20日だった。
グランド・ジョラス北壁よりも長くなった。壁のなかで4日間の降雪に苦労し、さらに2度ルートを間違え、日数がかさんでしまった。妙子はいま振り返っても、「スマートではなかった。どんくさかったね」と言うが、厳冬のヨーロッパアルプスで奮闘した結果だ。
最後の山頂へ向かう雪稜と、ノーマルルートを下るあたりは、うんざりするほど長かった。疲れから集中力が途切れたのか、妙子は山頂に向かう途中で滑落する。約40m、ロープがいっぱいに伸びて止まった。3人でロープを結びコンテニュアスで登っていたときであり、トップの惠滋が止めた。中間にいた木村は妙子の滑落によって飛ばされ、頭から雪壁に突っ込んだが無事だった。妙子は流される間、「もう駄目かもしれない。私のためにふたりを引きずり込んでしまうのか」と考えた。けれど、流されている間も惠滋のビレイで止まったときも、心臓がバクバクして混乱するようなことはなかった。止まったあと、すっくと立ち上がって惠滋たちがいるほうを見上げ、そのまま登り返した。その淡々としたさまが、妙子らしい。
山頂を越えてやっとたどり着いたバロの避難小屋では、腹を空かせた3人は登山者が残したゴミの山をあさった。チョコレート、ビスケット、チューブ入りのコンデンスミルク、どれも他人の食べ残しだが、お腹を落ち着かせることができた。
その後、グーテ小屋にたどり着いたとき、やっと登攀具を解き、少しの解放感にひたる。しかし、先はまだまだ長い。ガスで何も見えず、やっとのことでシャモニー谷に降り立った。
妙子と惠滋、木村の3人で成し遂げたこの登攀は、ボナッティ・ゴビルートの冬季第2登となった。
その後、妙子と惠滋はもう一度プトレイ大岩稜の別のルートを登り、フレネイへ継続したいと準備を始めた。10年もヨーロッパアルプスになじんできた惠滋が胸に温めてきた計画だ。妙子は、惠滋はこれでヨーロッパアルプスにピリオドを打とうとしているのではないかと想像した。けれど好天は巡ってこず、実行することができなかった。プトレイ大岩稜からフレネイへの継続は以前、山学同志会によって試みられたが失敗に終わったルートである。この冬、イタリア人のソロクライマーが20日間かけて4本のルートを登り、フレネイまでの継続に成功した。妙子は、その登攀に感嘆した。
岩登りを始めて5年。ヨーロッパアルプスは3シーズン目。妙子は夏と冬のウォーカー稜とボナッティ・ゴビルートを登った。すばらしい成果ではないか。しかし、当時の妙子は冷静に自分を分析し、『岳人』(1982年8月号)に文章を残している。要約するとこんな内容だ。
「冬の登攀などまったく考えていなかった自分を、惠滋さんが誘ってくれたからこそ、グランド・ジョラス北壁とボナッティ・ゴビルートというふたつの山行が実現した。準備や装備のこと、とくにスキーについては何もわからず、惠滋さんに頼りっぱなしだった。ツルベで登り、等分した荷物を背負ったけれど、それは全体の何分の一かの重要性しかない。計画したのは惠滋さんであり、それこそが重要なことだ。自分は壁の中でも何も心配せず、ただ上に登っていくことのみ考えていた」
それでも、妙子にはやれることをやり切った充溢感があった。妙子なりにシンプルに少人数で登った。この先ヨーロッパアルプスを離れて、別の魅力ある山を目指すときも、妙子は今回のようになるべくシンプルで少人数のスタイルで登るだろうし、そのときには今回のシャモニーでの経験を充分に活かせるだろうと思った。
(『凪の人 山野井妙子』より抜粋)

山野井妙子(やまのい・たえこ)
1956年、滋賀県生まれ。77年、東京北稜山岳会入会。82年、冬季グランド・ジョラス北壁登攀。91年、ブロード・ピーク、マカルー登頂。94年、チョ・オユー南西壁スイス・ポーランドルート第2登。96年、山野井泰史と結婚。2002年、ギャチュン・カン北壁登攀。これにより植村直己冒険賞受賞。07年、グリーンランドのミルネ島「オルカ」初登。20年、静岡県伊東市に移住。

凪の人 山野井妙子
| 著 | 柏 澄子 |
|---|---|
| 発行 | 山と溪谷社 |
| 価格 | 1,980円(税込) |
プロフィール

柏 澄子(かしわ・すみこ)
登山全般、世界各地の山岳地域のことをテーマにしたフリーランスライター。クライマーなど人物インタビューや野外医療、登山医学に関する記事を多数執筆。著書に『彼女たちの山』(山と溪谷社)。
(公社)日本山岳ガイド協会認定登山ガイド。
(写真=渡辺洋一)
関連記事
こちらの連載もおすすめ
編集部おすすめ記事

- 道具・装備
- はじめての登山装備
【初心者向け】チェーンスパイクの基礎知識。軽アイゼンとの違いは? 雪山にはどこまで使える?

- 道具・装備
「ただのインナーとは違う」圧倒的な温かさと品質! 冬の低山・雪山で大活躍の最強ベースレイヤー13選

- コースガイド
- 下山メシのよろこび
丹沢・シダンゴ山でのんびり低山歩き。昭和レトロな食堂で「ザクッ、じゅわー」な定食を味わう

- コースガイド
- 読者レポート
初冬の高尾山を独り占め。のんびり低山ハイクを楽しむ

- その他
山仲間にグルメを贈ろう! 2025年のおすすめプレゼント&ギフト5選

- その他