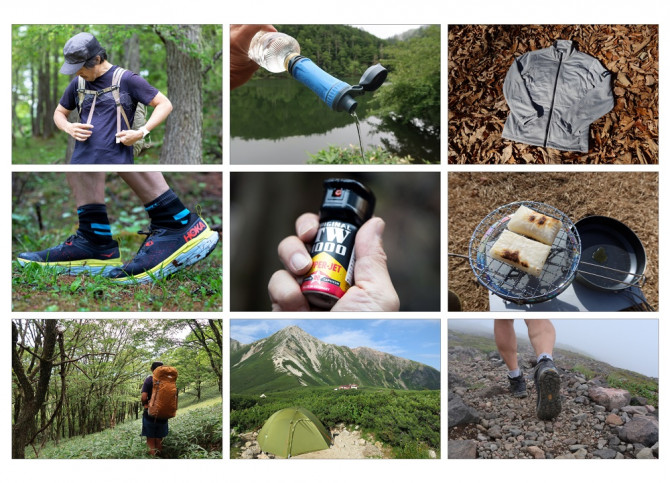社会から「裏切り者」がなくならない根本理由とは?――進化生物学者が教えてくれること
コロニーと呼ばれる集団をつくり階層社会を営む「真社会性生物」の驚きの生態を、進化生物 学者がヒトの社会にたとえながらわかりやすく語った名著『働かないアリに意義がある』がヤマケイ文庫で復刊! 働かないアリが存在するのはなぜなのか? ムシの社会で行われる協力 、裏切り、出し抜き、悲喜こもごも――面白く、味わい深い「ムシの生きざま」を紹介する。

完全な個体、不完全な群体
われわれは自者・他者それぞれを別々の生き物だと認識しており、それを名指して「個体」という言葉があります。僕と君は別の人(個体)と言えば、誰もなんの疑問ももたないでしょう。
そもそも「我」とは他とは異なる「この私」を指す言葉で、自分が他人と別の個体であることに疑問を抱く人はめったにいません。
ところが、われわれヒトを含む多くの生き物は、たくさんの細胞が集まってできている多細胞生物です。細胞の一つひとつはそれぞれがゲノムDNAをもっており、細胞分裂で自分のコピーを増やしていきます。
これはどこかで見た構図です。そう、同種の集団内でそれぞれの個体が自分の子どもを生んで増やしていくのと似ていますね。
こういう構図のもとでは、遺伝的なラインのあいだの増殖率の違いにより、競争に勝つ特定のラインが増えていくことも、それを「進化」と呼ぶことも、ご承知のとおりです。
では、個体をつくる多数の細胞のあいだでそういう競争は起こらないのでしょうか?なぜ、複数の細胞は様々な器官に分かれ、統合された個体という「完全な社会」として振る舞えるのでしょうか。
秘密は2つあると考えられます。
1つは、われわれをつくる細胞が、最初はたった1つの受精卵から分かれて増えたものだということです。細胞は分裂するときに自分の核ゲノムDNAをコピーして2倍にし、分かれて2つになる細胞のそれぞれに渡します。
ですから、基本的に1つの受精卵から分かれて増えたすべての細胞は遺伝的に同じ(血縁度1)なのです。ということは、相手が子ども細胞を残すとそこには自分と同じ遺伝子のコピーが必ず含まれるということです。
相手との血縁度が高ければ高いほど包括適応度が高くなりやすく、協同が進化しやすくなります。多細胞生物では、腕や脳など様々な器官に分化して協同し、個体を形づくっていますが、それらはみな一つの細胞のコピーなので、実はどの細胞が子どもを残そうが同じことなのです。
つまり、個体内の進化は遺伝的に「完全」ということです。すべての細胞が遺伝的に同じなら、細胞のあいだで、誰が次の世代に遺伝子を伝えるかという競争は原理的に無意味です。
もう1つの秘密は、多細胞生物では多数の細胞が協同していますが、次の世代に遺伝子を残せる器官はたった1つしかないということです。いうまでもなく卵巣または精巣です。
そこでつくられた卵子及び精子のみが次世代の子どもをつくるときに使われ、その他のすべての器官は子どもに自分のコピーを伝えることができません。これはあまり注目されていませんが、実はおおいに意味のあることです。
多細胞生物の細胞は遺伝的に同一だといいましたが、DNAのコピーは完全に正確に行われるわけではないので、厳密には体の各部分の細胞はきわめて高い血縁度をもつ一方、塩基配列が異なっている可能性もあります。
「他人同士」だとすると、それらの遺伝的ラインのあいだに主導権を巡る競争が起こるはずですが、卵巣、または精巣になった細胞以外は次世代に子どもを残せません。
ですからそれらの器官は、反乱して個体全体が残す子どもの数を減らしてしまうよりは、血縁度がきわめて高い生殖細胞系列が子どもを残すほうを選んで、血縁選択による適応度を高めるように進化したと考えられます。
もし、各器官がそれぞれ次世代に子どもを残すことができるとすれば、各器官のあいだで競争が起こり、器官の分業によって保たれている個体自身の高い機能性は失われます。その結果、すべての器官と細胞が所属しているその個体は、他の個体との競争に敗れて滅びてしまうでしょう。
多数の細胞が集まった個体を1つの「社会」と考えると、その進化と維持も血縁選択や群選択(群れをつくることで個体の適応度があがる)、長期的適応度の観点から解釈できるわけです。
「群れ」とは「全体がなんらかの意味をもつように相互作用する個体の集団」と定義すると、ここでいう「個体」も、細胞を単位とする群れとして同一の論理で解釈できます。そんなことする必要あるのか?と思われるかもしれませんが、科学とは、世の中の物事を単純な論理で説明していく活動なのです。
いまは言葉遊びと思われるような理論でも、将来的にこの理論を応用することで、人体の謎のいくつかが解ける可能性だってあるかもしれません。
群れとして解釈できるとはいっても、われわれが体感するように個体は社会よりも遺伝的に純化されており、より完全です。あるいは、そのような純化されたものしか多細胞の「個体」として分業することができなかったのかもしれません。
しかし、「完全な個体」にも反乱は起こります。人類がいまだに克服できないでいる「癌」がそれです。癌細胞は正常な細胞がなんらかの要因で変化した細胞で、個体に対する忠誠を失い、周りの器官から栄養を吸収して増え続ける裏切り者細胞です。
自分たちが増えることだけに専念し、個体の維持に協力しないので、そのままにしておくと個体は死に至ります。ちょうどアミメアリにいる、働かず、繁殖だけを行う遺伝的チーター(コロニー内の裏切り者)のようなものです。
アミメアリでこのチーターに寄生されたコロニーが早晩(そうばん)滅びてしまうのと同様、癌細胞も宿主を滅ぼします。そうすることで癌細胞自身も滅びますが、そういう場合でもチーターの進入を止めることができないのは、個体も社会である以上、どうしようもないことだといえるでしょう。
それでも、個体はまだましです。もともと1つの細胞から分かれて増えたものですから、細胞間の血縁度は1ではないにせよきわめて高いし、繁殖できる経路も厳しく制限されています。しかし、多数の個体が集まってできているヒトやムシの社会では、協同するうえでこれらの条件がはるかに厳しいことになっています。
血縁度は高くてもアリやハチで4分の3くらい、社会のほとんど全員が潜在的には繁殖可能です。場合によってはまったく血縁関係のない個体が協同していることすらあります。
かように社会という名の群体は「不完全」なため、裏切りが常に起こるのです。
動物の社会に共通しているのは、不完全な個体から完全な群体が進化したのではなく、完全な個体から不完全な群体が進化したという流れです。
社会性生物では、その不完全さゆえに生物学的に興味深い様々な現象が進化してきたといってもよいでしょう。完全で無味乾燥なものは面白くないのかもしれません。
※本記事は『働かないアリに意義がある』を一部掲載したものです。
『働かないアリに意義がある』
今の時代に1番読みたい科学書! 復刊文庫化。アリの驚くべき生態を、進化生物学者がヒトの社会にたとえながらわかりやすく、深く、面白く語る。
『働かないアリに意義がある』
著: 長谷川 英祐
発売日:2021年8月30日
価格:935円(税込)
【著者略歴】
長谷川 英祐(はせがわ・えいすけ)
進化生物学者。北海道大学大学院農学研究員准教授。動物生態学研究室所属。1961年生まれ。
大学時代から社会性昆虫を研究。卒業後、民間企業に5年間勤務したのち、東京都立大学大学院で生態学を学ぶ。
主な研究分野は社会性の進化や、集団を作る動物の行動など。
特に、働かないハタラキアリの研究は大きく注目を集めている。
『働かないアリに意義がある』(メディアファクトリー新書)は20万部超のベストセラーとなった。
働かないアリに意義がある
アリの巣を観察すると、いつも働いているアリがいる一方で、ほとんど働かないアリもいる。 働かないアリが存在するのはなぜなのか? ムシの社会で行われる協力、裏切り、出し抜き、悲喜こもごも――。 コロニーと呼ばれる集団をつくり階層社会を営む「真社会性生物」の驚くべき生態を、 進化生物学者がヒトの社会にたとえながらわかりやすく、深く、面白く語る。