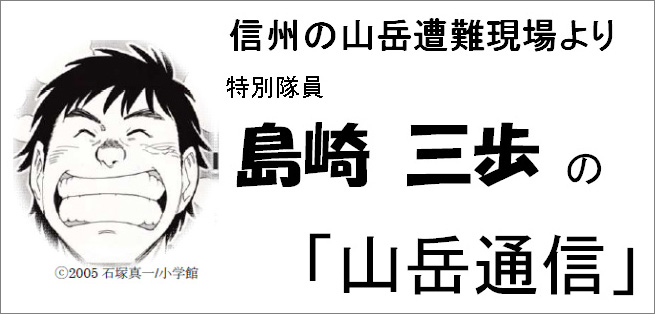【働かないアリに意義がある】めんどくさい人生を生きる価値とは?――進化生物学者が伝えたいこと
コロニーと呼ばれる集団をつくり階層社会を営む「真社会性生物」の驚きの生態を、進化生物 学者がヒトの社会にたとえながらわかりやすく語った名著『働かないアリに意義がある』がヤマケイ文庫で復刊! 働かないアリが存在するのはなぜなのか? ムシの社会で行われる協力 、裏切り、出し抜き、悲喜こもごも――面白く、味わい深い「ムシの生きざま」を紹介する。

自然選択説の限界
人間の社会には「働かざるもの食うべからず」という諺(ことわざ)があります。イソップ童話の「アリとキリギリス(もともとの話はキリギリスではなくセミだったともいいます)」では、アリが働いている夏のあいだ鳴き遊んでいたキリギリスが、冬になってアリに食べ物をねだると「夏は歌って暮らしたなら、冬は踊って暮らせ」と突き放されます。
これらの話は、勤労により社会の労働生産効率をあげることに貢献しない者は生きなくてよいという意味で、怠けている者を戒める話として使われています。
しかし『働かないアリに意義がある』(山と溪谷社)では、働かない働きアリをもつシステムは、短期的な労働効率は低くても長期的な存続率が高いため、長い時間で見ると生き残る、と言ってきました。
ここまで聞いて「何かおかしいぞ?」と思ったあなたは鋭い方です。
自然選択説の大原則は、「この世代」で「強いもの」が生き残るという思想です。いまこの世代における強弱のみが問題であり、短期的な効率が高いものが最後に残るはずだと言い換えることもできます。
ところが、働かない働きアリについては、短期的に高効率なシステムより低効率なものが残るという結論になっています。なぜこんなことになるのでしょうか? 「自然選択のもとでは適者生存」という鉄則自体が間違っているのでしょうか?
実はこの「適者」というのがくせ者です。ダーウィンの論理には、「何に対して適しているものが適者なのか」という定義がなされておらず、したがってどんな性質が進化してくるのかもこの論理だけでは決められないのです。
そこで進化論を支持する学者たちは「世代が重ならず(親と子の世代が共存しない)、世代間で個体数が変化せず、内部での交配は完全にランダムである」というきわめてシンプルな「定常個体群」という集団を想定し、そこで個体の適応度が異なると、適応度の高いものが最終的に残ることを計算によって示しました。それで現実の生物もすべて説明しようと考えたのです。
つまり、現在のほとんどの進化理論は、理想的な個体群においてのみ成立する考え方でしかないのです。この、理想状態での理論値と現実の生物が示す行動パターンが一致する例はたくさん報告されており、進化理論の正しさを示す証拠だとされていますし、確かにそうなのですが、問題はあります。
研究という活動は、理論と一致した結果だと公表されやすく、理論と一致しない結果は公表されずに終わる可能性が高いものです。つまり公表された例だけを目にしていることを考えると、現実が理論と一致する場合は「ある」とはいえるものの、本当に「多い」とはいえないかもしれないのです。
また、現実に生物が生きる環境は理想状態とはほど遠く、学者が設定した定常個体群のありようとは遠い隔たりがある場合もたくさんあります。ヒトを含む多くの生物では複数の世代が共存し、最近の日本の超高齢化社会の進行からもわかるように、世代ごとの個体数は常に変動しています。また、個体は自分が見つけられる範囲にいる個体としか交配できません。
このような変動要因まで考慮したときにどのような進化が起こるのかは、実はまだほとんど研究も理解もされていないのです。
適応度に基づく進化の考えにはもう一つ大きな問題があります。適応度は未来における値なので、測定する未来をどの時点に置くかで値が違ってくる可能性があるのです。通常は「次世代」または「孫の世代」での適応度を進化の指標にしますが、次世代で適応度が高い「ある性質」も、何百世代もの未来で考えると、次世代で低い適応度しか示せない性質より適応度は低いのかもしれません。
言い換えれば「ある生物がどのくらい未来の適応度に反応して進化しているのかはまったくわかっていない」のです。
もしかすると、次世代の適応度に反応する遺伝子型と、遠い未来の適応度に反応する遺伝子型がいまこの瞬間も、私たちの体内で競争しているのかもしれません。しかし、理論上にせよ、そんなことが検討されたことはいままでないのです。
神への長い道
これら自然選択説の盲点を考え合わせると、働かない働きアリの存在も、あながち進化の原則と矛盾していないと思えます。彼らには直近の未来の効率ではなく、遠い未来の存続可能性に反応した進化が起こっている、と私自身は考えています。
みながいっせいに働くシステムは直近の効率が高くても、未来の適応度は低いのです。
ところが、このような問題はごく最近の研究によってやっと扱われ始めたばかりですし、適応度の時間軸のスパンを変化させる理論で現実の生物がどれだけ説明できるのかもまだほとんど不明です。
科学は理論的に簡素で明解に説明できることを重んじますが、説明原理(この場合は適応度に基づく進化)にどのような理論的制約があるのかを忘れると、ただの机上の空論になってしまいます。
生物学は現実の生物が「なぜ(Why)」そして「どのように(How)」進化してきたのかを明らかにする学問ですから、理論的に美しいことよりも、現実の生物をうまく説明できるという価値観を大切にしなければなりません。私たちはそういう視点を忘れずにこれからも研究を進めていきたいと思っています。
進化は、永遠に終わることのない過程ですが、もしも「完全な適応」が生じれば進化は終わります。私は講義のなかで学生に「すべての環境で万能の生物がいれば、進化は終わるのか?」という問いを必ず投げかけます。全能の生物がもしいれば、どのような環境でも競争に勝てるため、世界にはその生物しかいなくなるからです。
進化とはそんな、存在しない「神」を目指す長い道行きだともいえるでしょう。と同時に、なぜそのような生物が存在しないのか、理由を考えることも、生物を理解するうえでは大切な姿勢だといえるでしょう。
いつも永遠の夏じゃなく
大学の一教員である私は、かつて学生にある質問をされて「それはこういう意味だ」と説明しました。彼は納得して帰ったのに、後で「先生の言ったことは教科書に載っていません」と言ってきました。
私はそのとき「君は自分の頭で納得したことより、教科書に書いてあるかどうかを正しいかどうかの基準にするのか? 科学者は、正しいと思ったことは世界中のすべての人が〝それは違う〟と言ったとしても〝こういう理由であなた方のほうが間違っている〟と言わなければならない存在なのに?」と怒りました。
多くの研究者(プロを含む)は、教科書を読むときに「何が書いてあるかを理解すること」ばかりに熱心で、「そこには何が書かれていないか」を読み取ろうとはしません。学者の仕事は「まだ誰も知らない現象やその説明理論を見つけること」なのにです。
優等生とは困ったものだと「変人」である私は思います。私はこれからも変人として、私たちの研究がそのような新たな科学の発展に役立つ一例となるよう、やっていきたいと思うのです。
生物の世界はいつも永遠の夏じゃなく、嵐や雪や大風の日など予測不可能な変動環境であることが当たり前です。「予測不可能」とは「規則性がない」ということですから、実は数式で表されるものしか理解できない理論体系が、最も苦手とする分野が「生物学」なのかもしれません。
生物の進化や生態の研究には、まだまだ何が出てくるかわからない驚きが残っていると私は思いますし、驚きがないのなら、そんな研究はもうやめたほうがましだと思います。人生もそうかもしれませんが、いつも永遠の夏じゃないからこそ、短期的な損得じゃない幸せがあると思うからこそ、面倒臭い人生を生きる価値がある、とは思いませんか?
※本記事は『働かないアリに意義がある』(山と溪谷社)を一部掲載したものです。
『働かないアリに意義がある』
今の時代に1番読みたい科学書! 復刊文庫化。アリの驚くべき生態を、進化生物学者がヒトの社会にたとえながらわかりやすく、深く、面白く語る。
『働かないアリに意義がある』
著: 長谷川 英祐
発売日:2021年8月30日
価格:935円(税込)
【著者略歴】
長谷川 英祐(はせがわ・えいすけ)
進化生物学者。北海道大学大学院農学研究員准教授。動物生態学研究室所属。1961年生まれ。
大学時代から社会性昆虫を研究。卒業後、民間企業に5年間勤務したのち、東京都立大学大学院で生態学を学ぶ。
主な研究分野は社会性の進化や、集団を作る動物の行動など。
特に、働かないハタラキアリの研究は大きく注目を集めている。
『働かないアリに意義がある』(メディアファクトリー新書)は20万部超のベストセラーとなった。
働かないアリに意義がある
アリの巣を観察すると、いつも働いているアリがいる一方で、ほとんど働かないアリもいる。 働かないアリが存在するのはなぜなのか? ムシの社会で行われる協力、裏切り、出し抜き、悲喜こもごも――。 コロニーと呼ばれる集団をつくり階層社会を営む「真社会性生物」の驚くべき生態を、 進化生物学者がヒトの社会にたとえながらわかりやすく、深く、面白く語る。
こちらの連載もおすすめ
編集部おすすめ記事

- 道具・装備
- はじめての登山装備
【初心者向け】チェーンスパイクの基礎知識。軽アイゼンとの違いは? 雪山にはどこまで使える?

- 道具・装備
「ただのインナーとは違う」圧倒的な温かさと品質! 冬の低山・雪山で大活躍の最強ベースレイヤー13選

- コースガイド
- 下山メシのよろこび
丹沢・シダンゴ山でのんびり低山歩き。昭和レトロな食堂で「ザクッ、じゅわー」な定食を味わう

- コースガイド
- 読者レポート
初冬の高尾山を独り占め。のんびり低山ハイクを楽しむ

- その他
山仲間にグルメを贈ろう! 2025年のおすすめプレゼント&ギフト5選

- その他