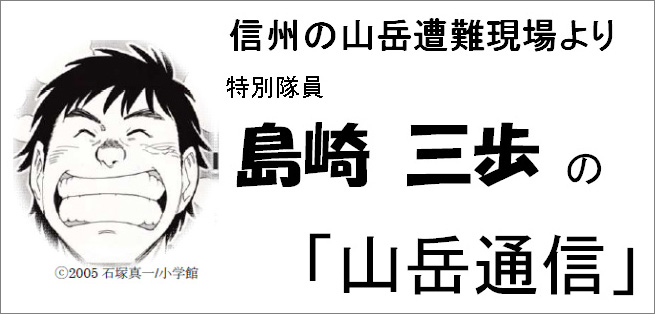【きのこ殺人事件】ローマ皇帝の暗殺にも使われた「猛毒きのこ」の正体とは?
「世界中の誰よりもきのこに詳しかった"きのこ博士“の名著」藤井一至氏(土の研究者)推薦!
「地上に平和をもたらしたのは、きのこだったのだ」小倉ヒラク氏(発酵デザイナー)推薦!
きのこ学の第一人者、故・小川真氏がのこした名著『きのこの自然誌』。世界中のきのこを取り上げながら、きのこの不思議な生き方やきのこと人との悲喜こもごもについて語る「魅惑のきのこエッセイ」です。文庫化を記念して、本書からおすすめの話をご紹介していきます。第2回は、きのこの毒にまつわるちょっと怖いお話。

きのこ殺人事件
子どもがうす紅色のかわいらしいドクベニタケにそっと手をのばすと、「汚い。毒だからさわっちゃだめ」と大声がとんでくる。手にとろうものなら、「死んでしまうよ」とくる。子どもはかわいそうにぶるっとふるえて、この瞬間からきのこ嫌いになってしまう。ヘビ、トカゲ、毛虫にきのこはいずれ劣らぬ人間の敵と思いこまされる。
もっとも、これほどまで嫌われるのにはそれなりの理由がある。たべて命を落とすほどのきのこの種類はわずかなものだが、その死にざまは毒ヘビにかまれたときのように悲惨である。まして、おいしいと思ってたべたその後でやられるのだから、だましうちにあったようで、食い物のうらみはいっそう大きくなる。
世界のいたる所で、これほどまでに恐怖が広がっている食べ物も珍しい。人類の歴史始まって以来、どれほど多くの人が毒きのこにあたり、命を落としたことか。
年に一度か、ものによってはめったに手にはいらないきのこをたべるのにはかなりの勇気がいる。しかし、年がら年じゅう飢えに苦しめられていた大昔の人にとって、軟らかな口あたりのよいきのこは大切な食糧で、危ないとは知りながら背に腹はかえられず、つい口にしたことだろう。
涼しい夏や秋の長雨はきのこには都合がよいが、作物は凶作になりやすく、飢饉の最中(さなか)に大発生したきのこを手あたり次第たべて死んだ人も多かったにちがいない。
たべたきのこがにがくても、からくても、たとえおいしかったとしても、その種類を正しく憶えているのはむずかしい。人に教えてやろうと思っても、出ているのはほんの数日で、すぐ消えてしまう。
「ええと、上が赤くて、下が黄色で、こんな形」と手まねをしてみても通じない。
「こんど見つけたら教えてやるよ」ということになる。たべた人が中毒して死んでしまえば死人に口なし。何を食べたのか誰にもわからない。
今でも中毒患者の胃袋の内容物や食べ残しを調べて、毒きのこの種類を鑑定しているが、かなりむずかしいという話である。運よく生き残ったとしても、治った頃にはもう問題のきのこはなくなっている。いつまでたっても、同じきのこに殺される人が跡を絶たず、いきおい恐怖心だけが残ることになったらしい。
きのこの毒がそれほど効くものなら、一服もって邪魔者を消してやろうとたくらむ悪い奴も出てくる。
紀元五四年のこと、ローマ宮廷できのこによる皇帝暗殺事件が起こった。時の皇帝ティベリウス=クラウディウス(紀元前一〇~紀元後五四)の四度目の妻、小アグリッピナは前夫の息子、ネロ(三七~六八)を皇帝の位につけようと機会をねらっていた。十月十二日の夜、宮廷の毒盛り専門の女ロクスタに命じて、毒きのこを入れた料理をつくらせ、きのこ好きの皇帝にたべさせた。
固唾(かたず)をのんで待っているのにいっこう苦しむ気配もない。それもそのはず、当時のローマ貴族たちはたべすぎると、わざわざゲロを吐いて、またたべるという習慣があったので、毒がまわる間がない。そこで、小アグリッピナは、皇帝の侍医クセノフォンをおどして、別の手を命じた。当時の侍医は皇帝ののどに羽根をつっこんでくすぐり、嘔吐を助けるのも仕事だったらしいが、その羽根の先に毒をぬれというのである。
効果はたちまち現われ、皇帝は悶絶し、翌日の昼には買収されていた親衛隊にかつがれてネロが帝位にのぼったという。おそらく、暗殺の陰謀に加わっていたためだろう。ネロの親衛隊長で哲学者セネカ(紀元前四頃~紀元後六五)の友人セレヌスとその家臣たちもやはり毒きのこで殺されたという。
小アグリッピナの溺愛(できあい)した息子ネロは乱行を重ね、ローマを火の海にし、キリスト教徒を虐殺し、ついには母まで殺してしまうほどの暴君となり、「皇帝を毒殺することで彼女はもう一つの毒、自分の息子ネロを世の中と彼女自身へ贈ったのである」と、プリニウスを嘆かせることになったのである。
この暗殺に使われたきのこが何であったか確かではないが、以下のプリニウスの文章からすると、タマゴテングタケだったように思える。
「毒きのこはうす紅色をしているので、たやすく見分けられる。見かけが悪く、中が鉛色で、ひだが割れており、かさのふちは白っぽくなっている。ただし、すべてのきのこがこんなふうではない。外を包むからから出てきて、かさに白い点をつけているごくふつうのきのこに似た種類もある。
このきのこをつくるために土はまず一つの塊になり、あとからそのなかにきのこができる。それはちょうど卵の黄味のように見える。また、生まれたてのきのこはひながするようにからを好んでたべるらしい。きのこができると、からが割れ、からはきのこが大きくなるにつれて、じくの下に吸いこまれてゆく。きのこのもとは湿った土のすっぱい汁や粘液か、ドングリをつける樹の根からやってくる。
はじめは泡よりもうすいが、生長するにつれて羊皮紙のようにかたくなり、それから、われわれがいうきのこが生まれる。こんな命とりのきのこにあたるのは運が悪いとしかいいようがない。(中略)田舎の人か自分で集めた人以外、誰が見分けられるというのだろう」
少なくとも、きのこの生長のしかたはテングタケ属のもので、かさが赤くないところを見ると、ベニテングタケではない。タマゴテングタケは広葉樹の根に菌根をつくる菌であり、ドングリのなる樹の根から出てくるというのは心憎い観察である。
タマゴテングタケとドクツルタケによる中毒死は大昔から多かったものとみえる。フランスのある町で十五世紀初めの墓を移していた作業員たちが一家七人のミイラ化した遺体を見つけた。死者の顔は見るも無惨、苦痛のためにゆがんでおり、診断した医者は即座にきのこ中毒で死んだものと断定したという。殺人か過失かわからないが、なんとなく無気味な話である。
一九一八年のパリの裁判記録によると、タマゴテングタケを使った殺人事件が起こっている。動機はわからないが、ある男が自分の友人たちに生命保険に加入するよう勧誘し、はいってくれた御礼だと称して、パリの私邸に皆を招待した。前日、年とった下男に毒きのこの形を教えて集めさせておき、パーティーにきのこ料理を出してもてなした。全員が死ぬかと思いきや、何人かが生き残った。
どうやら助かった人は運よく下男がまちがえてとってきた無毒のきのこをたべたせいだったという。この殺人犯も天罰てきめん、獄中で結核が悪化して数年後に死んだそうである。
人を殺すほどの猛毒をもっているきのこはテングタケ属のタマゴテングタケとドクツルタケである。タマゴテングタケは「デス・キャップ」——「亡者の頭巾(ずきん)」か「三角烏帽子(えぼし)」とでも訳すのか、不吉な名がついている。ドクツルタケはまっ白で形もきれいなせいか、「デストロイング・エンジェル」——「殺しの天使」というおそろしい異名がある。
いずれも小さいあいだは白い袋、ユニバーサル・ベールに包まれているので、見たところヨーロッパ人がパフ・ボールといってたべるホコリタケに似ている。大きくなると、かさが黄緑色か黄土色になるタマゴテングタケはうっかりすると、シロオオハラタケなど、ハラタケ属のきのこと見まちがいやすい。
ヨーロッパやアメリカの人はハラタケにも目がないので、よくまちがえて中毒することがあるという。日本ではドクツルタケが多く、タマゴテングタケはまれだが、用心するのにこしたことはない。
タマゴテングタケの有毒成分のなかのファロイジンは肝臓の細胞を破壊し、アマニチンは二〇〇分の一ミリグラムでマウスを殺すほどに強い毒性をもっている。このきのこの中毒症状は四段階に分かれていて複雑で、手後れになりやすい。
たべてから症状が現われるのに六~二四時間かかるが、この間に毒が肝臓や腎臓を冒してゆく。その後、はげしい嘔吐や下痢、腹痛が一日つづいて、いったんおさまる。
患者は治ったものと思って、退院するが、翌日は肝臓や腎臓が完全にこわれ、食後三、四日目には昏睡状態に陥って死ぬという。コレラに似ているので、手当てを誤ることも多いそうである。
日本にもきのこ殺人事件があったらしく、『今昔物語』巻二十八の「金峯山(きんぷせん)の別当、毒茸を食いて酔はざりし語はなし」というのがある。
吉野の奥にある金峯山の寺の長老様が八十をすぎても元気でいっこうに死にそうな気配がない。昔から俗臭ふんぷんの悪僧は珍しくなかったとみえて、七十になる次席の僧が早く長老になりたいばっかりに、そっと殺してしまおうと決心した。あれこれ考えあぐねた末にワタリという猛毒のきのこをうまく料理して、ヒラタケだといってたべさせることにした。
一人でこっそり山へ行き、たくさんとってきて、夜のあいだに上手に煮物にしておいた。翌朝早く長老を呼びにやり、「昨日みごとなヒラタケを人からもらいましたので、煮物にしてさしあげようと思い、お呼び立ていたしました。いやあ、年とると、こんなうまいものがたべたくなるものでして」とかなんとかいいながら、ワタリの煮物をあたためて汁のようにし、かゆにそえてごちそうした。
この悪僧は本物のヒラタケをたべてようすを見ていたが、長老様は年ににあわず、パクパクとたべて、湯まで飲んでけろっとしている。
「はて、もうくたばるはず」と待っているが、いっこうにその気配もない。
そのうち長老様、歯のない口をすぼめて、「うふふふ、この年になるまで、こんなに上手に料理したワタリをいただいたことはござらなんだ。ハイ、ごっつぉうさん」とおっしゃった。悪い坊主はほうほうの体で逃げ出したが、昔からかの長老様がワタリに強い人だというのを知らなかったらしい。
ワタリというのはツキヨタケの古い名前だというが、ツキヨタケには人を殺すほどの毒はないので、いずれにしてもこの殺人は失敗したことだろう。
洋の東西をとわず、どの話も未遂に終わるか犯人がすぐわれている。それというのも殺人にきのこを使おうと思うほどの奴ならきっときのこにくわしいはずである。被害者の身近にいるきのこ好きを追えばよい。きのこ好きはさほど多くないので、犯人をあげるのもたやすい。おまけに毒に対する感受性が人によってちがっており、毒がまわるのにも時間がかかる。
ミステリーとしてはいささか間抜けた話になるせいか、シャーロック=ホームズもアガサー=クリスティーも松本清張も使っていないようである。
※本記事は『きのこの自然誌』(山と溪谷社)を一部掲載したものです。
『きのこの自然誌』
ひそやかに光るきのこ、きのこ毒殺人事件、ナメクジは胞子の運び屋…
きのこ学の第一人者による魅惑のきのこエッセイ。
『きのこの自然誌』
著: 小川 真
価格:1188円(税込)
【著者略歴】
小川 真(おがわ・まこと)
1937年、京都生まれ。1962年に京都大学農学部農林生物学科を卒業、1967年に同大学院博士課程を修了。
1968年、農林水産省林業試験場土壌微生物研究室に勤務、森林総合研究所土壌微生物研究室長・きのこ科長、関西総合テクノス、生物環境研究所所長、大阪工業大学客員教授を歴任。農学博士。「森林のノーベル賞」と呼ばれる国際林業研究機関連合ユフロ学術賞のほか、日本林学賞、日経地球環境技術賞、愛・地球賞、日本菌学会教育文化賞受賞。2021年、没。
ヤマケイ文庫 きのこの自然誌
「世界中の誰よりもきのこに詳しかった"きのこ博士“の名著」藤井一至氏(土の研究者)推薦! 「地上に平和をもたらしたのは、きのこだったのだ」小倉ヒラク氏(発酵デザイナー)推薦! きのこ学の第一人者、故・小川真氏がのこした名著『きのこの自然誌』。世界中のきのこを取り上げながら、きのこの不思議な生き方やきのこと人との悲喜こもごもについて語る「魅惑のきのこエッセイ」です。
こちらの連載もおすすめ
編集部おすすめ記事

- 道具・装備
- はじめての登山装備
【初心者向け】チェーンスパイクの基礎知識。軽アイゼンとの違いは? 雪山にはどこまで使える?

- 道具・装備
「ただのインナーとは違う」圧倒的な温かさと品質! 冬の低山・雪山で大活躍の最強ベースレイヤー13選

- コースガイド
- 下山メシのよろこび
丹沢・シダンゴ山でのんびり低山歩き。昭和レトロな食堂で「ザクッ、じゅわー」な定食を味わう

- コースガイド
- 読者レポート
初冬の高尾山を独り占め。のんびり低山ハイクを楽しむ

- その他
山仲間にグルメを贈ろう! 2025年のおすすめプレゼント&ギフト5選

- その他