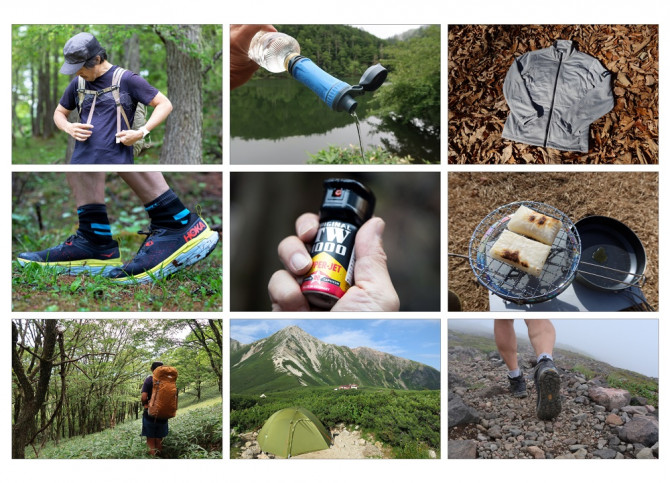『聖職の碑』遭難事故の真実――、不安定な天気による風雨が体力を奪い、爆弾低気圧のように発達した台風が追い打ちをかけた
今から約110年前、1913年8月26~27日に起きた、『聖職の碑』遭難事故。台風接近による暴風雨が直接の原因だが、NOAA(アメリカ海洋大気庁)の再解析データにより解析すると、知られざる真実が明らかになってきた。多くの貴重な教訓を含んだこの遭難事故を、台風シーズンの今、あらためて取り上げる。
目次
山岳防災気象予報士の大矢です。梅雨が明けて下界では、うだるような猛暑が続いていますが、山好きにとっては待ちに待った夏山シーズンです。「梅雨明け10日」ということわざがあって、梅雨が明けてからしばらくは太平洋高気圧が安定して張り出し、好天が続くことが多いものです。
しかし8月に入ると、お盆のころからは太平洋高気圧の勢力にも陰りが見えてきて、早くも秋雨前線が登場したり、台風が日本付近に接近してきたりします。今から110年前に起きた『聖職の碑』遭難事故は、そんな時期に起きた出来事でした。
この遭難事故は、3年前にも「『聖職の碑』の教訓を風化させてはいけない!! 台風と低体温症の恐ろしさ」で取り上げていますが、大きな反響を呼んだ前回の「八甲田山雪中行軍遭難事故」のコラム記事に続いて、今回はNOAA(アメリカ海洋大気庁)の再解析データを使って『聖職の碑』遭難事故の詳細な天気図と気象状況を再現することができましたので、ご紹介いたします。
NOAAの再解析データでは再現が不充分なところは、当時の気象庁の天気図や観測データによって補っています。そして八甲田山雪中行軍遭難事故と同様に当時の記録によるファクトチェックを行なってみると、後世に語り継ぐべき『聖職の碑』遭難事故の知られざる真実が明らかになってきました。

1913年8月に起きた『聖職の碑』遭難事故の概要
新田次郎の小説、そして鶴田浩二が主演した映画『聖職の碑』であまりにも有名な遭難事故ですが、残された記録から事故の経緯をあらためてまとめてみました。長野県箕輪町のWebサイトに詳しい資料がありますので、ご覧になるとよいと思います。
中箕輪(なかみのわ)尋常高等小学校(中学生の年齢に相当。現在の町立箕輪中学校)では明治44年から夏に木曽駒ヶ岳への集団登山を毎年行なっていた。3回目となる大正2年は8月26日から27日にかけて行なわれ、生徒25名を含む37名が参加して5時40分ごろに学校から歩いて出発した。
10時ごろに内の萱(うちのかや)の発電所に着いて昼食を取っていると、急に黒い雲に覆われ、雷が鳴ってにわか雨が降ったが、すぐに止んでしまった。一行は11時ごろには出発し、桂小場から登山道を登っていった。赤羽校長は皆に「帰ろうではないか」と言ったが、生徒たちは反対してどんどん登っていってしまった。証言によると当時は「猫の目のように変わりやすい天気」だったという。
一行は16時ごろに将棋頭山(標高2730m。現在の西駒山荘付近。当時、まだ山荘はなかった)に着いたが、森林限界から上では吹きさらしの稜線で肌寒く、風雨はだんだんと強くなる一方であった。学校から16kmもの道のりを歩いてからの登山であったため、濃ヶ池付近では疲労と空腹で、かなり弱っていた生徒がいたと記録に残されている。
ようやく18時ごろに宿泊予定であった伊那小屋(現在の宝剣山荘)に着いたが、小屋は焼け落ちて石垣が残るのみであった。一行はただちに残っていた木材を組み合わせて、その上に脱いだ着ゴザ(雨具)やハイマツを広げて、さらに石を置いて重石にして、急ごしらえの屋根を作り一夜を明かそうとした。
しかし夜になるとますます風雨が激しくなり、屋根は飛ばされてしまった。屋根も雨具もなく凍えるような寒さの中で、肩を寄せ合って眠らないように声を掛け合って朝を迎えたが、一人の生徒が力尽きて息を引き取ってしまった。ショックを受けた一行は、ほんの一瞬だけ風雨が弱まったのをきっかけに、台風による嵐の中で下山を開始した。27日の9時ごろのことだったという。
体力の弱い生徒は遅れ、一人また一人と倒れる者が続出した。樹林帯に入ることができた生徒は何とか助かったが、亡くなった生徒を背負った赤羽校長と10名の生徒が低体温症で亡くなるという最悪の事態になってしまった。残された記録によると、救助隊に発見された時に赤羽校長は「(この事故の責任は)おれ一人だ」と言って息を引き取ったという。

それではNOAAの再解析データで再現した天気図から、当時の気象状況を追っていきたいと思います。
前日:沖縄付近と本州の南に台風が停滞
図2に出発の前日の8月25日9時の天気図を示します。沖縄付近と本州の南の小笠原諸島付近に台風があって、ともにほとんど停滞していました。台風の中心気圧はそれぞれ1002hPaと1004hPaですので、この時点ではまだ台風になる前の熱帯低気圧だった可能性があります。
気象庁の天気図(図割愛)では中心気圧はそれぞれ1005hPaと1000hPaですので、NOAAの再解析データは当時の気象状況をほぼ再現できていると思います。

初日:湿った空気の影響で不安定な天気、夜に台風が発達しながら北上
生徒たちが学校を出発して、内の萱の発電所に着く少し前の9時の天気図を図3に示します。沖縄付近にあった台風は不明瞭になった一方、本州の南の台風は998hPaに発達しています。気象庁の天気図では996hPaですので、台風が1日で数hPa発達したことの再現はできています。

このように26日の日中はまだ台風は本州の南にあって、中部山岳から離れた位置にありました。しかし、離れた場所にある台風でも、その周辺には熱帯育ちの非常に湿った空気があります。台風の周囲の反時計回りの風に乗って、非常に湿った空気が中部山岳付近に流れ込んできている様子を図4で再現しています。

色分けは可降水量で、下層から上空までの水蒸気の量を表しています。このように中部山岳では湿った空気が山にぶつかって斜面を登る上昇気流となって、積乱雲が発生しやすい状況でした。これが10時ごろの休憩中に雷雨になった理由です。夏山においては通常、お昼ごろから夜のはじめにかけて雷が鳴りますが、午前中に雷が鳴るということは大気が非常に不安定な状態になっていることを意味します。
その後も台風からの湿った空気により、不安定な天気が続きました。不安定な天気のときは突風も吹きます。こうした気象状況にあったにもかかわらず、一行は小屋に入ればもう大丈夫だとの一心で伊那小屋まで頑張って登ったのでしょう。火事で崩壊した伊那小屋を目の当たりにした一行の落胆の気持ちは、本当に察して余りあるものがあります。
そして夜になると突然、台風は北上を始めます。26日21時の天気図を図5に示します。

接近してくる台風本体による強風のため、急ごしらえの屋根は吹き飛ばされて、屋根にしていた雨具をなくした一行は無防備な姿で暴風雨にさらされたのです。麓の飯田測候所(標高516m)の観測データでは27日の最低気温は19.3℃ですので、標高1000mあたり6℃気温が下がることを考慮すると、伊那小屋付近(標高2866m)では27日の明け方には5℃ぐらいまで気温が下がったと推定されます。
最大で風速15m/sの風が吹いたと推定されますので、体感温度はマイナス10℃(風速1m/sあたり体感温度は1℃低下)になります。さらに濡れた木綿の下着を着ていたため、気化熱によってさらに体温を奪われて、真冬の水温5℃のプールに裸で浸かっているのと同じような状態になってしまったのです。
2日目:台風はさらに発達しながら関東沖を通過、中部山岳は暴風雨
一人の生徒の死をきっかけにして下山を始めたという27日9時の天気図を図6に示します。さらに発達した台風が関東沖に接近し、中部山岳の付近は等圧線の間隔が非常に狭くなっています。NOAAの再解析データは台風の中心気圧は994hPaですが、当時の気象庁の天気図では979hPaまで発達しています。

NOAAの再解析データで台風の中心気圧が再現し切れない理由は、再現モデルの解像度が粗い(約100km間隔)ことが原因と思われます。従って台風の中心付近のような小さなスケールの現象解析には、実測データで補ってやる必要があります。
台風はその後も青線のように関東沖から三陸沖を北上し続け、28日0時には北海道の南に進み、NOAAの再解析データでは中心気圧988hPaまで発達、気象庁の天気図(27日22時)では981hPaでほぼ勢力を維持しており、暴風雨によって東北地方の太平洋側を中心に農作物に大きな被害を与えています。
NOAAの再解析データと気象庁の天気図を合わせると、中部山岳への台風の最接近は27日の11時から12時ごろと推定されます。伊那小屋から森林限界付近にある胸突き八丁ノ頭までのコースタイムは2時間15分で、すでに弱っていた生徒もいることを考えると、9時に伊那小屋から下山を開始したのは残念なことに最悪のタイミングになってしまったのです。
「小石は吹き飛ぶ、みぞれは顔にたたきつけられ、立ってもいられないくらいだった」という証言が残っていますので、気象庁の判断基準(PDF)から推定すると風速20m/sを超える非常に強い風が吹いていたと思われます。
南海上の高い海水温で発達したのち、気温差で爆弾低気圧のように
台風が発達するエネルギーは水蒸気ですので、その水蒸気を供給する海水の温度がある程度高くないと台風は発達しません。一般的には台風が発生・発達するのは海水温が26~27℃以上の海域といわれています。
気象庁では1850年から現在までの世界全体の海水温を実測値から解析したデータベース(COBE-SST2)を整備しています。そしてそのデータはNOAAのWebサイトで公開されており、誰でも入手することができます。
『聖職の碑』遭難事故が起きた1913年8月の海水温の分布を図7に示します。26日の夕方ごろまで台風は海水温が28℃以上の海域で停滞していたことがわかります。これが25日午前中から26日午前中にかけて台風が発達して中心気圧が数hPa低下した理由です。

一方、台風が26日の夜に北上を始めると、海水温が次第に下がっていく海域に入ります。それなのに台風がさらに発達したのはなぜでしょうか。その答えは、本州付近の南北の気温の差にあります。
上空約1500mの気温を図8に示します。本州付近で等温線の間隔が狭くなっており、南北の気温の差が大きくなっていることが分かります。南北の気温の差は、今度は温帯低気圧を発達させるエネルギーになります。いわゆる爆弾低気圧が発生する時には、例外なくその周辺で南北の気温の差が大きくなっています。

今回の台風では北緯32度付近において24時間で中心気圧が17hPa低下(気象庁の天気図)していますが、北緯32度での爆弾低気圧の基準を定義式「中心気圧が24時間で24hPa×sin[緯度]/sin[60度]以上低下」に従って計算すると、14.7hPaになりますので、爆弾低気圧の基準を満たしていることになります。
つまり、台風は本州付近の南北の気温の差によって、急激に発達する温帯低気圧(つまり爆弾低気圧)のように発達したことになります。このメカニズムによって、いったん衰弱した台風や、温帯低気圧に変わった台風が再発達することがあることを覚えておくとよいと思います。
『聖職の碑』遭難事故では、26日の長丁場の行動と不安定な天気で体力を消耗したところを、爆弾低気圧のように発達しながら接近してきた台風が追い打ちをかけたということが、この遭難事故の真相であったと思います。
明暗を分けた判断:同じ学校の別パーティは夜中に下山して全員生還
実は『聖職の碑』遭難事故には、あまり知られていない重要な事実があります。それは同じ学校で同じ日に木曽駒ヶ岳のすぐ北にある経ヶ岳(標高2296m)において、もう一つの集団登山が行なわれていたということです。
生徒4名・教師1名の一行は悪天のため26日の22時に経ヶ岳頂上からの下山を決断し、夜中の27日1時半に麓のお寺にたどり着き、夜を明かした後、8時ごろには全員無事に帰宅しています。
まさに1902年の八甲田山雪中行軍遭難事故の多くの犠牲者を出した青森隊と、全員生還の弘前隊のようなことが『聖職の碑』遭難事故でも起きていたのです。生死を分けたのは、台風の予報精度がなかった時代でも、経ヶ岳登山隊は台風接近によって急激に風雨が強まる状況を的確に把握して、夜の22時にもかかわらず下山の判断をしたことに尽きると思います。
木曽駒ヶ岳登山隊は、4度、判断できるポイントがあったと思います。まず午前中に雷雨に遭った時点、次に胸突き八丁ノ頭付近の森林限界で撤退の判断をしていたら何事も起きなかったでしょう。そして18時に伊那小屋が崩壊していたことを確認した時点、最後のチャンスとして19時から20時に急ごしらえの屋根が吹き飛ばされた時点で下山の判断をしていたら、犠牲者は最小限に留まったかもしれません。
「たら」「れば」は結果論に過ぎませんが、同じ日に同じ山域で全員生還したパーティが存在すれば話は違ってきます。登山においては悪天時の相手は「自然」の猛威ですので、最悪の事態を想定した安全サイドの総合判断が自分自身とメンバーの命を守るという貴重な教訓と思います。
『聖職の碑』遭難事故の貴重な教訓を無駄にしないことが亡くなった人たちへの鎮魂(レクイエム)
この遭難事故には多くの貴重な教訓を含んでおり、決して無駄にしてはなりません。この遭難事故における低体温症と台風についての教訓を以下にまとめておきますので、安全登山の一助となりましたら幸いです。
- 台風が離れた場所にあっても決して油断せず、気象状況に注意すること
- 午前中の雷は大気の状態が非常に不安定な証拠
- 森林限界での進退の判断は、時には生死を分ける重要なポイント
- 体力が消耗すると低体温症の危険にさらされる →昔使われた用語である「疲労凍死」につながる
- 空腹も低体温症のリスクが増えるので、悪天時は特に行動食によるエネルギー補給を心掛ける
- 濡れた身体で強風に吹かれるとアウト(レインウェア着用、風雨が当たらない場所に避難、できれば着替えるなど)
- レインウェアを着ていても、頭や首筋を冷やさないこと(しっかりとフードを被る、首筋に速乾性のタオルを巻くなど)
- 海水温が26~27℃以上の高い海域では台風が発達することがよくある
- 台風が接近してくると急激に風雨が強まる
- 南北の気温の差が大きい日本付近では、台風や温帯低気圧に変わった台風が急発達することがある
目次
プロフィール

大矢康裕
気象予報士No.6329、株式会社デンソーで山岳部、日本気象予報士会東海支部に所属し、山岳防災活動を実施している。
日本気象予報士会CPD認定第1号。1988年と2008年の二度にわたりキリマンジャロに登頂。キリマンジャロ頂上付近の氷河縮小を目の当たりにして、長期予報や気候変動にも関心を持つに至る。
2021年9月までの2年間、岐阜大学大学院工学研究科の研究生。その後も岐阜大学の吉野純教授と共同で、台風や山岳気象の研究も行っている。
2017年には日本気象予報士会の石井賞、2021年には木村賞を受賞。2022年6月と2023年7月にNHKラジオ第一の「石丸謙二郎の山カフェ」にゲスト出演。
著書に『山岳気象遭難の真実 過去と未来を繋いで遭難事故をなくす』(山と溪谷社)
山岳気象遭難の真実~過去と未来を繋いで遭難事故をなくす~
登山と天気は切っても切れない関係だ。気象遭難を避けるためには、天気についてある程度の知識と理解は持ちたいもの。 ふだんから気象情報と山の天気について情報発信し続けている“山岳防災気象予報士”の大矢康裕氏が、山の天気のイロハをさまざまな角度から説明。 過去の遭難事故の貴重な教訓を掘り起こし、将来の気候変動によるリスクも踏まえて遭難事故を解説。