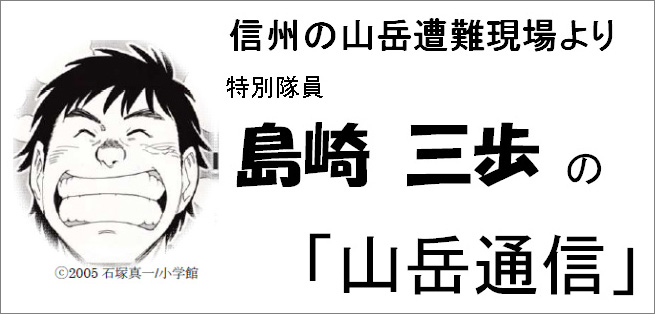でも誰も死ななかった——。雪崩の襲撃を経てついに世界のてっぺんへ【ピッケルと口紅③】
1975年5月、日本女子登山隊が世界で初めて女性によるエベレスト登頂に成功しました。頂に立ったのは副隊長・田部井淳子。そしてその傍らには、遠征準備から苦楽を共にした新聞記者・北村節子がいました。『ピッケルと口紅』は、著者と田部井がその後も長年にわたって挑み続けた世界の山々――シシャパンマ、マッキンリー、南極、そして七大陸の最後の一座・ニューギニア最高峰までの冒険を描いた、真実の「女子冒険譚」です。自らの足で世界を切り拓いてきた女性たちの姿は、今を生きる私たちに力強いメッセージを投げかけてくれます。同書から、BCからC1、C2への荷上げでアタック隊を支援しつつ、ついに登頂の一報を耳にしたシーンを抜粋してご紹介します。
文・写真=北村節子

雪崩がC2を襲撃!アタックメンバーは……
手ずれのした日記の行間からは、忘れていたほんのちょっとしたエピソードが、その時の情景とともに思いがけないほど鮮やかによみがえってきたりもする。
〈4・7。初めてアイスフォールの荷上げに出る。風なく快晴で救われた思い。ザイルはT(注・田部井)と。5・00すぎ、アイゼンをつけていると、あたりが刻々と明るくなる。タウチェの上空がうすずみ色から淡いあい色に変わる。透明な輝き。決してこの色は忘れないだろうな、というような美しさ。(中略)バーム・クーヘン(のような形の氷塊の通称)直下のものすごいトラバース。氷壁がかぶって今にも落ちそう。加えて足もとはぐずぐずのブロック。シェルパのアイゼン跡を信用して行くしかない。それにしてもこの、インクを溶かしたような深い青は何なんだ。何万年も閉じ込められた氷の色の凄さ。これを見ただけでココに来た甲斐があるのかも〉
〈4・18。三原(洋子)、私、中(幸子)の三人でC2へ荷上げ。BCからのシェルパ荷上げで日本からのレターがあるとの交信だったので、それを中継すべく待っていて出発がやや遅れた。(中略)あと二〇〇メートルほどでC2というところで、いきなりローツェ側から大きなナダレ──。一瞬ぽかんとしたが、次の瞬間には(反対側の)西稜側に向かって無我夢中走り出していた。すでにザイルははずしてかなり下方にデポ。三人は自由だったがまるで申し合わせたように。荷物を捨てる余裕なんてない(頭がまわらなかった)。
走る途中、ふと振り返って初めて総毛立つような恐怖におそわれた。モクモクと巨大な煙幕がこちらに向かって、まるで私を追いかけるようにすごいスピードで迫ってくる! 走った。息が切れる、なんて気づきもしなかった。
そして三〇メートルも走ったろうか。視界が急に暗くなり、背中にグイと風圧を感じて、とうとう雪煙に捕えられたんだと思った。ピッケルを思いきり雪面につき立ててしがみつき、口を手袋した手でおおった。
何十秒かあったんだろうか。時間の感覚が思い出せない。目をこらしていた雪面に突然自分の影が出た。雪煙が切れて、日光が届いたのだ。
(中略)三原さんと互いの姿を見て、吹き出してしまった。日が照っている中で、二人とも背中側の半身がまっ白け。シュガーパウダーのような粉雪が、風圧で体に吹きつけられたのだ。緊張からの解放もあり、しばらくゲラゲラと笑い続けた〉
女性隊が、男性シェルパを雇うという事態ならでは、のできごともあったっけ。
〈4・23。塩浦(玲子)さんと二人、C2へ荷上げ。いっしょのシェルパのローテーションがリンジン組(シェルパは四グループに分け、それぞれ〝組頭〟の名で呼んだ)。陽気な連中で楽しい。今日も出発前、テントわきに置いた食料用カートンボックスに腰かけてアイゼンをつけていたら、リンジンが英語プラス日本語プラスシェルパ語で言ってくれましたね。「シオウラさん、ノー・マリッジな。アイ、プレゼント、ラマさん。プリーズ、キープ、ラマさん、ジャパンな。ラマさん、ラムロよ」。早い話が、「塩浦さん、結婚しないんならこのラマさん(リンジンの兄のシェルパ。少年時代チベット仏教の寺でラマ=仏僧=になる修行した、ということからこのニックネーム)くれてやるよ、イイヤツだぜ」、と言うのだ。陽気なリンちゃんが、前歯の抜けた口で言うと全然イヤらしくなくて、これまた陽気な塩浦さんが「何言ってんのよォ。オトコなんて日本にはどっさりなんだからあ」と堂々、大声の日本語でやりあうあたり、聞いているだけで楽しくなる〉
鼻白むシーンがなかったわけではない。
〈5・3。(前略)夕方、アニマが「バッテリーを替えてくれ」とカラのヘッドランプを持ってきた。開けてみると一枚の紙にわいせつきわまる図が描いてある。こちらの反応を見ようということらしく、シェルパテントの中から何人かが様子をうかがう気配があり。「イッツ・ノーグッド」とだけ言って、さっさとバッテリーをセットしてやったので、ご一同ややアテはずれと見える。マジメ評の高いアニマにしてこの体たらく。気分はよくないが、もしや単純で健康な親しみ表現のつもりなら目にカド立ててもおかしいし……。雇用・被雇用、男と女、先進国と後進国(注・当時はまだこの表現が一般的だった)、ヒンズーに近い土地のラマ教(注・同前)──いろいろな関係軸をけっこう考えさせられた〉
そして、この日記帳の中にも、しっかりと刻まれている「あの日」。
〈5・4。六時五分。ギャルツェンの「メンサーブ」(注・女主人を呼ぶシェルパ語)の声で目がさめた。あれ、ギャルツェンはC2にいたんではないのか。あわててテント口を開けると、ギャルツェンとアン・ミンマがたった今、上から下りて来た様子でテントをのぞき込んだ。いつもおっとりしたギャルツェンが、わかりにくい早口の英語でまくし立て、あれ、と思ううち最後の「But nobody die」(でも誰も死ななかった)というひと言がガンと来た。上で何かが起きたんだ!(後略)〉
ヌプツェの壁上部にくっついていた懸垂氷河のブロックが夜半に崩落、いったん雪面にバウンドしたあと、津波のようにC2を襲撃。この事故はもう何回も語られてきたから、ここでは、くり返さないけれど、就寝中の隊員七人がテントもろとも約一五メートル流され、氷塊の下敷きとなった事故で、BCの隊本部はいったんはC2撤収を考える。
が、一番の重傷と伝えられた田部井が、現場から断固「継続」を主張。C1で、ケガ人の手当てにあたりながらBCとC2の通信にハラハラしていた当方は、BCが現場に押し切られたかっこうで「継続」を決めたこの時、改めて「本当にこの隊を引っぱってきた人物はだれか」が見えた気がした。私の中にあった、一部物見遊山的な気分とは全く別のレベルの、とにかくピークを、という山ヤ根性が初めて形となって現われて、私にも「こういうことか」と見えたのである。
再び日記から。〈5・10。C2でミーティングがあるとのことで、朝9・00荷上げを兼ねて登ってゆく。(中略)大きい報道テントを借り、まず隊長から「メンバーによるサポートはどうするか。(ナダレの損害などで)物理的にむずかしい状況にある」という相談があり、結局これはすんなりと「メンバーサポートなし」に決まる。私に言わせれば当然。ナダレがなくて、装備がフルに残っていて下手にメンバーサポートが出たらその方が危ないくらいだ。最強+シェルパ。それでいい。日射がこもって暑いテント内で、アタックメンバーの発表。予想どおりメンバーT(田部井)、W(渡辺百合子)コンビ。発表があったとたん、せまいテントの車座の四方から若い連中の握手の手がのびた。(後略)〉
五月十一日、C2を発ったアタック隊にはしかし、補給線が続かない。十三日、渡辺はC4から撤退、アタックは田部井とサーダー、アン・ツェリンという最少単位に絞られた。
五月十六日。C1からC2への荷上げの途中、開局しっ放しのトランシーバーが、ザックの中で何やら興奮気味に叫び出した。「先ほど登頂の報告がありましたあ。北村さーん、聞こえてるー?」。私はごく自然に、ザイルを組んでいた藤原(すみ子)と歩みよって抱きあった。あたりはピーカンの青い空。白い峰。生き物といえば地上にこの二人だけ、という景観だ。サングラスの下で涙があったかい。互いに背中をたたきあう。
たんたんと、なりゆきを楽しんできたつもりだった。それがこんなに登頂を願っていたなんて。それもあの人の登頂を、と自分で少し驚いて素直にすごくうれしかった。やったんだ!
(ヤマケイ文庫『ピッケルと口紅』より抜粋)
北村節子(きたむら・せつこ)
1949年生まれ。72年に読売新聞東京本社に入社。2001年、読売新聞社調査研究本部主任研究員。08年、退職。日本山岳会会員。主な共著書に『シングルウーマン』(有斐閣)、『「スピン」とは何か』(講談社)ほか多数。本書は『ピッケルと口紅 女たちの地球山旅』(1997年、東京新聞出版局)を復刻したもの。

ピッケルと口紅
| 著 | 北村節子 |
|---|---|
| 発行 | 山と溪谷社 |
| 価格 | 1,210円(税込) |
関連記事
こちらの連載もおすすめ
編集部おすすめ記事

- 道具・装備
- はじめての登山装備
【初心者向け】チェーンスパイクの基礎知識。軽アイゼンとの違いは? 雪山にはどこまで使える?

- 道具・装備
「ただのインナーとは違う」圧倒的な温かさと品質! 冬の低山・雪山で大活躍の最強ベースレイヤー13選

- コースガイド
- 下山メシのよろこび
丹沢・シダンゴ山でのんびり低山歩き。昭和レトロな食堂で「ザクッ、じゅわー」な定食を味わう

- コースガイド
- 読者レポート
初冬の高尾山を独り占め。のんびり低山ハイクを楽しむ

- その他
山仲間にグルメを贈ろう! 2025年のおすすめプレゼント&ギフト5選

- その他